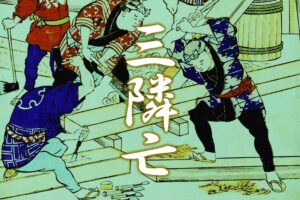■9月22日「彼岸の中日」です。■

「彼岸の中日(ちゅうにち)」です。二十四節気「秋分(しゅうぶん)」を中心に前後3日間、合わせて1週間が「彼岸」とされます。秋の彼岸は、春の彼岸と区別して、「後の彼岸(のちのひがん)」とも呼ばれます。彼岸の中日は、昼と夜の長さがほぼ同じ日、太陽が真東から昇って真西に沈む日、現世と西方浄土、彼岸と此岸(しがん)がもっとも近づく日です。

江戸時代、庶民のあいだで、春と秋の彼岸に「六阿弥陀詣(ろくあみだもうで)」をするのが流行りました。流行の発端は、足立区扇にある浄土宗の寺院「木余り 性翁寺(きあまり しょうおうじ)」の由緒にあります。
神亀2年(725)、この地に居住の足立之荘司宮城宰相(あだちしょうじみやぎさいしょう)の娘「足立姫(あだちひめ)」が、引出物が足りないと嫁ぎ先から罵られ、耐えかねて下女12人とともに荒川に入水しました。父親は悲しみ、諸国の霊場を巡り、熊野権現でお告げをもらい、霊木を見つけて海中に投げ入れると、当地に流れ着いたといいます。
当地に行化(ぎょうけ)していた法相宗(ほっそうしゅう)の高僧「行基(ぎょうき)菩薩」が、六道流転(ろくどうるてん)にちなみ一夜にして、霊木から6体の阿弥陀如来を手ずから造りあげました。これを6つの村里に安置して13人の亡き女性たちのため、また、末代衆生利益のためとしたのが「六阿弥陀(ろくあみだ)」の始まりと伝わります。
「六阿弥陀詣」は女性往生の霊場として、春と秋の彼岸に女性たちが近郊の6ヶ所の阿弥陀仏を巡りました。とくに秋の彼岸は気候もよく、たくさんの女性たちが六阿弥陀詣に出かけたようです。

立山連峰の玄関口、立山町芦峅寺(あしくらじ ※地名)では、彼岸の中日に「布橋灌頂会(ぬのばしかんじょうえ)」が行なわれます。女人禁制だった霊山立山の代わりに、姥堂川(うばどうがわ)に架かる「布橋(ぬのばし)」を渡り、極楽往生を願います。朱色の欄干の布橋は、煩悩の数と同じ108枚の板で組まれていて、「あの世」と「この世」の架け橋とされています。女性たちは、白装束を身に着け白く細い布の目隠しをしたまま、ゆっくりと橋を渡ります。
愛知県、知多半島(ちたはんとう)のほぼ中央に位置する「阿久比町(あぐいちょう)」では、秋の彼岸の中日に、平安の終わりからつづくという仏教行事「虫供養(むしくよう)」が行なわれます。寺院の境内や広場などに、10余りの仮屋を設けて仏画を安置し、中央に「大塔婆(おおとうば)」を建立。導師の先導で同行衆(どうぎょうしゅう)による「百万遍念仏(ひゃくまんべんねんぶつ)」が唱和されます。
◆彼岸沙魚(ひがんはぜ)

昔から「ハゼ釣りは秋の彼岸を過ぎてから」といわれます。「ハゼ(沙魚)」(主に河口近くの汽水域に生息するマハゼのこと)は、大きさも味も十分によくなるのが秋の彼岸のころからで、江戸時代は武家も旦那衆もハゼ釣りを楽しみました。
ハゼは、水気(すいき)の薬になり、とりわけ脚気によく効くとされたため、彼岸の中日のハゼを釣ろうと、夜も明けぬうちから舟宿におしかけ舟を貸切るひとも多く、この日、釣り船屋はおおいに繁盛したとのこと。
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
極楽浄土が此岸にもっとも近づく彼岸の中日。この日に行なわれる六阿弥陀詣、布橋灌頂会、虫供養といった行事には、か弱いいのち、はかなきものを慈しむ御仏のこころを感じます。お彼岸の中日です。これを機会に墓参に出向きましょう。
読者の皆様、お体ご自愛専一の程
筆者敬白