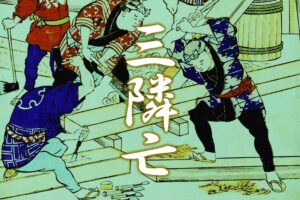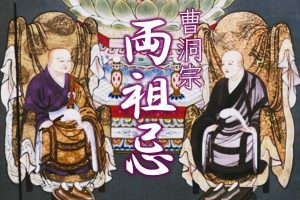■9月19日 奥州水沢、駒形神社(こまがたじんじゃ)「例祭」です。■

陸中国一宮(りくちゅうのくにいちのみや)「駒形神社(こまがたじんじゃ)」は、岩手県奥州市、JR水沢駅から徒歩10分ほどの「水沢公園(みずさわこうえん)」の敷地内に鎮座します。西北西に20kmほど内陸の「駒ヶ岳(こまがたけ)」山頂に「奥宮」、駒ヶ岳山麓の金ケ崎町(かねがさきちょう)に「里宮」があります。中部・関東から東北を中心に広がる全国各地の「駒形神社」の総本社とされています。
御祭神は
「天照大御神(あまてらすおおみかみ)」
「天常立尊(あめのとこたちのみこと)」
「国狭立尊(くにのさたちのみこと)」
「吾勝尊(あかつのみこと)」
「置瀬尊(おきせのみこと)」
「彦火尊(ひこほのみこと)」
を祀り、6柱を「駒形大神(こまがたのおおかみ)」と総称します。

「駒形大神」の6神は、現在「奥宮」となっている駒ヶ岳山頂の社の「棟札(むなふだ)」に記されていたとされます。御神徳は、産業開発(社業繁栄)、交通安全、必勝祈願、合格祈願、方位除け、家内安全、良縁祈願、厄除け、心願成就。
創祀ははっきりしませんが、社伝によると、関東「上毛野国(かみつけののくに)」より遠く陸奥に勢力をのばした「上毛野氏(かみつけのうじ)」が、雄略天皇の御代(456年頃)に「焼石連峰(やけいしれんぽう)」の外輪山のうち、胆沢平野(いさわへいや)から望んで形のよい山のひとつを「駒ヶ岳」と名付け、山頂に「駒形大神」を祀ったのが始まりとされています。「毛野(けの、けぬ)」一族(上毛野氏、下毛野氏)が故郷の「赤城山(あかぎやま)」を信奉し、その外輪山のひとつに「駒ヶ岳」があるため、それにならって新たに支配した地域の山から選んで「駒ヶ岳(駒形山)」と名前をつけていたとのこと。

陸奥国「胆沢城(いさわじょう、いさわのき)」を築いた征夷大将軍「坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)」の崇敬篤く、「源頼義・義家(みなもとのよりよし・よしいえ)」父子は武運を祈願、奥州に栄華を築いた「奥州藤原氏」も信仰しました。駒形神社の分社は東北各県から関東にわたり、その数は百余社に及びます。
藩政期には、伊達仙台藩、南部盛岡藩の両藩に庇護されました。約20年ごとに山頂の社殿が造り替えられ、両藩の藩境の起点として大切にされました。
明治4年(1871)国幣小社となり、以前より水沢県庁近くにあった「鹽竈神社(しおがまじんじゃ)」の本殿を仮遥拝所とし、明治7年(1874)社殿を改修、正式な遥拝所になりました。明治36年(1874)駒ヶ岳山頂より神霊が遷座され、鹽竈神社は駒形神社の境内別宮となりました。
◆駒形神社「例祭」
毎年9月19日、一年の加護に感謝するとともに、陸奥国の繁栄と幸福、五穀豊穣、国土安泰、産業開発、交通安全を祈念する「例祭」が行なわれます。雅楽の演奏のなか、祭儀が厳かに進められ、駒形こどもの杜の園児たちが「浦安の舞」を奉納します。年に2回、5月3日の「奉遷記念大祭(ほうせんきねんたいさい)」と9月19日の「例祭」の日のみ、本殿の御扉(みとびら)が開かれます。

駒形神社
◇岩手県奥州市水沢中上野町1-83(水沢公園内)
◇JR「水沢駅」徒歩10分
◇東北道「水沢IC」12分
◇公式サイト:https://komagata.iwate.jp
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

駒形神社の境内には桜をはじめ多くの樹木があり、水沢公園とともに「ヒガン系の桜」の名所として知られています。「駒形神社及び水沢公園のヒガン系桜群」として岩手県の天然記念物に指定されています。エドヒガン、ベニヒガン、シダレヒガンなど種類も多様で、樹齢はなんと250~300年だそうです。
筆者敬白