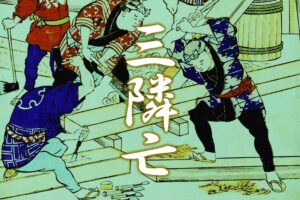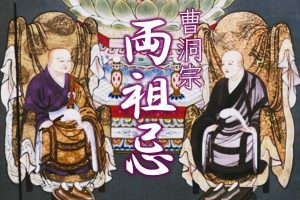■9月14~15日、10月12~13日「岸和田だんじり祭」です。■

「岸和田だんじり祭」は、毎年9月と10月、「岸和田城(きしわだじょう)」下などで行なわれる、約300年の歴史と伝統を誇るお祭りです。元禄16年(1703)、岸和田藩3代藩主「岡部長泰(おかべながやす)」が、「京都伏見稲荷」を城内三の丸に勧請し、米・麦・豆・粟・ヒエなどの「五穀豊穣」を祈願したのが始まりと伝わります。

「地車(だんじり)」とは、白木造りの大きな山車(だし)のこと。『忠臣蔵』などのモチーフの精緻な彫刻がほどこされただんじりに、お囃子連中を乗せ、揃いの法被姿の若者たちが力強く城下町を曳き回します。行列の途中で他のだんじりに会うと、競い合いや衝突になることもあり、「けんか祭り」「血祭り」とも呼ばれます。
一番の見どころは、だんじりが辻々を直角に勢いよく曲がる「やりまわし」です。ブレーキの機能を担う左右の「前テコ」と、舵を取る「後テコ」を操作するタイミングが難しく、腕の見せどころです。「岸城神社(きしきじんじゃ)」に「宮入り」するだんじりが「こなから坂」を一気に駆け上がり、豪快な「やりまわし」を行なう姿は圧巻です。宮入りは「岸和田天神宮(きしわだてんじんぐう)」「弥栄神社(やえいじんじゃ)」でも行なわれます。
日が暮れると、だんじりに大小多くの「提灯(ちょうちん)」がぶら下げられます。子どもたちが主役になって、ほのかな灯りで浮かび上がるだんじりを曳き、走ることもなく、ゆっくりと市中を練り歩く「灯入れ曳行」が行なわれます。昼間の激しさとは打って変わった幻想的な光景が魅力的です。

地車が宮入りする「岸城神社(きしきじんじゃ)」は、南北朝時代に「京都八坂神社」を勧請し、五穀豊穣を祈願する神明社を築いて「産土神(うぶすながみ)」として祀ったのが始まりです。もともとは、「伊勢神宮(いせじんぐう)」より勧請された「天照大御神(あまてらすおおみかみ)」を祀る神明社がありました。

「岸和田城」が築かれると、城主が八坂神社より「素戔嗚尊(すさのおのみこと)」(牛頭天王(ごずてんのう))を勧請し、その後、さらに「八幡神(やはたのかみ、はちまんしん)」(「品陀別命(ほんだわけのみこと:応神天皇)」が勧請され、祀られました。天正13年(1585年)当時の岸和田城主「小出秀政(こいでひでまさ」が、岸和田城の大改修の際に城内へ移し、御宮を建立しました。
厄除け、安産の神として岸和田の人びとに篤く信仰され、岸和田城が「千亀利城(ちきりじょう)」と呼ばれていたことにちなんで「縁結びの神(ちぎりのかみ)」としても知られます。平成23年(2011)には御鎮座650年祭が執り行なわれました。
岸城神社
◇大阪府岸和田市岸城町11-30
◇南海本線「岸和田駅」徒歩10分
◇南海本線「蛸地蔵駅」徒歩7分
◇公式サイト:https://www.kishikijinja.jp
◆「岸和田だんじり祭」公式サイト(岸和田市):https://www.city.kishiwada.lg.jp/site/danjiri/
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

勇壮な祭りで知られる「岸和田だんじり祭」です。夏の終わりは「だんじり」というイメージもすっかり定着しています。公式サイトには曲がり角での見物に関する注意事項が出ていたりして、怪我人が出ないようにといった心配りが感じられます。
まだまだ残暑厳しい時期です。お出かけの際には、熱中症や不慮の事故にご注意下さい。
読者の皆様、お体ご自愛専一の程
筆者敬白