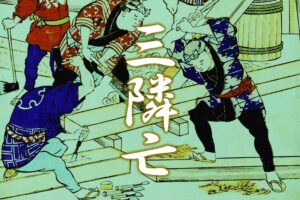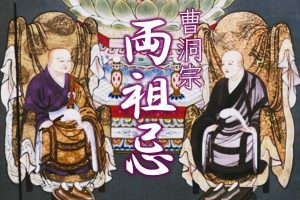■9月12~18日 福岡、筥崎宮「放生会(ほうじょうや)」です。■
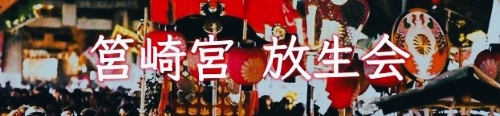
福岡市東区箱崎(はこざき)に鎮座する筑後国一宮「筥崎宮(はこざきぐう)」は、「応神天皇(おうじんてんのう=八幡大神)」を主祭神とし、「神功皇后(じんぐうこうごう=応神天皇の母)」「玉依姫命(たまよりひめのみこと=海の神、神武天皇の母)」を配祀する式内社(名神大社)で、「筥崎八幡宮」とも呼ばれます。

宇佐神宮(うさじんぐう)、石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)、あるいは鶴岡八幡宮(つるがおかはちまんぐう)とともに「日本三大八幡宮」のひとつに数えられます。筑前国には一宮が2社あり、もうひとつが福岡市博多区住吉の「住吉神社(すみよしじんじゃ)」です。

筥崎宮の創建の時期については諸説ありますが、延喜21年(921)醍醐天皇(だいごてんのう)が神勅(しんちょく)により「敵国降伏(てきこくこうふく)」の宸筆(しんぴつ)を下賜され、筑前国穂波郡(現・飯塚市周辺)の「大分宮(だいぶぐう)」を玄界灘(げんかいなだ)に面した土地に移し、延長元年(923)現在の地に遷座したと伝わります。
かつては、筥崎宮のほど近く、博多湾に沿って白砂青松が2kmにわたって広がり、この一帯の松林は「千代松原(ちよのまつばら)」「十里松(じゅうりまつ)」などと呼ばれ、古くより神木と伝えられてきました。「はこざき(筥崎、箱崎)」という社名・地名は、応神天皇誕生のとき胞衣(えな)を箱に入れてこの地に埋め「しるしの松」を植えたという伝説に由来するといわれます。

「敵国降伏」の宸筆は、醍醐天皇以降の天皇も納めたとされ、筥崎宮は37葉の宸筆を第一の神宝(じんぽう、かむだから)としています。「楼門(ろうもん)」に掲げられた「敵国降伏」の扁額(へんがく)は、文永11年(西暦1274)「蒙古襲来(もうこしゅうらい)」により炎上した社殿の再興にあたり「亀山上皇(かめやまじょうこう)」が納めた宸筆を模写拡大したものです。
「敵国降伏」とは、「武力で相手を降伏させる(覇道)ではなく、徳の力をもって導き、相手が自ずから靡(なび)き降伏するという、王道である我が国のあり方(真の勝利)」を説いています。
蒙古襲来の折り「神風(かみかぜ)」が吹いて未曾有の国難を乗り切ったことから「厄除・勝運」の神としても有名です。後世、足利尊氏(あしかわたかうじ)、大内義隆(おおうちよしたか)、小早川隆景(こばやかわたかかげ)、豊臣秀吉(とよとみひでよし)など、名だたる武将が参詣し、武功・文教にすぐれた八幡大神の御神徳を仰ぎました。
蒙古襲来時をはじめ幾度も社殿を焼失しましたが、そのたびに再建され、現在の拝殿・本殿は大内義隆が、楼門は小早川隆景が建立したもので、国の重要文化財に指定されています。
◆放生会

「放生会(ほうじょうえ)」(筥崎宮では「ほうじょうや」と読みます)とは、仏教の戒律「殺生戒(せっしょうかい)」を基に行なわれる、殺生を戒める宗教儀式です。
日本では収穫祭や感謝祭の意味も合わせて、春と秋に全国の寺院や八幡社で行なわれます。捕えた魚や貝、鳥や動物などを殺さずに川や池、山林に放ちます。インドでは釈迦存世の時から行なわれていたと伝わります。
天台宗の開祖「智顗(ちぎ)/天台大師・智者大師」が、漁民が雑魚を捨てている様子を見てそれを憐れみ、自分の持ち物を売って金に換え、魚を買い取って放生池(ほうじょうち)に放したことが始まりとされ、『法華経』を最上の経典とする天台宗の寺院の仏教儀式となりました。
神仏混淆の時代、放生会は神事でした。養老4年(720)「宇佐神宮(うさじんぐう)」で行なわれたのが、日本の放生会の始まりとされています。京都「岩清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)」の放生会は、勅祭「岩清水祭(いわしみずさい)」とも呼ばれ、9月15日に行なわれます。
「筥崎宮の放生会(ほうじょうや)」は、春の「博多どんたく」、夏の「博多祇園山笠」とならび「博多三大祭」のひとつに数えられ、秋の行事として盛大に行なわれます。1000年以上続く最も重要な神事で、「合戦の間多く殺生すよろしく放生会を修すべし」という御神託が起源とされています。「万物の生命をいつくしみ、殺生を戒め、秋の実りに感謝する」お祭りです。

7日7夜にわたり、さまざまな神事や神賑行事が執り行なわれ、参道には「お化け屋敷」や射的、ヨーヨー釣りなど数百軒もの露天が軒をつらね、毎年100万人の参拝客で賑わいます。2年にいちど(西暦の奇数年)、氏子らにより御神幸(御神輿行列)が厳かに行なわれます。開運の縁起物「筥崎宮おはじき」は、「博多人形師」の手により粘土で型取り、素焼きされたもので、放生会の期間中に授与されます。
筥崎宮
◇福岡県福岡市東区箱崎1-22-1
◇市営地下鉄「箱崎宮前駅」徒歩3分
◇JR鹿児島本線「箱崎駅」徒歩8分
◇公式サイト:https://www.hakozakigu.or.jp
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

筥崎宮(箱崎宮)といえば、楼門の扁額に「敵國降伏」の文字が刻まれています。これは元寇の名残です。記録によると筥崎宮が元寇対策場所だったようです。このような歴史を持つ筥崎宮が、殺生を戒める放生会を斎行しているところが、日本人の文化といえるでしょう。
そろそろ、日が沈むと風の涼しさを感じるようになります。
季節の変わり目です。お体ご自愛専一の程
筆者敬白