■9月9日「重陽(ちょうよう)」です。■
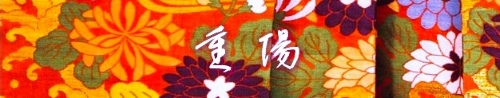
「重陽(ちょうよう)」は、「五節句(ごせっく)」のひとつで、旧暦9月9日の「節会(せちえ)」のことです。「菊の節句」「九月節句」「九日(ここのか)の節句」「おくにち」「おくんち」ともいいます。「9」が2つ重なることから「重九(ちょうきゅう、ちょうく)」とも。

◆中国の「重陽節」
中国では、旧暦9月9日を「重陽節」として祝いました。儒教の古典『易経(えききょう)』では、偶数は陰の数、奇数は陽の数です。陽の数の極である「9」が月と日に重なる(重陽)ことは、めでたさの極みであり、したがって、9月9日は大変めでたい日、めでたい節句とされました。
もともとは、究極の陽の数「9」が2つあるのは陽の気が強すぎるとして「邪気を払う」日でしたが、いつしか転じて「吉祥(この上もなく吉)」の日となりました。「重陽節」を祝う風習は、唐代にはすでに民間の祝い事として定着し、邪気払いとお祝いの両方の意味がありました。
中国の伝統的な「重陽節」の風習は、主に3つありました。

・「登高(とうこう)」(高きに登る)といって、邪気払い・厄払いのため、山や丘などに登る。現在は、もっぱら秋の行楽としてピクニックや山登りに出かける。
・「菊の酒」を飲む。「菊」は延命長寿の霊草とされ、「重陽節」に菊の酒を飲んで養生し、除災招福を祈る。
・「茱萸(しゅゆ)」を髪に挿す、あるいは、茱萸を入れた袋を持って高い山などに登る。「茱萸」とは「カワハジカミ(呉茱萸)」のことで、重陽の頃、芳香を放つ赤い実が熟し、ひとふさ髪に挿すと、邪気除け、寒さ除けになるという。
「重陽節」に食べる「重陽糕(ちょうようこう、重阳糕)」という餅菓子もあります。「糕(こう)」は、ケーキ、こなもち、あるいは「菓子」の総称です。「重陽糕」は、もち米粉とあずきあんを重ねて蒸し、ナッツ、ドライフルーツ、キンモクセイの花の砂糖漬けなどを乗せて華やかに飾ったもので、かつては互いに贈り合っていました。
◆日本の「重陽の節句」
朝廷では、「節句(せっく)」「節日(せちにち)」その他の重要な公事(くじ)のある日に天皇が群臣を朝廷に集めて宴会を賜りました。それを「節会」といいます。
五節句(ごせっく)
「五節句」は、中国の暦で定められた季節の変わり目のこと。日本では、江戸幕府が公的な行事・祝日として定めました。
3月3日「上巳(じょうし)」
5月5日「端午(たんご)」
7月7日「七夕(しちせき)」
9月9日「重陽(ちょうよう)」
のように奇数の重なる日が選ばれていますが、1月だけは1日「元旦(がんたん)」を別格とし、 1月7日「人日(じんじつ)」
が選ばれました。「五節句」は明治6年(1873)に廃止されましたが、暦の上では年中行事として定着しています。
宮中での「重陽の節会」は、中国から伝わった重陽の概念や儀式が取り入れられ、菊の花を観賞し、菊の酒を嗜む会を兼ねたことから「菊花宴(きっかのえん)」とも呼ばれました。『枕草子』や『紫式部日記』にも、菊にまつわる風習が描かれています。

また、前日8日の夜に真綿を菊の花に覆いかぶせておき、9日に菊の花の露と香りが移った真綿で顔やからだを拭うと、不老長寿を保つといわれていました。これを「菊の着綿(きせわた)」といい、後宮(こうきゅう)行事として女官たちのあいだで行なわれていました。「藤原道長(ふじわらのみちなが)」の正室「源倫子(みなもとのりんし、みちこ、ともこ)」から「菊の被綿」を贈られた「紫式部(むらさきしきぶ)」が感激して詠んだ歌は有名です。
菊の露 若ゆばかりに袖ふれて 花のあるじに 千代はゆづらむ
(私はほんの少し若返る程度に袖を触れるだけにとどめておいて、この菊の露がもたらす千年の寿命は、花の持ち主であるあなた様にお譲り申しましょう)

江戸時代には、「重陽の節句」は五節句のなかでもっとも公的な行事となり、武家では菊の花を酒に漬して飲み祝いました。庶民のあいだでは「お九日(おくにち、おくんち)」と呼ばれ、地方によっては秋の収穫と合わせてお祝いしました。この日から酒を温めて飲むなど、大きな季節の節目の日でもありました。九州北部で秋祭りのことを「くんち」「おくんち」と呼ぶのは、こういった重陽の風習の名残りではないかといわれています。
また、旧暦9月9日(現在では10月)は「栗」の収穫期にあたり、「栗の節句」とも呼ばれて「栗飯」や「栗おこわ」などをこしらえ、節句を祝いました。
◆重陽の花「菊」
「菊(きく)」は、「萩(はぎ)」とともに、日本の「秋」を代表する花です。日が短くなると咲き始める「短日植物(たんじつしょくぶつ)」で、晩秋に花の盛りを迎えます。旧暦9月(あるいは10月)を「菊月(きくづき)」とも呼びます。
中国では、菊の花には「不老長寿」の効果があると信じられ、鑑賞用としてより先に、薬用として栽培されていました。日本には、奈良時代末から平安時代初めに渡来したと考えられています。
新暦10~11月、全国各地で「菊花展(きくかてん、きっかてん)」が開かれ、秋の風物詩になっています。「菊師(きくし)」(菊人形師)が作る「菊人形(きくにんぎょう)」も披露されます福井県越前市の「たけふ菊人形」、福島県二本松市の「二本松の菊人形」、山形県南陽市の「南陽の菊まつり」など、菊品評会とともに創意工夫を凝らした菊人形が飾られます。
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

重陽と菊は切り離せません。重陽と菊のように、季節の草花を重ね合わせた暦は「八朔」などがあります。日々暦の意味を知りましょう。世知辛い世の中で、今日という日の意味を知る心のゆとりが欲しいものです。
時節柄お体ご自愛専一の程
筆者敬白













