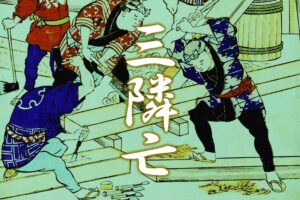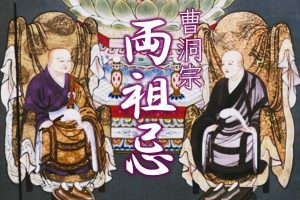■9月7~9日 群馬県太田市、大光院「呑龍上人開山忌(どんりゅうしょうにん かいさんき)」です。■

群馬県太田市金山町(かなやまちょう)の浄土宗の寺院「大光院(だいこういん)」は、慶長18年(1613)「新田義重(にったよししげ、源義重)」の菩提所として「徳川家康(とくがわいえやす)」が建立しました。正式名称は「義重山大光院新田寺(ぎじゅうさんだいこういんにったじ)」。本尊は「阿弥陀如来(あみだにょらい)」。開山は「呑龍上人(どんりゅうしょうにん)」で、大光院は「呑龍さま」と呼ばれて親しまれ、多くのひとが参拝に訪れます。

「金山(かなやま)」は、太田市の市域中央の東に位置する丘陵(最高点は239m)です。金山の北に流れる「渡良瀬川(わたらせがわ)」は、かつて「上野国(こうずけのくに)」と「下野国(しもつけのくに)」の国境(くにざかい)となっていました。
金山は「新田山(にひたやま)」として『万葉集』にも詠まれ、山頂には「新田義貞(にったよしさだ)」を祀る「新田神社(にったじんじゃ)」、戦国時代に築城された山城(やまじろ)「金山城址(かなやまじょうあと)」(国の史跡)があり、南側には太田市街、「大光院」は金山の麓にあります。

「新田義重」は、平安時代から鎌倉時代前期の東国の武将で、「源義家(みなもとのよしいえ、八幡太郎)」の孫、清和源氏「新田氏(にったし)」の祖。平安末期、天仁元年(1108)に起きた浅間山の大噴火により、上野国はほぼ全域が大量の火山灰で覆われて荒廃し、「空閑の郷々(こかんのさとざと)」と呼ばれました。義重はこの地域を再開発して支配下に置き、「新田荘(にったのしょう)」が成立しました。
義重の四男「新田義季(にったよしすえ)」は、新田郡世良田荘徳川(得川)郷(現在の太田市尾島町)に住んで、「徳川(または得川)」を称し、「徳川(得川)義季」と名乗りました。これが「徳川氏(とくがわし)」の発祥といわれています。「徳川家康」は「わが遠祖は、上野国新田の一族徳川氏である」として、「新田義重」を祖と仰ぎ、義重追善(ついぜん)のため、金山の南麓に「大光院」を建立しました。
開山には、徳川家の菩提寺「増上寺(ぞうじょうじ)」12世法主「観智国師(かんちこくし)」の門弟のうち、四哲(してつ)のひとりといわれる「呑龍上人」を迎えました。寺領300石、「関東十八檀林(かんとうじゅうはちだんりん)」(浄土宗の関東における檀林(学問所))のひとつ。
本堂には、阿弥陀三尊像が安置されています。阿弥陀如来立像は「安阿弥(あんなみ、快慶の異名)」の作、観音菩薩像と勢至菩薩像は「運慶(うんけい)」の作と伝わります。

参拝の中心になっている「開山堂(かいさんどう)」の本尊は、呑龍上人の尊像です。尊像は、元和8年(1622)、人びとの強い求めに応じて、呑龍が自身の手で自らの像を作り、開眼を行なったもの。呑龍の没後、尊像を安置するため建立されたのが「開山堂」です。昭和9年(1934)建て替えられ、現在の桃山風建築の堂宇が完成しました。日本初の大型鉄筋コンクリート仏閣建築物として貴重な遺構です。
大光院の正面にある大手門は、家康が大坂城を落城させたその日に落成したため、「吉祥門(きっしょうもん)」と名づけられたといわれています。間口3間、奥行き1間、切妻造(きりづまづくり)で桟瓦葺(さんかわらぶき)。瓦の葺き替え・袖垣(そでがき)の修理のほかは、ほとんど当時のまま保存され古式をよく遺しているとして、太田市の有形文化財に指定されています。
◆子育て呑龍
大光院の開山「呑竜上人(どんりゅうしょうにん)」は、戦国時代から江戸時代初期にかけての浄土宗の僧で、字は「故信(こしん)」、「源蓮社然誉(げんれんしゃ ねんよ)」。武蔵国埼玉郡(現・春日部市)に生まれました。父は「岩付(岩槻)太田氏」の家臣。15歳で「増上寺」の学寮に入り、徳望の高い「観智国師」が住持となって以降、そのもとで修行を積み、四哲のひとりに数えられるようになりました。

江戸時代初期は、長く続いた戦乱の影響で、人心は荒廃し、凶作飢饉が起きると間引きなどが当たり前のように行なわれていました。呑龍は世情を見て悲しみ、人びとに因果応報の仏法を精力的に説くなかで、
一、人を殺さずものの生命を奪わない
一、他人の物品に手をかけない、盗まない
一、みだらで放従な生き方はしない
一、うそ・いつわり・悪口は言わない
一、酒はつつしむ
の五戒をわかりやすく語ってきかせました。そのかたわら、貧困家庭の子どもたちを「弟子入り」と称して大光院の寮に引き取り、家の手伝いができる年齢まで養育し、親もとに帰しました。呑龍にあずけられた子どもたちは皆健康に育ったといいます。慈悲深く愛情に満ちた呑龍の行ないは世に広まり、現在も大光院には「子育て呑龍」に子どもたちの健全な生育を祈願する親子連れが参拝に訪れます。
呑竜は、将軍家康と直接法談を行なったほどの高僧でしたが、一方、庶民のあいだでも呑竜を敬愛し尊崇する人びとが増えていきました。そして、晩年の呑龍にある大きな出来事が降りかかりました。
元和2年(1616)の春、武州の郷士源次兵衛(げんじべえ)という若者が、大光院に駆け込んできて命乞いを願いました。

源次兵衛は、禁鳥の「鶴」を殺した罪で幕吏に追われていました。源次兵衛には難病で苦しむ父がいて、鶴の生き血が病に効くという話を聞き、密かに鶴を捕獲して、その血を病父に与えたのです。当時、江戸近辺では、将軍家の「鷹狩り」の獲物を保護するため、鶴や白鳥などを捕えるのは御法度でした。これを犯せば確実に死罪です。
呑龍は、源次兵衛の父親への孝心に心をうたれ、彼をかくまいました。幕府が身柄の引き渡しを求めてきましたが、呑龍はこれを拒否し、役人たちを一歩も境内に入れませんでした。
しかし、なおも幕府は厳しく追及。呑龍は「いかなる理由があろうとも、いちど救うと誓った以上、懐に入れた窮鳥を見捨てるわけにはいかない」と、あとの者に大光院を頼み、源次兵衛を連れて出奔、信州小諸(こもろ)の浅間山麓に隠れ住みました。呑龍61歳のときのことでした。

小諸で仮住まいした草庵での暮らしは、三度の食事にも事欠き、筵(むしろ)をまとって寒さをしのぐほど困窮しました。難儀を極めた隠棲生活は足かけ5年におよび、このあいだにも土地の人びとが呑龍の徳を慕い、さまざまな祈願を頼みにやってきました。
一方、幕府は、呑龍の位階と大光院住職の身分を剝奪、300石の寺領を没収しました。1000名もの僧徒や衆生は四散せざるをえず、大光院は死の伽藍と化しました。
元和6年(1620)、呑龍の師、増上寺の観智国師が病により入寂。臨終間際、2代将軍徳川秀忠(とくがわひでただ)が遣わした見舞いの使者が最後の希望をたずねると、観智国師は「願わくば大光院住職呑龍の赦免(しゃめん)を」と言い残しました。恩師の遺言によって呑龍は御赦免となり、帰山すると、弟子たちも戻り、参拝の人びとも檀林の学徒も増え、以前にも増して大光院は栄えました。
秀忠は、呑龍を江戸城に招き、これまでの功績を称えて「常紫衣(じょうしえ)」(住職が紫衣を着用して宮中に参内することを許されること)上申を告げ、呑龍は「後水尾天皇(ごみずのおてんのう)」より紫衣を賜わりました。
ほどなくして呑龍は体調を崩し、ある日、「わたしはもうすぐこの世をさる。来る9日正午がそのときである。自分が命を終えたあとは、亡骸は茶毘に附さず、本堂の西に霊廟を建て、そのかたわらに葬りなさい」と遺言を残し、7日間の念仏会を執行したあと、元和9年(1623)8月9日、「南無阿弥陀仏」と十念を唱え、示寂しました。68歳でした。権力に抗い、栄誉高き僧階を捨てて、ひとりの親思いの若者を守った呑龍上人を敬い慕う人びとの思いは、絶えることなく今に至ります
9月7日から9日、大光院では呑龍上人の忌日法要が行なわれます。稚児による「礼讃舞」の奉納、献花、献茶、散華のほか、安産・子育ての祈願も行なわれ、今も変わらず人びとに慕われる「呑龍さま」を忍びます。
義重山大光院新田寺
◇群馬県太田市金山町37-8
◇東武鉄道「太田駅」徒歩20分
◇北関東自動車道「太田桐生IC」約10分
◆「大光院」(太田市観光物産協会):https://www.ota-kanko.jp/member/list/daikoin
◆「まんが大田の歴史・大光院と呑龍上人」(太田市):https://www.city.ota.gunma.jp/page/4212.html