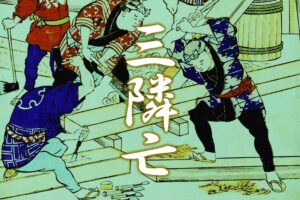■10月20日「えびす講」です。■
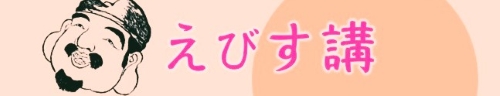
10月20日は「えびす講(えびすこう)」です。「七福神(しちふくじん)」のひとり「えびす(ゑびす)」を祀る行事です。「恵比須講」「恵比寿講」「夷講」「戎講」などと書かれます。

「えびす」は、生業を守護し、商売繁盛、豊漁、豊作をもたらす、日本古来の「福の神」です。台所や茶の間などに祀られます。「烏帽子(えぼし)」をかぶり、「釣り竿」を持ち、「鯛」を抱えた姿をしていることから、もともとは漁民のあいだで信仰されていた神が、商業や農業を営む人びとにも受け入れられ、広く親しまれるようになっていったのではないかと考えられています。
「えびす」の本社は、兵庫県西宮市の「西宮神社(にしのみやじんじゃ)」とされています、社伝によると、「茅渟の海(ちぬのうみ)」(大阪湾)の神戸港の西、「和田岬(わだみさき)」沖に出現した「ひるこ」の御神像を、西宮の鳴尾(なるお)の漁師がすくいあげ、自分の家で祀っていたところ、御神託があったので西の宮地(西宮)に遷し、あらためて祀ったのが西宮神社の始まりと伝えられています。

「ひるこ」は日本神話に登場する神さまです。『古事記』では、「伊邪那岐命(いざなぎのみこと)」と「伊邪那美命(いざなみのみこと)」のあいだに生まれた不具の子とされています。『日本書紀』では、黄泉の国から戻った「伊邪那岐命」が、禊をして黄泉のけがれを落としたとき、「天照大御神(あまてらすおおみかみ)」「月読命(つくよみのみこと)」「須佐之男命(すさのおのみこと)」の「三貴神(さんきしん)」が生まれたのですが、月読命のあと、須佐之男命の前に生まれ落ちたのが「ひるこ」であったとされています。その子は3歳になっても足が立たなかったため、穢れとして海に流されました。「ひるこ」には「水蛭子」「蛭子神」「蛭子命」「蛭児」などの漢字があてられます。
「ひるこの神が流れ着いた」という伝説は日本各地に残っていて、海岸に流れ着いた漂着物を「来訪神(らいほうしん)」とし、福をもたらす神さまとして祀ります。そして、「えびす」も漁業の神、すなわち、海の神であることから、「えびす」と「ひるこ」が結び付いて同一視されるようになりました。
また、大阪市浪速区の「今宮戎神社(いまみやえびすじんじゃ)」は、「大阪七福神」のひとり、商売繁盛の神「えべっさん」を祀ります。こちらの「えびす」は、「事代主神(ことしろぬしのかみ)」とされています。記紀で「大国主命(おおくにぬしのみこと)」の子「事代主神」が「釣り(あるいは漁)」をしていたと描かれたことから、釣りをする神「えびす」と「事代主神」が混同されて習合したとされています。
◆えびす講

旧暦10月「神無月(かんなづき)」は、全国の神々が出雲に集合するため、土地の神さまが不在になります。神の不在のあいだ、留守を守るのが「留守神(るすがみ)」です。留守神となるのは、「荒神(あらがみ、こうじん)」(屋敷やかまどを守る神々)や「こんぴらさま(金毘羅神)」、「大黒さま(大黒神)」、そして「えびすさま」といった神々です。

「えびす講」は、商家の同業者による互助組織や農村で祭祀を行なう地区組織などいろいろなかたちの「講中(こうじゅう)」が作られ行なわれました。また、年中行事のひとつとして個々の家庭でも「えびす」を祀りました。
関東では「二十日えびす」といって、10月20日、あるいは、1月20日に「えびすさま」に参詣して福運を祈ります。関西では「十日えびす」といい、正月10日に行なわれ、町じゅうの人が盛り上がります。「誓文払い(せいもんばらい)」のあと、11月20日に行なうところもあります。「えびすさま」や「えべっさん」を祀る神社の境内や参道には、縁起物の「熊手」や「福笹」などを売る露店が並び、たいへんな人出でにぎわいます。
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

「えびす講」は全国に広く浸透した民間信仰です。家庭では神棚に酒や料理などをお供えしたり、商家では客を招いて尾頭付きの鯛を食べたりします。
由来を調べると、「福の神」と親しまれるえびす神の背景には、「ひるこ」や「事代主神」、来訪神や漂着神など、いくつもの要素が混じり合っていて、歴史や文化の不思議さを思います。
秋が深まり気温が下がってきました。
夜店に出かける際は風邪をひかないようご注意ください。
筆者敬白