■10月19~20日 東京、日本橋「べったら市」です。■
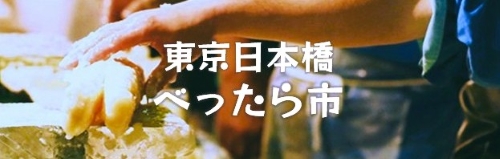
東京都中央区日本橋の「宝田恵比寿神社(たからだえびすじんじゃ)」を中心に日本橋大伝馬町(にほんばしおおでんまちょう)、日本橋本町(にほんばしほんちょう)界隈の通りで開かれる「べったら市」は江戸時代から続く伝統をもつ市で、下町の風物詩となっています。

もともとは翌20日の「えびす講」に使う神像や打出の小槌、懸鯛(かけだい)、切山椒などを売る市でしたが、いつの頃からかここで売られる「べったら漬」が評判になり、市の名として定着しました。現在では、べったら漬の露店をはじめ、七味や飴細工などのさまざまな露店500軒ほどが軒を連ね、多くの人が集まり賑わいます。
「べったら」は、「大根の浅漬」のことで、生干しの大根を甘塩で淡白に漬けた上品な漬物です。大根の旬は、秋から冬にかけてのものなので、浅漬も冬に食べ頃を迎えるということで、旧暦10月19日「えびす講」の宵宮(よみや:前夜)に口開けをして売り出していました。今は日付はそのままに新暦に移行したため、旬よりもひと月ほど早くなっています。

『江戸府内絵本風俗往来』によると、商家の年季勤めの小僧たちが浅漬大根を買い求めて「べったり、べったり」と大声で呼びながらやってくると、娘たちは浅漬の糠粕(かす)に触らないように混雑のなかでよける、よけた先でもまた「べったり、べったり」と呼ぶ声が。これが面白いとして見物しに出る男女で賑わったとか。
「宝田恵比寿神社」は、日本橋七福神の恵比寿さまです。もともと江戸城外の「宝田村」(現在の千代田区、皇居外苑)の鎮守でした。徳川家康の江戸入府の際、江戸城の拡張工事に伴い、慶長11年(1606)宝田、祝田、千代田の3ヶ村は大伝馬町・南伝馬町に移転することになりました。

三河から家康に随行し、宝田村の草創名主(くさわけなぬし)を務めていた「馬込勘解由(まごめかげゆ)」も、住民を率いて現在の日本橋に居を移し、大伝馬町2丁目の伝馬役・名主役を務め、伊勢、駿河、遠江、美濃、尾張などから商人を呼び集めたため、日本橋はあらゆる物資の集散地として栄えました。
宝田村の鎮守社は馬込勘解由の所有地に安置され、「宝田恵比寿神社」となりました。商売繁盛、家族繁栄、火防の守護神として今も広く信仰を集めています。
宝田恵比寿神社
◇東京都中央区日本橋本町3丁目10番11号
◇地下鉄日比谷線「小伝馬町駅」徒歩3分
◇JR「新日本橋駅」徒歩3分
◆参考「日本橋べったら市」(東京にいたか屋):https://www.niitakaya.co.jp/lp/bettaraichi/
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

べったら漬が本当においしくなるのは、もうすこし先のようです。今はスーパーに行けば一年を通じて大抵のものが手に入りますが、大根にかぎらず、食物の旬の頃合いは、いちど旧暦の行事を辿って確かめてみるのもよいかもしれません。
筆者敬白













