■10月17~19日「釜石まつり」です。■
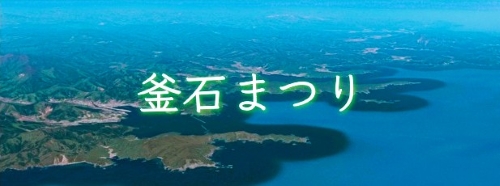
岩手県釜石市の「釜石まつり」は、古くから伝わる「尾崎神社(おさきじんじゃ)」の祭典と「釜石製鉄所」の守護神社である「山神社(さんじんじゃ)」(釜石製鐵所山神社)の祭典を合同で開催するお祭りです。開催日は、10月第3日曜日を最終日とする金、土、日の3日間。

「尾崎神社」は「海の守り神」です。尾崎神社に伝わる縁起によると、「日本武尊(やまとたけるのみこと)」が東征の折、足跡を残した最北端の地で、最終地点は「釜石湾(かまいしわん)」の南側に位置する「尾崎半島(おさきはんとう)」であり、その足跡のしるしとして半島のなかほどに建て置いた「宝剣」を土地の人びとが敬い祀ったことが始まりとされています。

源頼朝の一武将「源為朝(みなもとのためとも)」(鎮西八郎)の三男で「閉伊郡(へいぐん)」の開拓者「閉伊頼基(へいよりもと)」が、承久2年(1220)、逝去の間際に「我東海の守護神とならむ、亡骸は尾崎の宝剣の傍らに葬れ」と遺言を残し、宝剣の傍らに葬られたといわれ、以来「日本武尊」とともに「閉伊頼基」も祭神として合祀されています。
「宝剣」は、尾崎半島の中間の山中にある「奥の院」にあります。さらに、「奥の院」から「青出浜(あおだしはま)」に下りていったところの「奥宮」、半島のつけねの尾崎白浜(おざきしらはま)の「本宮」、そして、釜石湾を挟んで釜石市街の北にある「里宮」の4社で構成されています。

「山神社(釜石製鐵所山神社)」の創建は、1880年頃。釜石は、「近代製鉄発祥の地」です。安政4年(1858)洋式高炉での連続出銑(しゅっせん)に日本で初めて成功、明治27年(1894)、日本で初めて「コークス」を用いた高炉操業に成功しました。釜石市橋野町にある「橋野鉄鉱山(はしのてっこうざん)」(橋野高炉跡及び関連遺跡)は、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼,造船,石炭産業」の構成資産として、平成27年(2015)「世界遺産」に登録されました。
「山神社」の鳥居にかかる「鉄製扁額(てつせいへんがく)」は、初出銑時のコークス銑で造られた扁額で、製鉄史上重要かつ画期的成功を証明する貴重な「歴史遺産」です。釜石市有形文化財。
◆釜石まつり
、海・業業の神さま「尾崎神社」に古くから伝わる例祭と釜石製鐵所の守護神「山神社」の祭典を合同で行なうお祭りで、昭和42年(1967)から「釜石まつり」となりました。

初日
・「宵宮祭」(尾崎神社)
中日
・「曳船まつり」尾崎半島にある尾崎神社「本宮」から船で「里宮」にご神体を奉遷します。お召船を中心に、「虎舞(とらまい)」や神楽を乗せた十数隻の船が「大漁旗」をなびかせて「釜石港」をパレードします。
・「例大祭」(尾崎神社)
・「宵宮祭」(山神社)
最終日
・「例大祭」(山神社)
・「尾崎神社・山神社合同祭」市内目抜き通りを「虎舞」や神楽、山車、「鹿踊(ししおどり)」のほか両神社の神輿が渡御します。

「虎舞」は、獅子舞の一種で、虎模様の胴膜を身にまとい、虎の頭を操って舞う伝統芸能です。「虎は千里往って千里還る」といわれる虎に託して、航海から無事に帰ることを祈る漁民のあいだで伝承されてきたと考えられています。
尾崎神社
◇本宮:岩手県釜石市平田7-130
◇里宮:岩手県釜石市浜町3丁目23
山神社(釜石製鐵所山神社)
◇岩手県釜石市桜木町1-5-1
◆「令和7年 釜石まつり」(釜石観光物産協会):https://kamaishi-kankou.jp/event/7759/
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
釜石の方々の心意気あふれるお祭りです。是非復興した釜石を見に観光にお出かけ下さい。
時節柄、お体ご自愛専一の程
筆者敬白













