■10月13日 和歌山、竈山神社(かまやまじんじゃ)「例祭」です。■
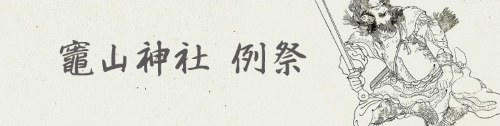
和歌山市南部、「名草山(なぐさやま)」の北方やや東寄りに鎮座する「竈山神社(かまやまじんじゃ)」は、「神武天皇(じんむてんのう)」の長兄「彦五瀬命(ひこいつせのみこと)」を祀ります。本殿の背後には、宮内庁が彦五瀬命の墓と治定する御陵「竈山墓(かまやまのはか)」があります。

「竈山神社」は、式内社で、旧社格は官幣大社。「釜山神社」と表記されることも。主宰神は「彦五瀬命」。左の脇殿に彦五瀬命の弟たち、右に古代の有力な氏族の祖を配祀します。
主祭神:彦五瀬命
配祀神:
(左脇殿)稲飯命、三毛入野命、神日本磐余彦命(神武天皇)
(右脇殿)高倉下命、可美眞手命、天日方竒日方命、天種子命、天富命、道臣命、大久米命、椎根津彦命、頭八咫烏命
◆彦五瀬命
記紀によると、彦五瀬命(ひこいつせのみこと)は、鵜葺草葺不合命(うがやふきあえずのみこと)と玉依姫(たまよりびめ)の長子として生まれました。「五」は「厳(いつ)、斎(いつ)」、「瀬」は「神稲」を意味します。

弟たちに、稲飯命(いないのみこと)、三毛入野命(みけいりののみこと)、神日本磐余彦命(かむやまといわれびこのみこと)がいます。神日本磐余彦命は「神武東征(じんむとうせい)」ののち日本国を建国した神武天皇です。「神武東征」とは、神日本磐余彦命が「日向国(ひゅうがのくに、ひむかのくに)」を出立し、「大和国(やまとのくに)」一帯を征服して、初代天皇の位につくまでの一連の説話のことです。
神日本磐余彦命の一行が大和国に入る際、大和の指導者のひとり長髄彦(ながすねひこ)が「孔舎衛坂(くさえのさか)」で迎え撃ち、戦いとなりました。このとき彦五瀬命は、流れ矢にあたって負傷してしまいます。
日の神の子孫である自分たちは東側から攻めるべきだったのだと考え、日を背にして戦うため、南下して紀伊半島を迂回することにしました。
しかし、道半ば、彦五瀬命は矢傷が悪化し、剣の柄を握りしめて雄たけびをあげ、「なんと悔しいことか。大丈夫(ますらお)として賊に傷つけられ報復もしないうちに死にゆくとは」と叫びました。それゆえ人びとは、この場所を「男之水門(おのみなと)」と号しました。

さらに進軍して「竈山(かまやま)」の地に至ったとき、彦五瀬命はついに絶命し、その地に葬られました。『紀伊続風土記(きいぞくふどき)』によると、彦五瀬命の墓がつくられてすぐに、神社がつくられたとあります。
●竈山墓(かまやまのはか)
「竈山墓」は、竈山神社の本殿の背面、高さ約9mの独立山丘の頂上にあります。直径約6m、高さ約1mの円丘。墳丘の裾には護石があります。『延喜式(えんぎしき)』には記載がありましたが、のちに所在不明となり、明治9年(1876)現在の場所に考定され、宮内庁が管轄しています。
往古は社殿も広大で、皇室御崇敬の大社だったと伝わります。しかし、天正13年(1585)の「豊臣秀吉(とよとみひでよし)」の紀州攻めの際、兵禍により社宝・古文書等を焼失、社領も奪われて荒廃しました。慶長5年(1600)紀伊国に入国した和歌山藩初代藩主「浅野幸長(あさのよしなが)」が小祠を再建。寛文9年(1669)紀州徳川家の祖「徳川頼宣(とくがわよりのぶ)」が社殿を再建しました。

明治に入り、宮内省管轄の「竈山墓」と竈山神社が正式に区分されました。明治14年(1881)村社に列格しましたが、「神武天皇の兄」を祀るという由緒をもって社殿が整備され、明治18年(1885)官幣中社に、大正4年(1915)には官幣大社に異例の昇格を果たしました(現在は別表神社)。
毎年10月13日、例祭「秋の大祭」が斎行されます。彦五瀬命の命日と伝わる5月8日には、「雄誥祭(おたけびさい)」が行なわれます。参拝の人びとはお清めを受けて手を合わせたのち、本殿裏の竈山墓へ行き再び手を合わせ、彦五瀬命の遺徳をしのび、国の平和と繁栄を祈念します。
竈山神社
◇和歌山県和歌山市和田438
◇和歌山電鐵貴志川線「竈山駅」徒歩約15分
◇公式サイト:https://www.kamayama-jinja.com
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

彦五瀬命は神武天皇の長兄で、墓所がこの地にあります。歴史研究が進んで、重要な土地と判明しました。竈山神社は「竈山墓」の南に鎮座し、いまも彦五瀬命の神霊を祀っています。皆さんの土地も何らかの由緒があるかもしれません。風土史を調べてみるのも、お住まいの土地に馴染むことなのでしょう。
読者の皆様、時節柄お身体ご自愛専一の程
筆者敬白













