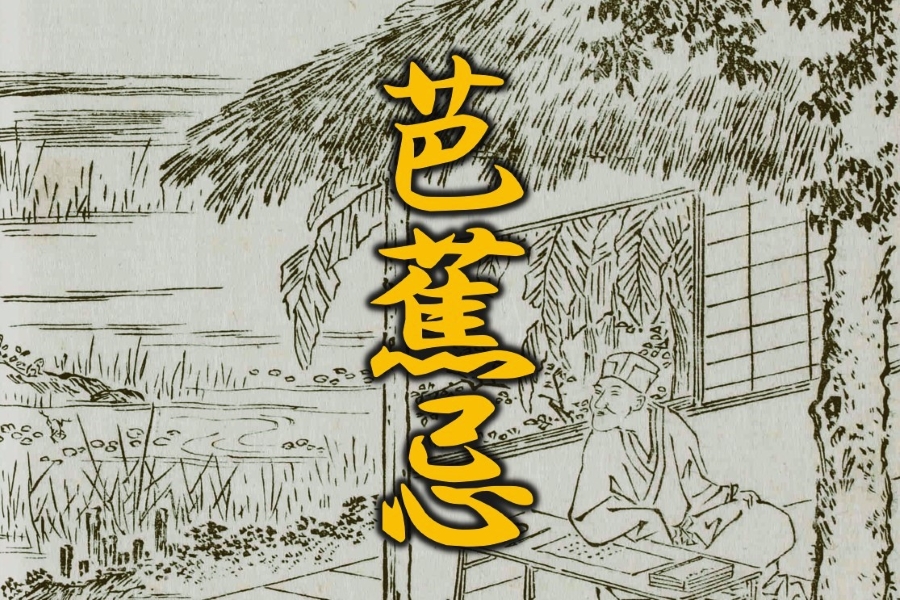■10月12日「芭蕉忌」松尾芭蕉の命日です。■
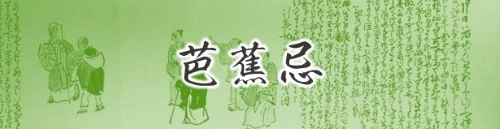
「松尾芭蕉(まつおばしょう)」は、江戸時代前期の「俳諧師(はいかいし)」で、俳諧を革新し「蕉風(しょうふう)」〔※〕を樹立。俳諧に偉大な足跡を残し、明治時代に成立した俳句の源流をつくりました。
古池や蛙飛込む水のをと
閑さや岩にしみ入る蝉の声
五月雨をあつめて早し最上川
夏草や兵共(つはものども)が夢の跡
など、いくつもの句が今もよく知られています。
※蕉風、正風(しょうふう):松尾芭蕉とその門弟の築いた俳風。それまでの俳諧は、洒落やおかしみ、あるいは、奇抜さを主とした知的な遊戯だったが、芭蕉は、さび・しおり・細み・軽みを尊び幽玄閑寂の境地を求め、遊戯だった俳諧を文芸芸術へと発展させた。

伊賀国の松尾与左衛門と妻・梅の次男として誕生。農家とはいえ松尾の苗字を持つ家柄。若くして、伊賀国上野の侍大将・藤堂新七郎良清の嗣子「藤堂良忠(とうどうよしただ)」(俳号は「蝉吟(せんぎん)」)に仕えて共に俳諧を嗜み、京に出て「北村季吟(きたむらきぎん)」に師事して俳諧の道に入りました。
寛文12年(1672)初の句集『貝おほひ』を三重県伊賀市に鎮座する「菅原神社(すがわらじんじゃ)」(通称「上野天神宮」)に奉納。3年後、江戸に移って「宗匠(そうしょう)」(和歌・連歌・俳諧・茶道などの先生)となります。
延宝8年(1680)深川に草庵を結び、門人の李下(りか)から贈られた芭蕉の木を一株植えると大いに茂ったのを見て「芭蕉庵」と名付けます。ところが、天和2年(1683)、「天和の大火(てんなのたいか)」により芭蕉庵は焼失してしまいました。
そこで、門人の甲斐国谷村藩の国家老・高山傳右衛門(高山繁文、通称「傳右衛門」)に招かれて移り住み、しばしば旅に出るように。そして、
『鹿島紀行(かしまきこう)』鹿島神宮へ月見を兼ねて参拝したときの俳諧紀行
『笈の小文(おいのこぶみ)』尾張・伊賀・伊勢・大和・紀伊を経て、須磨・明石を遊覧したときの俳諧紀行
『更科紀行』名古屋から木曽路を通り、更科「姨捨山(おばすてやま)」の月見をしたときの俳諧紀行
などの「紀行文」を残しました。

元禄2年(1689)弟子の「河合曾良(かわいそら)」を伴い、江戸を発って東北、北陸を巡り岐阜の大垣まで『おくのほそ道』の旅に出ます。2年後、江戸に戻りました。
敬慕した「西行(さいぎょう)」「宗祇(そうぎ)」「李白(りはく)」「杜甫(とほ)」のように、芭蕉もまた旅に生きました。その旅の途中、大坂御堂筋の旅宿、花屋仁左衛門(仁右衛門)の離れ座敷で、「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」の句を残し、客死します。これが辞世句に。享年51歳。「秋深き隣は何をする人ぞ」は、死の床に臥す直前に書いた句です。
生前のことば「骸は木曽塚に送るべし」のとおりに、門弟たちによって滋賀県大津市の琵琶湖のほとりに建つ「義仲寺(ぎちゅうじ)」に運ばれ、「木曽義仲(きそよしなか)」の墓(木曽塚)のかたわらに葬られました。

門人「島田又玄(しまだゆうげん)」が、平安末期に生きた義仲と江戸の俳人芭蕉が500年の歳月を超えて寒さを共にしている姿を詠んだといわれる「木曾殿と背中合わせの寒さかな」が有名です。
芭蕉が好んで詠んだ句材「時雨」は、旧暦10月の異称です。忌日10月12日は、俳号に因んで「桃青忌(とうせいき)」、あるいは「時雨忌」「翁忌(おきなき)」などと呼ばれます。
義仲寺
◇滋賀県大津市馬場1-5-12
◇JR琵琶湖線「膳所駅」徒歩10分
◇京阪電鉄/石山坂本線「京阪膳所駅」徒歩10分
◆「義仲寺」(滋賀・びわ湖観光情報):https://www.biwako-visitors.jp/spot/detail/410/
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

「秋深き隣は何をする人ぞ」は、死の床に臥す直前に書いた句とありました。筆者も大病して病床に就いたことがあります。静けさのなか隣人の気配に耳をすます感覚は、共通するものがあります。
俳人の多くが旅先で名句を詠みます。李白・杜甫など生まれた国や時代は違えど、頷ける漢詩に出会うと、悠久の時を共有したような感覚になります。
季節の変わり目です。皆様、お体ご自愛専一の程
筆者敬白