■10月7~9日 日本三大くんち「長崎くんち」です。■
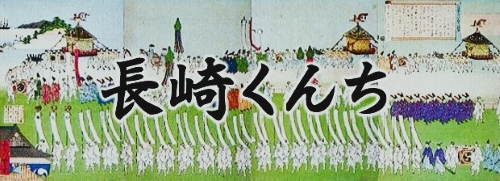
「長崎くんち」は、「諏訪神社(すわじんじゃ)」の秋の例大祭で、「博多おくんち」「唐津くんち」とともに「日本三大くんち」に数えられる長崎最大のイベントです。毎年10月7日から3日間、町を挙げて催されます。国の無形重要民俗文化財。

長崎市の「諏訪神社(すわじんじゃ)」は、長崎の総氏神です。地元では「お諏訪さま」「おすわさん」と呼ばれて親しまれ、「鎮西大社(ちんぜいたいしゃ)」と称えられます。初代宮司となった神道家「青木賢清(あおきかたきよ)」が、戦国時代、「切支丹(キリシタン)」によって破壊された前身の3社(諏訪神社、森崎神社、住吉神社)を、寛永2年(1625)長崎奉行に願い出て合祀、社殿を造営したのが創建とされます。
御祭神は、
「諏訪大神」武神・厄除けの神
「森崎大神」万物創生・縁結び
「住吉大神」海上安全・大漁満足の神
「厄除け、縁結び、海上守護」の神社として崇敬されています。

慶安元年(1648)幕府より「朱印地(しゅいんち)」1万7000坪を得て、荘厳な社殿が造営されました。「中国通商船」「オランダ商人」からも造営資金が寄せられました。安政4年(1857)の火災で社殿のほとんどを焼失してしまいましたが、「孝明天皇(こうめいてんのう)」の思召しにより再建がなされ、明治2年(1869)約10年の歳月をかけて、以前にまさる社殿が完成しました。
昭和20年(1945)8月9日、長崎に原子爆弾が投下されました。当日の諏訪神社の社務日誌には「浦上(うらかみ)全地域より大黒町方面、五島町以南より大村町、引地(ひきち)町方面、灰燼に帰す。古来未曾有の災禍と言うべし」と書かれてあります。諏訪神社は、爆心地からわずか2kmの距離にありましたが、クスノキなどの巨木が繁茂する「諏訪の社(長崎公園)」の背後に位置していたため本殿の火災は免れました。しかし、すさまじい爆風で回廊の屋根が崩壊するなどの被害を被りました。原爆投下からわずか59日目の10月7日、諏訪神社で「奉納踊(ほうのうおどり)」が行なわれ、市民の氏神さまから長崎の復興の一歩が踏み出されました。
昭和59年(1984)の御鎮座360年祭、平成6年(1994)の370年祭にともない2度の記念造営を行ない、現在の社殿が造営されました。
◆諏訪神社、秋の例大祭「長崎くんち」

「おくんち」とは「御九日(おくにち)」のことで、旧暦9月9日「重陽」の節句のこと、または、例祭のことをいいます。「御供日」「御宮日」とも書き、これが訛って「くんち」「おくんち」と呼ばれます。
「長崎くんち」は、寛永11年(1634)「諏訪神社」の神前に、丸山町と寄合両町のふたりの遊女が、謡曲「小舞(こめえ)」を奉納したのが始まりとされています。キリシタン弾圧政策として幕府がこの祭を利用したため、年々盛大になっていきました。長崎奉行の援助もあり、「奉納踊」には「異国趣味」が多く取り入れられ、豪華絢爛な祭礼となりました。
現在、「奉納踊」を出す「踊町(おどっちょう・おどりちょう)」は氏子の人びとで、長崎市内の58ヶ町が7つの組に分けられ、7年にいちど当番がまわってきます。

「奉納踊」の演し物は、大きく分けて「踊り」「曳物(ひきもの)」「担ぎ物(かつぎもの)」「通り物」があります。独特のめずらしいものとしては、「おらんだ万才」「龍踊(じゃおどり)」「鯨の潮吹き」「太皷山(コッコデショ)」「鯱太鼓(しゃちだいこ)」「アニオーさんの輿入れ行列」などなど。踊町の先頭には、ビードロ細工やからくり仕掛けの巨大な「傘鉾(かさぼこ)」が立ち、川船(かわふね)、唐人船(とうじんぶね)、龍船(じゃぶね)、御座船、御朱印船(ごしゅいんせん)、竜宮船(りゅうぐうせん)、阿蘭陀船(おらんだぶね)、南蛮船(なんばんせん)といった船型に車を付けて、大勢で曳き回します。
くんちの観客が掛ける掛け声には、独特の約束があります。

「モッテコーイ!」
いちど退場した曳き物などの演し物を呼び戻す時などに連呼する。「アンコール」の意味。
「ショモーヤレ!」
「所望するからもう1回やれ」の意味。本踊が終わりアンコールをする時に使う。
「フトーマワレ!」
「大きく輪を描いて、雄大に回れ」の意味。傘鉾を回しているときに使う。
「ヨイヤァ!」
「ヤッタ」という意味。川船の網打船頭が投網を投げ、魚が見事網にかかった時や、傘鉾が勇壮に回ったときなどに使う。
会場は市内4ヶ所で、筆頭の諏訪神社前の踊場には、桟敷席のほか、神社大門下の73段の石段坂「長坂(ながさか)」も観客席になります。踊場を正面に見る特等席の「長坂」は、「坂の町長崎」の象徴です。桟敷席と「長坂」が2500人もの観衆で埋め尽くされ、華麗な演し物に「モッテコーイ!」の声が掛かると、祭りの熱気は最高潮に達します。
諏訪神社には、御祭神3柱それぞれの神輿があり、例大祭では、「大波止(おおはと)」御旅所に移す「神輿渡御」が行なわれます。7日午後、神輿が約1000名の行列を従えて市中を練り歩き、御旅所へ渡ります。本社から「長坂」を含む約200段の石段を下るため、これを「お下り(おくだり)」といいます。

9日午後、本社へ神輿が出発、本社へ還る「お上り(おのぼり)」が行なわれます。このとき、3基の神輿が「長坂」73段の石段を一気に駆け上がる「もりこみ」が行なわれ、激しく勇壮な姿に見物の参拝客はひときわ盛り上がります。
鎮西大社「諏訪神社」
◇長崎市上西山町18-15
◇路面電車「諏訪神社」下車
◇「長崎芒塚IC」「出島IC」より約10分
◇公式サイト:https://www.osuwasan.jp
◆例大祭「長崎くんち」(諏訪神社):https://www.osuwasan.jp/kunchi/
◆長崎くんち(長崎伝統芸能振興会):https://nagasaki-kunchi.com
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
あまり知られてはいませんが、キリスト教の布教によって寺社仏閣が焼き払われた歴史を持つ長崎です。「おくんち」は神社の祭礼を幕府がキリスト教弾圧に利用したとあります。
各地の祭礼や忌日などの発祥を調べていると、土地に根付く歴史があることがわかります。「季節のお便り」はそれを紐解き歴史を知る楽しさがあります。
読者の皆様、朝晩はめっきり涼しくなりました。時節柄お体ご自愛専一の程
筆者敬白













