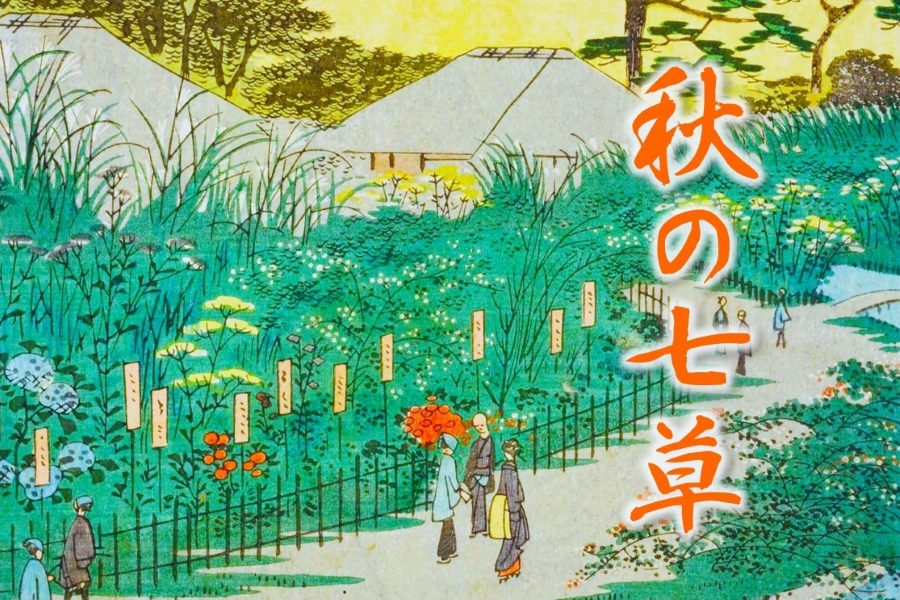◆◆「秋の七草」◆◆
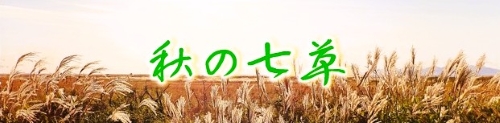
「秋の七草」とは、ハギ、ススキ、クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、キキョウのこと。『万葉集』で「山上憶良(やまのうえのおくら)」が、秋の野の花を詠んだ歌2首が、広まり親しまれるようになったといわれます。
秋の野に咲きたる花を指折りてかき数ふれば七種(ななくさ)の花
萩の花尾花(おばな)葛花(くずはな)なでしこの花女郎花(をみなへし)また藤袴(ふぢばかま)朝がほの花」
秋の野に美しく咲いている花を、指折り数えてみると、ちょうど七種類の花がある。
その七種類の花は、萩の花、尾花、葛の花、撫子の花、女郎花、それに藤袴と朝顔の花である。
憶良が「朝顔」と呼ぶのは「桔梗(キキョウ)」の花だとされています。
秋、野山は、春や夏とはまた異なる趣きの草花で彩られます。「春の七草」は、1月7日「人日(じんじつ)の節句」に「七種菜羹(しちしゅさいこう:七草がゆ、七種がゆ)」を食べて無病を祈るという「食」にまつわる風習ですが、「秋の七草」は秋の草花を愛で、風情を楽しむ習慣です。秋の七草をはじめ、吾亦紅(われもこう)や野菊などの「秋草」が咲く野原を「花野(はなの)」といいます。
なにとなく君に待たるるここちして出でし花野の夕月夜かな ―― 与謝野晶子『みだれ髪』

萩(はぎ)
マメ科ハギ属。花は豆のような蝶形花。枝や葉は家畜の飼料や屋根ふきの材料。葉を落とした枝を束ねて箒(ほうき)に。根を煎じて眩暈やのぼせの薬にするなど人々の生活にも溶け込んでいました。
秋萩をしがらみ伏せて鳴く鹿の目には見えずて音のさやけさ ―― よみ人知らず
秋萩を身にからみつけ倒しながら鳴く鹿の、姿は目に見えないけれど、その声はありありと聞こえることよ。

薄(すすき)
イネ科ススキ属。収穫したものを悪霊から守る力があるとされます。屋根材のほかに炭俵、家畜の餌などに利用されます。中秋の名月では魔除け、災難除けとして飾られます。「尾花(おばな)」とも。「芒」という漢字もしばしば使われます。
山は暮れて野は黄昏の芒かな ―― 与謝蕪村

桔梗(ききょう)
キキョウ科キキョウ属。紫または白の美しい花。漢方では太い根を干して咳や咽喉の薬に。薬用成分サポニンを含有し、昆虫による食害から自らを守ります。かつて漢名で「キチコウ」と読みました。『万葉集』などに登場する「朝顔」は桔梗のことだと考えられています。
平安時代の陰陽師「安倍晴明」は、魔除けの呪符「五芒星」を桔梗の花に見立てて紋様としました。武家の家紋にも多く取り入れられています。

撫子(なでしこ)
ナデシコ科ナデシコ属、薄紅色の可憐な花をつけます。「撫子」は「撫でし子」、つまり、愛しい子、かわいがっている子の意味。英語の pink はもともと撫子の花を意味していましたが、のちにピンク色そのものも指すようになりました。
中国から平安時代に渡来した「石竹(せきちく)」を「唐撫子(からなでしこ)」と呼ぶのに対して、日本古来の種を「大和撫子(やまとなでしこ)」と呼んで、日本女性を美称しました。
撫子の露もさながらきらめきたる小袿に、御ぐしはこぼれかゝりて少し傾ぶきかゝり給へる傍めまめやかに光を放つとはかゝるをやと見え給ふ。よろしきをだに人の親はいかゞはみなす。ましてかく類ひなき御有樣どもなめれば世に知らぬ心の闇に惑ひ給ふもことわりなるべし。――『増鏡』
なでしこの花がそのまま煌めいている模様の小袿(こうちぎ)に御髪がこぼれかかって、少し前かがみになっていらっしゃるのが、まさに光を放つとはこういうことだろうかというお姿であられた。世間並みの娘であっても人の親は良いものと思ってしまうものである。まして、このような類なき御容姿であれば、父の実雄公が親心の深みに迷われてしまうのも、もっともなことであろう。

葛(くず)
マメ科クズ属、周囲の木をツルで覆ってしまう程の生命力。大和の国(奈良県)の国栖(くず)が葛粉の産地であったことから。「葛」は漢名。「まくず」とも。根に含まれる多量の澱粉は葛粉の原料になり、漢方薬で使われる「葛根(かっこん)」にも用いられます。ツルの繊維で「葛布(くずふ、くずぬの)」を織ります。秋、紫色の香りのある蝶形の花が咲き、紅葉も美しい。
わが屋戸(やど)のくず葉日に異に(ひにけに)色づきぬ来まさぬ君は何情ぞも ―― 作者未詳
「我屋戸之田葛葉日殊色付奴不来座君者何情曽毛」わが家の葛の葉が日増しに色づいてきましたのに、いつまでたってもお出でにならないあなたは一体どういうおつもりなのでしょう。

藤袴(ふじばかま)
キク科ヒヨドリバナ属。花の色は藤色で、花弁の形が袴の形をしているのが名前の所以。桜餅のようなよい香りがします。平安時代の女性は、干した藤袴の茎や葉を水につけて髪を洗いました。また、防虫剤や芳香剤、お茶などにも利用していました。

女郎花(おみなえし)
オミナエシ科オミナエシ属。山野に生える黄色い清楚な花。「おみな」は「女」の意。「えし」は古語「へし(圧)」のことで、美女を圧倒する美しさから。
餅米で炊く御飯「おこわ」を「男飯」といったのに対して「粟(あわ)御飯」のことを「女飯」といい、花が粟の粒のように黄色く粒々していることから「女飯」を「おみなめし」「おみなえし」というようになったという説もあります。「女郎花」と書くようになったのは平安時代の中頃。同科で白い花を咲かせる「男郎花(おとこえし)」という草もあります。
手に取れば袖さへにほふ女郎花この白露に散らまく惜しも ―― よみ人知らず
手に折り取ると、袖までもその色に染まりそうな女郎花が、この置かれた白露のために散るのは惜しいことだなあ。
をみなへし秋萩交じる芦城の野今日を始めて万代に見む ―― よみ人知らず
女郎花が咲き、萩の花も交じるこの美しい芦城野(あしきの)には、今日より始めて万年のあとまでも変わることなく来て眺めたいものだ。