■11月7日(旧10月亥の日)「炉開き(ろびらき)」です。■
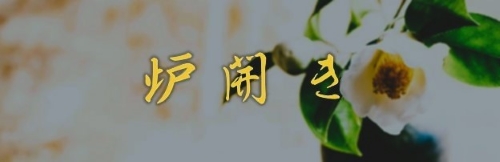
茶室では、春から半年間使った「風炉(ふろ)」を仕舞い、「炉(ろ)」を開きます。

「炉」とは、茶室の畳を切って五徳を入れて炭を組む小さな「いろり」のことです。11月から4月まで使用されるものを「炉」、5月から10月頃まで使用されるものを「風呂」といいます。風呂は、暑い季節に狭い茶室の温度が高くなりすぎないように、炭を入れるための金属製の容器のことです。
炉開きに合わせて、その年5月に摘まれた「新茶」を使い始めます。茶壷の口を切って使い始めるので「口切り(くちきり)」ともいいます。
お茶の世界では、炉を開いて新しい季節を迎え、新茶の入った壷を開けるこの時期を「茶人の正月」として祝います。昔は茶壷を床の間に飾り、お正月と同じように客を茶室に招き、新茶を味わい祝ったそうです。いまは新茶の口を切って客人をもてなすお茶の世界の一大イベントになっています。
炉開きや仏間に隣る四畳半 ―― 夏目漱石
炉を開く二番亥の子の暖き ―― 高浜虚子
炉をひらく火のひえびえともえにけり ―― 飯田蛇笏
◆防火とイノシシ

そもそも「炉開き」の「炉」は、具体的には、屋内の土間や床の一部を切って設ける「囲炉裏(いろり)」、床に炉を切って櫓(やぐら)を乗せてふとんで覆う「掘炬燵(ほりごたつ)」、行火(あんか)や火入(ひいれ)に櫓をかぶせてふとんを掛ける「置炬燵(おきごたつ)」、木・陶磁器・金属で作る「火鉢」などのことで、明治の中頃までは、「炉開き」というと、旧暦10月の亥の日、囲炉裏や炬燵を開いて、来客にも火鉢を出すという一般的な習慣でした。
『一年諸事雑記帳』によると、家の中で火を起こして炭や灰で調節しながら使う道具類は、火事の原因になることが多かったので、「防火」のおまじないとして縁起を担ぎ「亥の日」に炉開きをするようになったそうです。というのも、十二支の「亥」がほぼ北に位置し、「水」を象徴していたからです。

十二支の「亥」だけでなく、動物の「猪(いのしし)」も、防火のおまじないとして飼われていたそうです。火事が多かった「吉原」あたりの往来を猪がうろうろしていたり、8大将軍「徳川吉宗」も柳原土手(やなぎはらどて)下に猪を放し飼いにしたり、幕末、呉服屋の大店がこぞって猪を飼っていたりしていたとか。
江戸のなかばころから、いわゆる「ももんじ屋」といった野獣野鳥の肉を出す料理屋が増え、猪がよく食べられていたのは、防火のおまじないとして放し飼いにされている猪が市中にたくさんいたからという背景もあるようです。
『江戸府内絵本風俗往来』には、江戸城でも10月の初亥の日に、城中の部屋ごとに火鉢を出していたとあります。この日は、「玄猪(げんちょ)のご祝儀」として大名諸侯は暮六ツ時(日暮れ過ぎ)前に登城し、その際、大手門と桜田門の外で「大篝火(おおかがりび)」が焚かれました。これを「玄猪の御篝火(げんちょのおんかがりび)」と呼んだそうです。
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

かつては家のなかのいろいろな場所で火を使っていました。亥や猪を防火のシンボルのように扱うのは、迷信といえば迷信なのですが、それだけ人びとの火事に対する恐怖は深刻で、防火の意識も高かったのだろうと思われます。
昨今、家庭の台所でも電気で煮炊きをするようになり、日常生活で火そのものをほとんど見たことがない子どもたちも少なくないようです。しかしそのぶん油断せず、とくに木枯らしが吹き抜けるこの時期は「火の用心」です。
朝夕が冷え込む季節です。
お風邪などお召しにならない様お体ご自愛専一の程
筆者敬白













