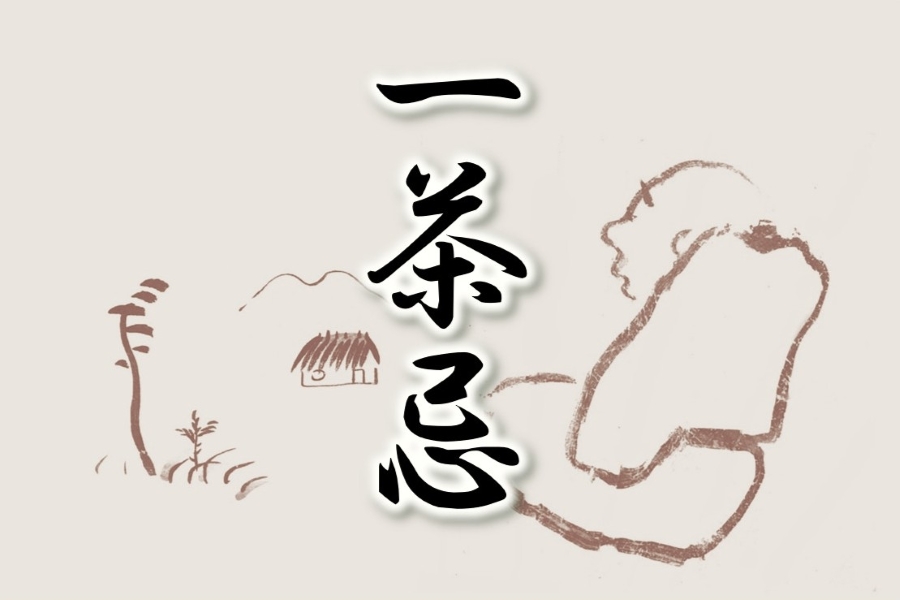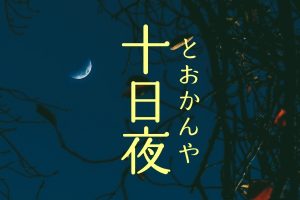■11月19日「一茶忌」です。■
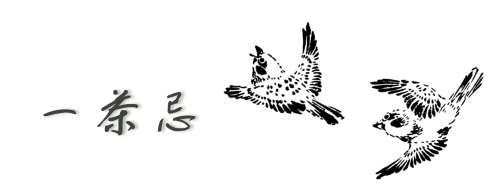
旧暦11月19日は、俳人「小林一茶(こばやしいっさ)」の忌日です。一茶は、松尾芭蕉(まつおばしょう)、与謝蕪村(よさぶそん)と並び、江戸時代を代表する俳諧師のひとり。方言や俗語を交えたり、社会的に弱い立場の人びとの姿を小さな生きものに反映させたりするなど、庶民の生活に寄り添う作品は今もなお多くのひとに愛され、親しまれています。

宝暦13年(1763)信濃国の北部、北国街道(ほっこくかいどう)の宿駅「柏原(かしわばら)」(現・長野県上水内郡信濃町)で中農の長男として生まれました。本名「弥太郎」。3歳の時に生母を失い、8歳で継母を迎えましたが、継母に馴染めず、15歳で江戸に奉公に出されました。
いくつもの職を転々としながら、20歳のころから俳諧を始め、25歳のときに「二六庵竹阿(にろくあんちくあ)」(小林竹阿)に師事。奉公時代の10年間は非常に苦しい生活だったと一茶本人が振り返っています。
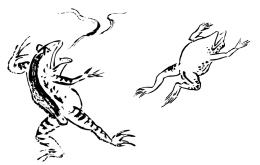
近畿・四国・九州など各地を行脚をし、日本や中国の古典を貪欲に学んで俳諧師として修行を積み、やがて名を知られるようになりました。蔵前の札差で俳人の「夏目成美(なつめせいび)」などから経済的な援助を受けつつ、貧しいながらも俳諧師として生計を立てていました。
享和元年(1801)、父親の病の知らせを受けた一茶は、故郷にもどり看病しますが、父親はひと月後に亡くなります。そのとき、農家を継ぎ一家をもり立ててきた弟・継母と遺産相続で対立し、以後13年にわたって長く苦しい骨肉の争いがつづくことになります。文化9年(1812)50歳で再び柏原に帰郷、翌年ようやく遺産相続が和解しました。故郷に戻ったのは冬のころで、山深い奥信濃はすでに厚い雪に覆われていました。
これがまあつひの栖(すみか)か雪五尺

残りの人生をこの地で終えるのだと決意した一茶が、雪に埋もれるふるさとの景色を前に詠んだ句には、複雑な感慨が読み取れます。
一茶は、生涯で3人の妻を迎えて4人の子どもが生まれましたが、みな幼くして亡くなりました。さらに、文政10年(1827)6月、柏原宿のほとんどを焼失する大火が起き、一茶の家はひと棟の土蔵を除いて全焼しました。焼け残った土蔵で暮らしていた一茶は、同年11月19日、その土蔵のなかで65歳の生涯をとじました。
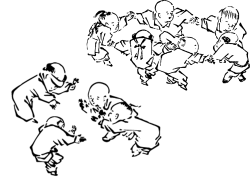
子どもを欲しがっていた一茶でしたが、3番めの妻が身ごもっていた女児を無事に産んだのは、皮肉にも彼の死後のことでした。娘は明治まで生きて一茶の血脈を後世に伝えました。
家庭的に恵まれず不幸が続いた一茶でしたが、自身の経験にもとづく独自の作風を示し、彼の作品は権威に虐げられる人びとから支持を得ました。死の直前まで北信濃の門人を訪ねて精力的に俳句指導や出版活動を行ない、2万句を超えるともいわれるたくさんの作品を残しました。死後、編集出版された句集も多く、有名な俳諧俳文集『おらが春』(文政2年(1819))も、そうしたなかの一冊です。
目出度さもちう位也おらが春
一茶は当時からとても人気のある俳人でしたが、死後もますます評価が高まり、大正7年(1918)には教科書に一茶の句が載りました。
雀の子そこのけそこのけお馬が通る
やれ打つな蝿が手をすり足をする
やせ蛙負けるな一茶是にあり
11月19日、故郷柏原の「一茶記念館」では、一茶を偲んで、法要・俳句大会・そば会などが行なわれます。
一茶記念館
◇長野県上水内郡信濃町柏原2437-2
◇JR「長野駅」~しなの線「黒姫駅」徒歩5分
◇上信越自動車道「信濃町IC」3分
◇公式サイト:https://www.issakinenkan.com
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
皆さん一度は一茶の句を耳にしたことがあるでしょう。200年近い歳月が流れた今もなお一茶は人びとに愛されています。一部の作品は英訳され海外にも伝わっています。
ともかくもあなた任せのとしの暮
Trusting the Buddha, good and bad,
I bid farewell
To the departing year.(英訳:鈴木大拙)

「あなた」とは阿弥陀如来のことです。禍福は糾える縄のごとし。幸も不幸もどうしようもないけれど自分は阿弥陀さまを信じていくのだという一茶の素朴な気持ちが読み取れます。
災害や戦争など災禍は次々にやってきますが、変わらぬものに思いを馳せてみるのも心のゆとりです。
日に日に朝夕が冷え込むようになってきました。
読者の皆様、お体ご自愛専一の程
筆写敬白