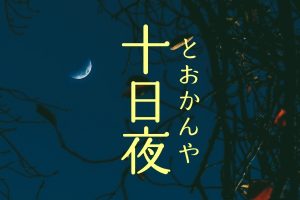■11月9日 京都「嵐山もみじ祭り」です。■

毎年11月の第2日曜日「嵐山もみじ祭り」が行なわれます。これは、天下の名勝「嵐山(あらしやま)」の紅葉を讃え、嵐山一帯を守護する「蔵王大権現(ざおうだいごんげん)」に感謝する神事です。「渡月橋(とげつきょう)」上流一帯に浮かんだ船上舞台では、由緒ある史蹟や文化、この地にゆかりの深い芸能が披露されます。

「嵐山」は、標高382m、、京都市西部にあります。北は嵯峨野(さがの)、南は桂(かつら)と、名所旧跡の多い観光の中心地です。四季折々の表情を見せる渡月橋周辺は、桜と紅葉の名所として多くの観光客が訪れます。
嵐山を象徴する「渡月橋」は、「嵐橋」とも呼ばれ、古く平安時代初めの承和3年(836)、空海の高弟「道昌(どうしょう)」が「大堰川(おおいがわ)」を修築した折に架橋したと伝わります。「亀山上皇(かめやまじょうこう)」が、曇りない夜空に月がさながら橋を渡るようなさまを見て「くまなき月の渡るに似る」と述べたとのこと。これが「渡月橋」の名前の由来といわれます。
渡月橋を境に、上流の「大堰川」から「桂川(かつらがわ)」と名を変えて流れる川で、平安時代の貴族たちが舟遊びや紅葉狩りを楽しみました。
◆嵐山の公式サイト「THE 嵐山」:https://www.arashiyamahoshokai.com

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

亀山上皇と聞き馳せる感覚は、鎌倉時代中期の元寇(蒙古襲来)に際し、「我が身を以て国難にかわらん」と「敵国降伏」の祈願をしたこと。その一方で、渡月橋のあり様を「くまなき月の渡るに似る」と表現し、橋の名前の由来となったといいます。激しい一面と風情を愛でる一面とをあわせもつ人物だったようです。
秋の朝夕の温度差からお風邪などお召しにならないよう
お体ご自愛専一位の程
筆者敬白