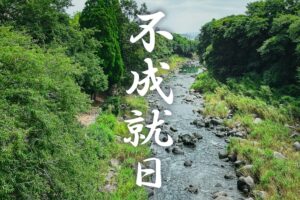■5月19~21日 福井県坂井市「三国祭(みくにまつり)」です。■
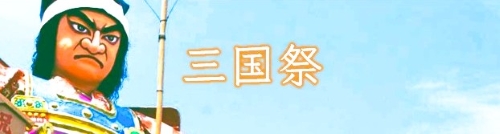
「三国祭(みくにまつり)」は、福井県坂井市三国町(さかいしみくにちょう)で行なわれる「三國神社(みくにじんじゃ)」の春祭りです。富山高岡の「御車山祭(みくるまやままつり)」と石川七尾の「青柏祭(せいはくさい)」と合わせて「北陸三大祭」と呼ばれています。

「九頭竜川(くずりゅうがわ)」の河口に位置する「三国港(みくにこう:現・福井港)」は、日本海航路の要地として、多くの「北前船(きたまえぶね)」で賑わい、九頭竜川上流の新田開発により、米などの物資が九頭竜川の流れに沿って集まり、「越前(えちぜん)」の集積地として繁栄していました。

「三國神社」は、天文9年(1540)湊の住人・坂津清兵衛が、高柳村より流れてきた御神体を拾い上げ、性海寺(しょうかいじ)の塔頭「正智院」に納めたところから始まります。のちに、正智院は「桜谷神社」と改められ、明治5年(1872)には、近隣の水門宮の御神体「継体天皇(けいたいてんのう)」を合祀し、明治18年(1885)に「三國神社」と改称されました。御祭神は「大山咋命(おおやまくいのかみ」「継体天皇」です。
樹齢約600年ともいわれる鳥居横のケヤキをはじめ大樹が生い茂る荘厳な境内には、県指定文化財の太刀や立願文、実物大の木造彩色の神馬が安置されています。京都八坂神社の楼門(ろうもん)を写せしという重厚な楼門「随神門(ずいじんもん)」は、明治初期に湊の町衆によって造られました。和様を基調としながら扇垂木(おうぎだるき)など禅宗様も加味され、組入天井(くみいれてんじょう)を縁板(えんいた)の下まで張ったり、軒に菱と雲の支輪(しりん)を併用しているのも珍しく、県の有形文化財に指定されています。
◆三国祭(みくにまつり)

三國神社の春祭り「三国祭」は、毎年5月19日「例大祭」、20日「山車(やま)神輿巡行」「中日祭」、21日「後日祭」の3日間行なわれます。三国町の古い家並みや300年の歴史を持つ勇壮な三国祭は、江戸から明治にかけて北前船交易で隆盛を極めた「三国湊(みくにみなと)」の栄華を物語ります。
祭りの呼びものは、20日の「山車巡行」です。町内には18基の「山車(やま)」があり、山番にあたった6基(または7基)が三國神社前に集結します。武者人形の山車は、最大高さ6.5m。立並ぶ露店商の屋根をハネ上げ、歴史が刻まれた町の路地を巨大な山車が車輪を軋ませながら進みます。「三国っ子」たちが、大人も子どもも三味線・笛・太鼓を演奏しながら山車とともに練り歩き、伝統的な祭囃子の音色が町中に響き渡ります。

神仏分離以前の伝統を守り伝えられてきた祭は、ほかにあまり例を見ません。奉仕者は毎年700人を超え、狭い町並みの両脇には700軒の露店がぎっしり立ち並び、この日は町全体が休日になります。
三國神社
◇福井県坂井市三国町山王6-2-80
◇公式サイト:http://www.mikunijinja.jp
◇坂井市へのアクセス:https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/koho/shisei/gaiyo/profile/access.html
◆三国祭(三国祭保存振興会 ):https://mikunimatsuri.com
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

三国町には、サスペンスドラマに登場することでも有名な断崖絶壁「東尋坊」もあります。九頭竜川河口に築かれた三国港、日本海の荒波が削った東尋坊。厳しくも美しい自然とともに生きてきた三国の人びとの歴史を想わせます。
5月の福井は春から初夏へと移り変わる爽やかな季節です。朝晩の冷え込みにはご用心を。
読者の皆様、ご自愛専一の程
筆者敬白