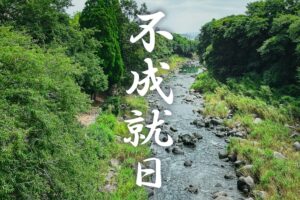■5月16~18日 浅草神社(あさくさじんじゃ)例大祭「三社祭(さんじゃまつり)」です。■

「三社祭(さんじゃまつり)」は、毎年5月に行なわれる「浅草神社(あさくさじんじゃ)」の例祭です。浅草神社は、通称「三社様(さんじゃさま)」「三社権現(さんじゃごんげん)」と呼ばれます。

土師真中知命(はじのまなかちのみこと)と檜前浜成命(ひのくまのはまなりのみこと)・檜前武成命(ひのくまのたけなりのみこと)兄弟を主祭神として祀り、この3人の霊をもって「三社権現」と称します。のちに東照宮(徳川家康)、大国主命(おおくにぬしのみこと)を合祀しました。
社伝によると、推古天皇36年(628)檜前浜成・武成の兄弟が、宮戸川(みやとがわ:現在の隅田川)で漁をしていたところ、同じ人形の像が繰り返し網に掛かりました。地元の文化人だった土師真中知に相談したところ、これは聖観音菩薩(しょうかんのんぼさつ)像であると教えられ、漁師の兄弟は毎日観音像に祈念するようになりました。その後、土師真中知は剃髪して僧となり自宅を寺としました。これが現在の「浅草寺(せんそうじ)」の始まりと伝えられます。土師真中知の歿後、真中知の子の夢に観音菩薩が現れ、そのお告げに従って真中知・浜成・武成を神として祀ったのが「浅草神社」の起源とされています。

明治の神仏分離により、浅草寺とは別法人になり、明治元年(1868)「三社明神社」に改称、明治5年(1872)に「郷社(もと、神社社格のひとつ)」に列し、明治6年(1873)に現在の「浅草神社」に改称しました。
国の重要文化財に指定されている社殿は、第3代将軍「徳川家光(とくがわいえみつ)」の寄進で、慶安2年(1649)に建てられたものです。朱塗りや彩色の美しさ、精緻な彫刻など、江戸時代初期の神社建築のひとつとして貴重な歴史的財産です。
◆三社祭(さんじゃまつり)

「三社祭(さんじゃまつり)」は、氏子四十四ヶ町を中心に、5月の第3土曜日の前後を合わせた3日間、勇壮かつ華やかな神輿渡御が見どころの日本を代表するお祭りです。江戸風情の残る下町浅草は期間中およそ180万人の人出で賑わいます。
その昔、3月中旬に祭が行なわれ、丑・卯・巳・未・酉・亥の年には「本祭」が行なわれていました。宮戸川の浅草裏で聖観音菩薩が示現した「三社の神話」にもとづき、正和元年(1312)、船祭「舟渡御」が始められたと伝わります。江戸時代には浅草寺と一体で祭が行なわれ「観音祭」「浅草祭」と呼ばれていました。明治5年(1872)から祭礼は5月に時期をうつし、氏子各町で神輿の渡御を行なうようになりました。
初日は、お囃子屋台をはじめ鳶頭木遣り(とびがしらきやり)、浅草の各舞、芸妓連の手古舞(てこまい)や組踊り(くみおどり)などで編成された「名物大行列」が浅草の町を練り歩きます。拝殿では、五穀豊穣、商売繁盛、子孫繁栄などを祈って氏子の人びとによる神事「びんざさら舞」も奉納されます。

2日目、「例大祭式典」が斎行されます。そのあと「町内神輿連合渡御」によって浅草氏子四十四ヶ町の町内神輿約100基が本堂裏広場に参集し、一基ずつお祓いを受けて、各町会を渡御します。
最終日は、本社神輿3基「一之宮」「二之宮」「三之宮」が早朝より発進する「宮出し」が行なわれます。神輿は3方面に分かれ、浅草の各町を渡り、日没後に神社境内へ戻る「宮入り」を迎えて祭礼行事が終わります。
浅草神社
◇東京都台東区浅草2-3-1
◇地下鉄浅草線・地下鉄銀座線・東武伊勢崎線「浅草駅」徒歩7分
◇公式サイト:https://www.asakusajinja.jp
◇「三社祭」(浅草神社):https://www.asakusajinja.jp/sanjamatsuri/
◆「三社祭」公式サイト(浅草神社奏賀会):https://www.sanjasama.jp
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

東京の初夏の風物詩のひとつ、浅草神社の「三社祭」です。令和10年(2028)に浅草寺本尊御示現1400年を記念して、浅草神社宮神輿「舟渡御」が斎行されるそうです。隅田川と東京湾岸を中心に、多くのひとやものを運び、にぎわいを見せていた江戸の水運。古式に則り行なわれる船渡御は江戸情緒あふれるお祭りになるのでしょう。
「下谷神社大祭」「鳥越神社例大祭」など、5月の江戸下町は祭り一色ムードでとてもにぎやかです。三社祭が終わると、東京はそろそろ梅雨に入ります。
皆様、お体ご自愛専一の程
筆者敬白