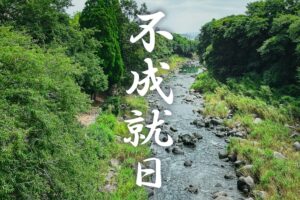■5月14~16日 島根、出雲大社「大祭礼」です。■
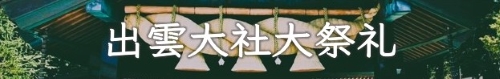
出雲国一宮「出雲大社(いずもたいしゃ)」は、式内社(名神大)で旧社格は官幣大社。明治維新にともなう「近代社格制度」下では、唯一「大社」を名乗る神社でした。古来より「国中第一の霊神(れいじん)」として称えられ、その本殿は「天下無双の大廈(たいか)」(ふたつと同じものがない壮大な神殿)と評されました。

本殿は「大社造(たいしゃづくり)」と呼ばれる日本最古の神社様式の木造建築で、国宝に指定されています。高さは8丈(約24m)で、神社としては破格の大きさです。かつての本殿は現在よりもはるかに高く、中古には16丈(48m)、上古には32丈(96m)であったと伝わります。「八雲山(やくもやま)」を背景にした姿は、逞しい生命力を感じさせます。
出雲大社の御祭神「大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)」は、「だいこくさま」として親しまれ、広く「えんむすび」の神として、全国各地で祀られています。縁結びとは、単に男女の仲を結ぶことだけでなく、人間が立派に成長するよう、社会が明るく楽しいものであるよう、すべてのものが幸福であるようにと、お互いの生成のためのつながりとしての「縁」が結ばれることです。
日本神話には、「高天原(たかまがはら)」にいる「天津神(あまつかみ)」と、「葦原中国(あしはらのなかつくに:高天原と黄泉の国のあいだにある地)」に現れた「国津神(くにつかみ)」が登場しますが、大国主大神は、国津神の主宰神で、日本国を創った神とされています。『出雲国風土記(いずものくにふどき)』では、「所造天下大神(あめのしたつくらししおおかみ)」と呼ばれ、福の神、平和の神、縁結びの神、農耕の神、医薬の神として崇められています。
◆大祭礼(例祭)

5月14日、天皇陛下の「勅使(ちょくし)」を迎えて例祭が執り行なわれます。古く「三月会(さんがつえ)」と称され、旧暦3月1日より3日までの3日間、盛大に厳かに執り行なわれていました。三月会は出雲大社で最も重儀な祭典です。
勅使をお迎えする祭典を「勅祭(ちょくさい)」といいますが、勅祭にお仕えできるのは、伊勢神宮をはじめとする由緒正しき十数社に限られます。
5月14日 的射祭(まといさい)、例祭
5月15日 例祭二之祭、神輿渡御祭
5月16日 例祭三之祭、出雲屋敷感謝大祭
5月14日、拝殿で「的射祭」が斎行されます。「松の参道」で邪物を祓う矢が神職によって放たれ、境内を祓い清めます。
そして、宮司以下祀職たちは、年にいちど、この例祭のときにしか身に着けない「正服(せいふく)」で身をつつみ、海、川、山、野の「神饌(しんせん:お供え物)」を神前へ供えます。宮司が祝詞を奏上し、天皇陛下の勅使が本殿へと参進します。天皇陛下より御幣物が宮司へと伝達され、本殿奥の大国主大神の前に供えられます。勅使より「御祭文(ごさいもん)」が奏せられます。

期間中の行事は流鏑馬神事・田植舞・茶会・伊勢大神楽(いせだいかぐら)・獅子舞など。華道展、絵画展、書道展のほか、スポーツ大会や骨董市も開催されます。
出雲大社
◇島根県出雲市大社町杵築東195
◇一畑電車「出雲大社前駅」徒歩7分
◇JR山陰本線「出雲市駅」バス25分
公式サイト:https://izumooyashiro.or.jp
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

初夏の時期、出雲大社の大祭礼です。この大祭礼に限らず、お伊勢参り同様、出雲大社には是非いちどお出かけください。
読者の皆様、時節柄お体ご自愛専一の程
筆者敬白