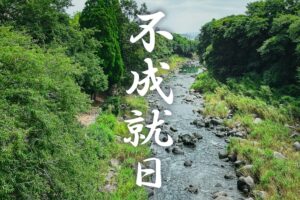■5月10~11日 岐阜「大垣まつり」です。■
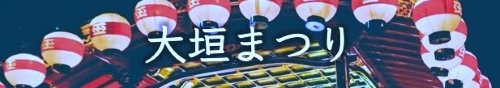
370年余の伝統を誇る「大垣まつり」は、「大垣八幡神社(おおがきはちまんじんじゃ)」の例大祭です。大垣八幡神社の祭神は「応神天皇(おうじんてんのう)」「神功皇后(じんぐうこうごう)」「比咩大神(ひめのおおかみ)」。大垣八幡神社は通称で、正式名称は「八幡神社」。大垣市の総鎮守です。

天平勝宝元年(749)より、大井荘(おおいのしょう:現大垣市付近)は奈良「東大寺」の荘園でした。建武元年(1334)、後醍醐天皇の時代、東大寺鎮守神「手向山八幡宮(たむけやまはちまんぐう)」を勧誘したのが大垣八幡神社の始まりと伝わります。
宝徳3年(1451)ごろ現在の地に遷座、大垣町及び近傍十八郷の総社と称しました。「遮那院(しゃないん:真言宗の寺院)」が別当寺(べっとうじ:神社を管理するために置かれた寺)を務めました。
天文15年(1546)には、斉藤道三(さいとうどうさん)の兵火により全焼しましたが、慶長5年(1600)頃、ほどなく再建されました。その後、慶長11年(1606)大垣城主石川康道(いしかわやすみち)の刀奉納、13年(1608)幣殿、拝殿、舞殿が建てられました。慶安元年(1648)美濃大垣藩初代藩主「戸田氏鉄(とだうじかね)」により再建整備が行なわれました。大東亜戦争中の空襲で社殿が焼失しましたが、氏子の奉仕により本殿、拝殿、社務所の復興が叶い、いまに至ります。
◆大垣まつり

大垣藩初代藩主、戸田氏鉄が大垣城下の総氏神である八幡神社を再建整備した際、城下18郷が再建の喜びを御輿3社の寄付で表し、大垣10か町が10両の「やま(軕)」を造って曳回したのが「大垣まつり」の始まりと伝わります。
延宝7年(1679)、第3代藩主「戸田氏西(とだうじあき)」から、「神楽やま」「大黒やま」「恵比須やま」のいわゆる三両やまを賜り、それを機に10か町は、やまの飾りつけに趣向を凝らしていきました。
明治24年(1891)の濃尾地震や大東亜戦争によって多くのやまを失いますが、その後、修復や復元、購入するなどして再建が進められ、平成24年(2012)になって残る2両となっていたやまが復元されました。これで全13両のやまが勢揃いし、華麗な元禄絵巻を繰り広げます。
大垣まつりは、大垣の城下町祭礼として伝えられてきた美濃地方を代表する祭礼行事であり、大垣藩主下賜の「やま」と町衆の「やま」が併存する形式は全国的にも珍しく、また、中京圏の山車行事の影響がみられる「からくり人形」、近畿圏の山車行事の影響が色濃い「やま上の芸能」には、東西の祭礼文化の交流のあとがうかがえます。

大垣八幡神社
◇岐阜県大垣市西外側町1-1
◇公式サイト:http://ogaki80003.or.jp
◆「大垣まつり」(大垣観光協会):https://www.ogakikanko.jp/event/ogakimaturi/
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

大垣まつりは平成27年(2015)、「大垣祭の軕行事」として、国の重要無形民俗文化財に指定されました。平成28年(2016)には、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。
岐阜県ではこの時期、岐阜市長良川の「鵜匠」、大垣市の「大垣まつり」と観光行事が目白押しです。
お出かけの際には紫外線対策などお忘れなく、お体ご自愛専一の程
筆者敬白