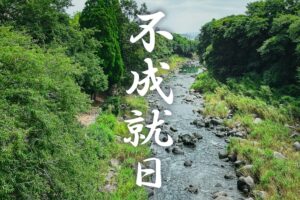■5月10日 笠間稲荷「御田植祭(おたうえさい)」です。■
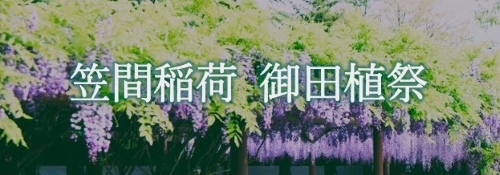
「笠間稲荷神社(かさまいなりじんじゃ)」は、別称「胡桃下稲荷(くるみがしたいなり)」「紋三郎稲荷(もんざぶろういなり)」と呼ばれる神社本庁の別表神社です。本殿は万延元年(1860)建立の建築で、周囲の彫刻は国の重要文化財に指定され、「三頭八方睨み龍」「牡丹唐獅子」は特に有名です。

御祭神は「宇迦之御魂命(うかのみたまのみこと:正一位の最高位の神)」。第36代孝徳天皇の御代、白雉2年(651)創建、1350余年の歴史を有する由緒ある神社で、日本三大稲荷のひとつです。五穀の神「宇迦之御魂命」は、生命の根源を司る「いのち」の根の神「稲荷大神(いなりおおかみ)」と古くから同一視され、農業の守護神、商業、工業、殖産興業、交通安全、厄除、火防の神として広く崇敬されています
稲荷大神にとって「キツネ」は、熊野神社の「カラス」、八幡神社の「ハト」、氏神さまの「狛犬」などと同様に神さまのお使いをする霊獣で、「神使(かみのつかい)」「眷属(けんぞく)」などと呼ばれます。

中世の時代、人間が持っている様々な欲望を、直接神さまに祈願するのは畏れ多いとして、特別に選ばれた動物を通してお願いすることが行なわれたことによるものです。キツネがお使いとして選ばれたのは、稲荷大神が農業神であることと深く結びついています。
日本人には古くから神道の原形「山の神、田の神」が信仰されていました。春になると山の神は山から里へ降り、田の神となって稲の生育を守護し、収穫が終えた秋に山へ帰って山の神となります。ちょうどキツネが「農事の始まる初午の頃から収穫の終わる秋まで」人里に姿を見せる時期と重なります。

キツネが稲荷大神のご祭神と混同されるようになったのは、平安時代以降の神仏習合によります。稲荷大神が仏教の守護神「茶枳尼天(だきにてん)」の垂迹(すいじゃく:仏菩薩が、仮に日本の神の姿をとって現れること)とされたからです。
茶枳尼天は、またの名を「白晨狐王菩薩(びゃくしんこおうぼさつ)」といい、キツネの精とされました。このことから一般民衆の間で、いつのまにか稲荷大神のご祭神とキツネが混同されてしまったと考えられています。
また、稲荷大神の別称「御饌津神(みけつかみ)」の「ミケツ」が混同されて「三狐神(みけつかみ)」と記されたこともその一因。ちなみに御饌津神は、食物をつかさどる神(「饌(せん)」は、食物、食事、供え物のこと)で、キツネとは全く関係ありません。
◆御田植祭
5月10日、御神饌田(しんせんでん)において、古式ゆかしい「御田植祭(おたうえさい)」が行なわれます。その年の豊穣を祈願するとともに、稲荷大神に毎日御供えする「御米(みけ)」を栽培する稲苗の植付けの神事です。
御神饌田は正方形で広さは約300坪(約992平米)。四方の中央に素木鳥居(しらきとりい)、周囲に竹矢来(たけやらい)を巡らせます。正面に祭場、右前には舞殿が設けられます。

舞殿にて、巫女、氏子らによる神楽舞「稲荷舞」、「迦陵頻(かりょうびん)」が奉奏されます。ついで、早朝神前にお供えし祓清められた早苗が宮司より配られ、太鼓三打を合図に田植えが始まります。地元の中学生らが『御田植祭歌』(折口信夫作詞、兼常清佐作曲)を歌い上げます。
検知役の宮司が田植えの進捗状況を確認し、祭典は終了します。その後、関係者一同社務所に戻り、「直会(なおらい)」(祭事が終わって供え物の神酒・神饌を下げて皆で飲食すること)を行ない、秋の豊穣を期待し合います。
笠間稲荷神社(かさまいなりじんじゃ)
◇茨城県笠間市笠間1番地
◇JR水戸線「笠間駅」徒歩20分
◇北関東自動車道「友部IC」~国道355号約15分
◇公式サイト:http://www.kasama.or.jp
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
笠間稲荷の御田植祭で歌われる『御田植祭歌』は、昭和11年(1936)から歌われているそうです。当時、昭和天皇即位にくわえて皇紀2600年(昭和15年)の祝賀ムードもあり、全国各地の町や村でわが町自慢の歌を作ろうと「~音頭」や「~ぶし」といった曲が次々に生まれました。笠間稲荷の『御田植祭歌』もそんな曲のなかのひとつです。
筆者敬白