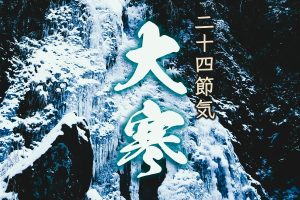■二十四節気◆令和7年(2025)5月5日「立夏(りっか)」です。■

令和7年(2025)5月5日14時57分「立夏」です。旧暦4月、巳(み)の月の正節で、新暦5月5日~6日頃。天文学的には太陽が黄経45度の点を通過するときを指します。旧暦では3月15日~4月15日の間のどこかになります。

立夏は、春分と夏至の中間にあたります。昼夜の長さを基準に季節を区分すると、立夏から立秋の前日までが「夏」となります。「暦便覧」には立夏を「夏の立つがゆへなり」と記されています。「立夏」は「夏立つ」「夏来る」などとともに代表的な夏の季語になっています。
春ようやく褪せて、山野に新緑が目立ち始め、吹く風は爽やかになり、いよいよ夏の気配を感じられる頃。旧暦5月の田植えを知らせる渡り鳥、ホトトギスが「忍び音(しのびね)」〔※〕で鳴く頃。蛙も鳴き始め、ミミズが地上に這い出て、竹の子が芽を出します。ゴールデンウィークの終盤にあたります。歳時記の上では立夏といっても、体感的にはいまだ春の感じがします。
※忍び音(しのびね):ホトトギスの、声をひそめるような鳴き声。陰暦4月ごろの初音。「初音(はつね)」とは、鳥や虫の、その年、その季節の最初の鳴き声のこと。
唱歌『夏は来ぬ』(1896、佐佐木信綱作詞、小山作之助作曲)には、卯の花(ウツギの花)、ホトトギス、五月雨、田植えの早乙女、橘、蛍、楝(おうち:センダン)、水鶏(くいな)などの「初夏」を彩る風物詩が散りばめられています。
一.
 卯の花の 匂う垣根に
卯の花の 匂う垣根に
時鳥(ほととぎす) 早も来鳴きて
忍音(しのびね)もらす 夏は来ぬ
二.
さみだれの そそぐ山田に
早乙女が 裳裾(もすそ)ぬらして
玉苗(たまなえ)植うる 夏は来ぬ
三.
橘の 薫るのきばの
窓近く 蛍飛びかい
おこたり諌むる 夏は来ぬ
四.
楝(おうち)ちる 川べの宿の
門(かど)遠く 水鶏(くいな)声して
夕月すずしき 夏は来ぬ
五.
五月(さつき)やみ 蛍飛びかい
水鶏(くいな)鳴き 卯の花咲きて
早苗植えわたす 夏は来ぬ
◆◆七十二候◆◆
◆初候「蛙始鳴」(かえる はじめて なく):蛙が鳴き始める
◇雨蛙が鳴き、産卵を始める時節。
◆次候「蚯蚓出」(きゅういん いずる):蚯蚓が地上に這出る
◇蚯蚓が地上に這い出る時節。蚯蚓(きゅういん)=ミミズ。目もなく手足もない紐状の動物。名の由来は「目 見ず」から。多くは陸上の土壌中に生息。
◆末候「竹笋生」(ちくかん しょうず):筍が生えて来る
◇タケノコが生えて来る時節。タケノコ=若い竹の幹の部分。食用としては、日に当たったものほどアクが強いため、土から顔を出す前に掘るのが望ましい。

◆◆5月の花◆◆

◆「文目」(あやめ) あやめ科 アヤメ属 学名:Iris sanguinea ギリシャ語で「虹」の意。開花時期:5月1日~5月20日頃。
剣形の葉が整列して生える様子から「文目(あやめ:筋道、模様の意)」と呼ばれます。花弁の中央に網目模様があり、葉は細くて長い。「綾目」とも書く。よく「菖蒲」と書いて「あやめ」といいますが、菖蒲とは別種で、湿地ではなく乾いた土地に生えます。「いずれ文目か杜若(かきつばた)」とは、区別できないことの喩え。
花言葉は、「希望」「よい便り」「信じるものは救われる」「愛」「神秘的」など。

◆「杜若」(かきつばた) あやめ科 アヤメ属 学名:Iris laevigata 開花時期:5~6月。
花は紫、青紫、白。その昔、花の汁で布を染めていました。これを「書き付け花」といい、「かきつばた」と変化したもの。水中に生えます。葉は幅広で長い。「燕子花」とも。万葉の頃には「垣津幡」「加古都幡多」などと書いていました。
花言葉は、「高貴」「思慕」「幸せは必ず来る」など。

◆「菖蒲」(しょうぶ) 里芋科 ショウブ属 学名:Acorus calamus var. angustatus。「美しくない花」の意。漢名の「菖蒲」を音読みしたもの。開花時期:5~7月。
沼や川などの水辺に群生し、初夏にうす茶色の花を咲かせます。葉の途中に花穂をつけ、見た目には空中に浮いているようにみえます。「端午の節句(5月5日)」に菖蒲の葉を風呂に入れる「菖蒲湯」の習慣があります。薬効と香りによって邪気を祓います。
花言葉は、「優雅」「心意気」「優しい心」「うれしい知らせ」など。
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
二十四節気「立夏」で暦の上では「土用」が明けます。これまで停滞していた事柄の解決に奔走するのはまさしくこれからです。
季節の変わり目です。読者の皆様、お体ご自愛専一の程
筆者敬白