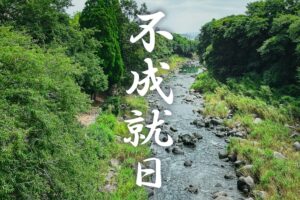■5月2日「奈良、東大寺 聖武天皇祭」です。■
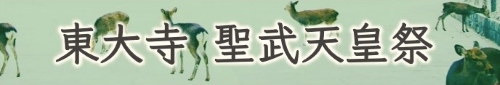
華厳宗(けごんしゅう)大本山「東大寺(とうだいじ)」は「金光明四天王護国之寺(こんこうみょうしてんのうごこくのてら)」とも。奈良時代に聖武天皇(しょうむてんのう)が国力を尽くして建立した寺です。

「奈良の大仏さま」として知られる「盧舎那仏(るしゃなぶつ)」を本尊とし、大仏創建に力のあった良弁(ろうべん)、聖武天皇、行基(ぎょうき)、菩提僊那(ぼだいせんな)は「四聖(ししょう)」と呼ばれています。
この「盧舎那大仏造顕(ぞうけん=造立)」という国を挙げての難事業について、聖武天皇は「若し朕が時に造り了るを得ざるあらば来世に於て身を改めて猶作らん」と述べ、自らを「三宝(あるいはみほとけ)の奴(やっこ)と仕えまつる天皇(すめらみこと)」と称しました。華厳経の教理が明らかにされてはじめて聖武天皇の熱意と信仰心が伝わり、これが原動力となって可能になったとも伝わります。
現在の境内は、世界最大級の木造建造物である大仏殿(だいぶつでん)を中心に、南大門(なんだいもん)、鐘楼(しょうろう)、俊乗堂(しゅんじょうどう)、開山堂(かいさんどう)、法華堂(三月堂)、二月堂、戒壇院戒壇堂(かいだんいんかいだんどう)、転害門(てがいもん)などの建造物が建ち並んでいます。また、大仏殿の北方(裏手)には正倉院(しょうそういん)、東方には、宇佐八幡宮より東大寺の鎮守神として勧請された手向山八幡宮(たむけやまはちまんぐう)があります。諸堂内には、盧舎那仏をはじめとして多数の国宝・国重要文化財の彫刻を蔵します。
◆聖武天皇祭(しょうむてんのうさい)◆

「聖武天皇祭(しょうむてんのうさい)」は、天平勝宝8年(756)56歳で崩御された聖武天皇の御忌法要です。
午前中、「天皇殿(てんのうでん)」で論議法要が執り行われます。この法要中に限り、日ごろは公開されていない天皇殿を屋外から参拝することができます。元禄2年(1689)造立の聖武天皇像が祀られています。
午後からは式衆、稚児等の練り行列が行なわれます。行列は奈良春日野国際フォーラム甍を出発し、南大門を経て参道を大仏殿に向かいます。先駈(さきがけ)、道楽(みちがく)を奏でる楽人、稚児、物詣女(ものもうでおんな)、奈良市観光協会関係者、聖武講役員、僧兵、会奉行(えぶぎょう)、式衆(東大寺本山末寺の僧侶、伴侍、傘もち)、東大寺住職、侍僧等、約250人からなる行列です。
大仏殿到着後「聖武天皇慶讃法要」が行なわれ、鏡池(かがみいけ)の水上舞楽台では、南都楽所(なんとがくそ)による舞楽が奉納されます。
翌3日には、東大寺一山の僧侶が聖武天皇を祀る「佐保山南陵(さほやまのみなみのみささぎ)」に参拝する「山陵祭(さんりょうさい)」が行なわれます。それから大仏殿に戻り、裏千家による献茶式が行なわれます。献茶式が終わると、大仏殿東回廊の施茶席で抹茶がふるまわれます。参拝者用約4000人分用意されるそうです。

東大寺
◇奈良市雑司町406-1
◇JR・近鉄「奈良駅」から市内循環バス「東大寺大仏殿・春日大社前」下車
◇近鉄「奈良駅」から、ぐるっとバス「大仏殿前駐車場」下車
◇公式サイト:https://www.todaiji.or.jp
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

5月2日の聖武天皇御忌から3日の山陵祭へと一連の行事が続きます。見どころの「練り行列」は、5月2日午後1時頃から始まります。なかなか見ごたえのある時代絵巻です。
緑のきれいな季節です。日が沈むと急に寒くなることもあります。薄着でお風邪など引かないよう、お体ご自愛専一の程
筆者敬白