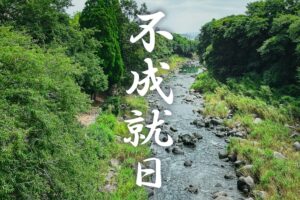■5月2~4日「しものせき海峡まつり」です。■

山口県下関市にある「赤間神宮(あかまじんぐう)」は、「壇ノ浦の戦い(だんのうらのたたかい)」において入水した第81代「安徳天皇(あんとくてんのう)」を祀ります。旧社格は官幣大社。

今から800年の昔、平氏は源義経(みなもとのよしつね)を総大将とする源氏の軍に敗れ、数え8歳の安徳天皇は幼くして二位尼(平時子)とともに壇ノ浦に入水しました。大将平宗盛(たいらのむねもり)も捕えられ、栄華を誇った平家も遂に敗北し、武将や女官たちは海に身を投じました。
『平家物語』には、「悲しきかな無情の春の風、忽ちに花の御姿を散らし、情けなきかな分断の荒き浪、玉体を沈め奉る」と描かれています。

入水崩御した安徳天皇を慰めるために建てられた「安徳天皇御影堂」は、江戸時代までは「阿弥陀寺(あみだじ)」が守り冥福を祈っていました。阿弥陀寺は小泉八雲(こいずみやくも)の怪談『耳なし芳一』の舞台としても知られます。
明治時代の廃仏毀釈運動により、阿弥陀寺は廃され、明治8年(1875)「赤間宮」が創建され、昭和15年(1940)「赤間神宮」と改称、社殿も整えられました。安徳天皇の御陵は宮内庁により「阿彌陀寺陵(あみだじのみささぎ)」として赤間神宮境内に治定されています。境内には、壇ノ浦の戦に敗れ波の底に沈んだ平家一門の墓「七盛塚(ななもりづか、しちもりづか)」もあります。
◆しものせき海峡まつり

「しものせき海峡まつり」は、赤間神宮の特殊神事「先帝祭(せんていさい)」を中心に、下関の歴史を今に伝える歴史情緒豊かなお祭りです。安徳天皇の命日は旧暦3月24日ですが、明治の改暦の際、新暦5月2日と定められました。しものせき海峡まつりは、5月2日から4日まで下関の町をあげて開催されます。
5月2日
平家落人の子孫らで組織される「全国平家会」の参列のもと「御陵前祭」「平家一門追悼祭」が斎行されます。
5月3日
「大祭神事」が厳修され、平家太鼓などが奉納されます。
先帝祭では、竜宮城をイメージして造られた赤間神宮境内の「水天門」から本殿へと橋「天橋」が架けられます。豪華絢爛な衣装を身にまとった5人の太夫が、稚児、警固、官女、禿(かむろ)を従えて、外八文字()を披露しながら市内を練り歩く「上臈道中」、そして、天橋を渡り神前に拝礼する「上臈参拝(じょうろうさんぱい)」で祭りはクライマックスをむかえます。
◆上臈参拝の由来
平家滅亡後、残された女官たちは里人に救われたものの、宮仕えの育ちのため生計の法を知らず、付近の稲荷山などの草花を手折っては沖がかりの船人に売り、ほそぼそと暮らしていました。それでも毎年、安徳天皇の命日には威儀を正して御影堂に参拝し、香華を手向けました。
女官やその遺族が没したあとも、里人のなかで奴楼を営むようになった者が、遊女に女官たちのように容姿を整えて参拝させるようになりました。江戸時代に入ると、稲荷町に遊郭ができ、そこでも参拝の行事が受け継がれ、現在の「上臈道中」「上臈参拝」になったと伝わります。
5月4日
甲冑に身を包んだ約100名もの武者と艶やかな衣装をまとった官女たちが、源氏と平氏に分かれて市内を行進する「源平武者行列」が行なわれます。両軍、各所で勇壮な「勝ち鬨の声」をあげ、源平の合戦を再現します。
最終日のこの日、「源平船合戦(海上パレード)」や「八丁浜総踊り」も行なわれ、下関の町と港は歴史情緒豊かなイベントで賑わいます。

赤間神宮
◇山口県下関市阿弥陀寺町4-1
◇公式サイト:https://akama-jingu.com
◆「しものせき海峡まつり」(下関市):https://shimonoseki.travel/kaikyo_fes/
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

ゴールデンウィーク真っ只中。天候次第では見ることがかなわないかもしれませんが、それでも巌流島船舶による海上パレードは見もの。先帝祭の上臈参拝の花魁道中もこれまた見ごたえがある時代絵巻です。
読者の皆様、時節柄お体ご自愛専一の程
筆者敬白