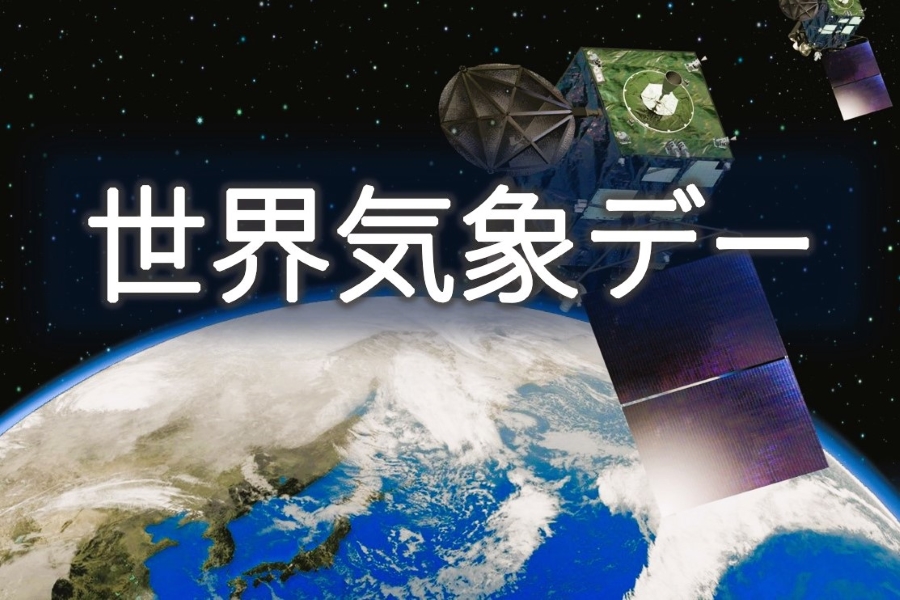■3月23日「世界気象デー」です。■
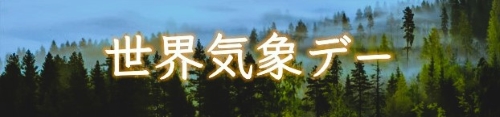
昭和22年(1947)9月、国際気象台長会議で、気象情報の国際協力を目的とした「世界気象機関条約」が採択されました。同条約は、昭和25年(1950)3月23日に発効し、WMO(世界気象機関:World Meteorological Organization)が正式に設立、翌年には国連の専門機関になりました。

WMO設立の目的は、「世界の気象業務を調整し、標準化し、及び改善し、並びに各国間の気象情報の効果的な交換を奨励し、もって人類の活動に資する」こと。本部はスイスのジュネーブ。令和6年(2024)3月現在、187ヶ国・6領域が加盟しています。
日本は昭和28年(1953)9月10日、WMOに加盟しました。現在、気象庁は、気象衛星ひまわりの運用や、観測、通信、熱帯低気圧、気候等の様々な分野に関するWMOの地区センターの運用を通じて、各国の気象業務を支援するための情報提供、技術協力等を行っています。

開発途上国では、気象観測網の整備や維持が十分になされていないため、気象予報や気象情報の提供が難しく、適切な災害対策ができないことが問題になっています。WMOは戦略対策として「ビジョン2030」を掲げ、「2030年までに、全世界の国々、特に最も脆弱な国々が極端な気象・気候・水文及び関連する環境現象の社会経済的影響に対してより強靭化し、陸上、海上、航空の可能な限り最善のサービスを通じて持続可能な開発を推進するために力を与えられること」を目指すとしています。
◆世界気象デ―
WMOは世界気象機関条約が発効したことを記念して3月23日を「世界気象デー」とし、毎年、キャンペーンテーマを設け、気象業務への国際的な理解の促進に努めています。

令和6年(2024)12月30日、国連のグテーレス事務総長はビデオメッセージで、「気候の崩壊が起きている」と、地球温暖化の進行について強い危機感を示しました。その要因は戦争や社会の分断などによるものだとし、各国に対して温室効果ガスの排出規制などに一致して取り組むよう呼びかけました。令和7年(2025)1月10日、WMOは「令和6年(2024)は観測史上最も暑い一年だった」とし、世界全体の気温が産業革命以前と比べて1.55℃上昇したことを発表しました。
近年、日本でも、大雨の頻度や強度が増加しているなど、気候変動の社会的影響が如実に表れています。気象庁は、様々な防災気象情報の発表、気候変動の監視・予測に関する情報発信などを通じて社会の気候変動対策に貢献し、今後も引き続き取り組むとしています。
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
近年、気象に関する技術は、これまで観測不能だった竜巻や局部的な豪雨、ヒョウ、豪雪などの予測ができるまでに進歩しています。気象予報の精度が上がれば、産業界のロスを減らすことにも役立つでしょう。
気象が軍事機密だった時代や、『三国志演義』で諸葛孔明が六象台(ろくしょうだい)を築き味方に有利な風を吹かせた「赤壁の戦い」など、気象を知ることは大変重要です。
筆者敬白