■3月9日 茨城、鹿島神宮「祭頭祭(さいとうさい)」です。■
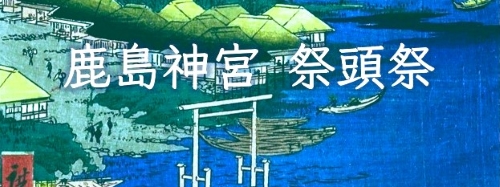
常陸国一之宮「鹿島神宮(かしまじんぐう)」の創建は、神武天皇(じんむてんのう)即位年の皇紀元年(西暦紀元前660)と伝わります。

祭神は「武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)」です。東征の半ば、思わぬ窮地に陥った神武天皇を救ったのが、武甕槌大神の「韴霊剣(ふつのみたまのつるぎ)」の神威だったことから、国の守護神として篤く信仰されるようになりました。中世以降は、源頼朝(みなもとのよりとも)、徳川家康(とくがわいえやす)など武将の崇敬を集め、武神として仰がれるようになりました。
そのため鹿島神宮周辺では武芸が盛んとなり、剣聖・塚原卜伝(つかはらぼくでん)を生んでいます。

鹿島神宮は皇室、公家、武士に関わらず長く尊崇され、現在に至ります。本殿は国の重要文化財。宝物殿には、国宝・直刀「布都御魂剣(ふつのみたまのつるぎ、韴霊剣)」が納められています。
境内の鹿園には、奈良の春日大社から譲り受けた鹿がいます。Jリーグの鹿島アントラーズのチーム名「鹿の枝角(antler)」は鹿島神宮の神鹿(しんろく)に因んでいます。
『古事記』『日本書紀』によれば、武甕槌大神は、宇宙自然の創世に成りませる陰陽の神「イザナギ、イザナミ」の両神より生まれた火の神カグツチより誕生したとされています。即ち、原初の自然創世の頃に成りませる神ということです。
武甕槌大神は鹿島神宮の主神として祀られていることから「鹿島神(かしまのかみ)」とも呼ばれます。
◆祭頭祭(さいとうさい)
「祭頭祭(さいとうさい)」は、鹿島神宮の春の大祭です。奈良時代の頃、九州の壱岐・筑紫・対馬を守るために旅立った防人(さきもり)たちが、無事に帰れたことを祝ったことが始まりと伝わります。祭りでは、3つの神事が執り行われます。
「出陣の神事(祭頭祭)」:午前、大勢の参列者が見守るなか、狩衣姿の一軍の将「大総督(だいそうとく)」と当番地区の代表者らが拝殿前に参列し、玉串をあげるなどの儀式が行なわれます。「大総督」は前年の春季祭の当番卜定後に字内より選ばれた3~6歳の男児で、「新発意(しぼち)」とも呼ばれます。
「凱旋の神事(祭頭囃(さいとうばやし))」:午後から行なわれます。甲冑姿の「大総督」を先頭に、衣装を纏った囃人らが本陣(鹿島神宮近くの旅館など)を出発し、町内を勇壮に練り歩きます。
「卜定(ぼくじょう)の神事(春季祭)」:午後6時、宮司の祝詞奏上ののち、町内の若衆によって「万灯」がともされ、「大豊竹(だいほうだけ)」が何度も叩きつけられて粉々になるまで打ち壊されます。一説には、大豊竹を稲穂に見立て、そこから無数の米が生まれることになぞらえた予祝行事だといわれています。そして、宮司が次年度の当番候補の地区の字名が入った紙片を釣り上げる「神占の義」が執り行われ、次年の当番地区が決定、地区の代表者らが祭頭囃を歌いながら神宮を後にし、祭が終了します。

※令和2年以降、これまで一日のうちに行なわれていた3つの神事のうち、3月9日に「出陣の神事(祭頭祭)」、3月9日の次の土曜日に「凱旋の神事(祭頭囃)」と「卜定の神事(春季祭)」が行なわれるようになっています。ただし、3月9日が土日にあたる場合は、3月9日に3つの神事がすべて行なわれます。

祭りの見どころは、凱旋の神事「祭頭囃」です。15、6人の囃人が一組となり、奈良時代風の唐服に似た伝来の装束をつけ、色鮮やかな五色のタスキをまとい、6尺の樫棒を組み合わせたりしながら随所で円陣を組み、馬簾や太鼓を勇ましく打ち鳴らして神宮へ向かいます。午後4時頃になると囃人の隊列が、鹿島神宮境内に到着します。拝殿前まで来ると、大総督が特設の舞台に着床し、囃人は各組ごとに一度拝殿前で囃します。すべての組が境内に揃うと、祭事委員長の合図に合わせて一斉囃子が行われます。
鹿島神宮
◇茨城県鹿嶋市宮中2306-1
◇JR「鹿島神宮駅」徒歩10分
◇高速バス「かしま号」(東京駅発)「鹿島神宮」下車
◇東関東自動車道「潮来IC」15分
◇公式サイト:https://kashimajingu.jp
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

二十四節気「啓蟄」も過ぎ、日差しがあたたかくなってきました。祭頭祭は鹿島地方に春を呼び、人びとの健康や豊作を祈る祭りです。
春から冬へ移り変わる今の季節には、日本海側に大雪が降ったり、不安定な天気が続きます。毎冬流行する感染症はもとより、急な気温の変化などでお風邪などお召しにならないよう一枚余分に持ってお出かけください。
皆様、お体ご自愛専一の程
筆者敬白













