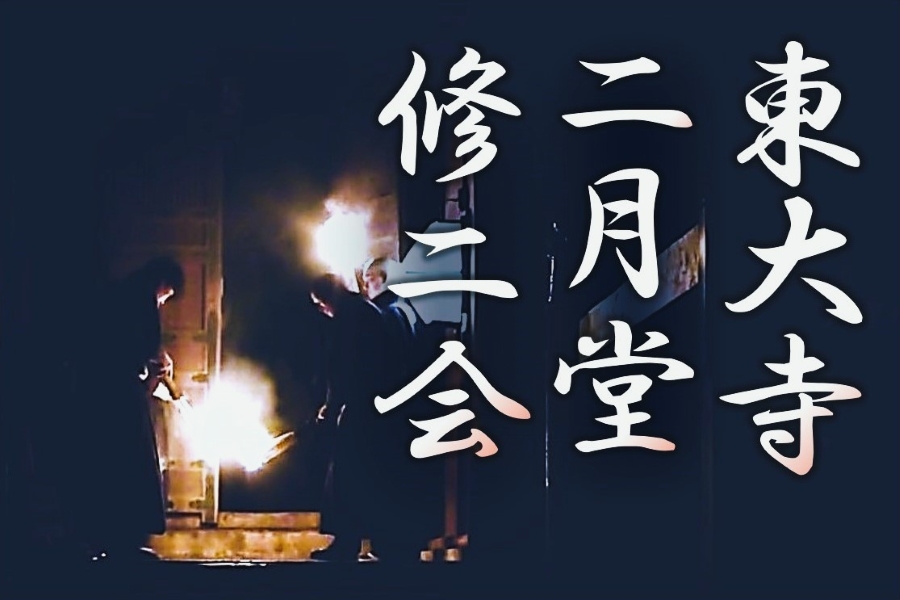■3月1~15日 東大寺二月堂「修二会(しゅにえ)」です。■
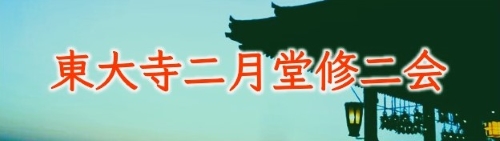
華厳宗(けごんしゅう)大本山「東大寺(とうだいじ)」は「金光明四天王護国之寺(こんこうみょうしてんのうごこくのてら)」とも。奈良時代に聖武天皇(しょうむてんのう)が国力を尽くして建立した寺です。

「奈良の大仏さま」として知られる「盧舎那仏(るしゃなぶつ)」を本尊とし、大仏創建に力のあった良弁(ろうべん)、聖武天皇、行基(ぎょうき)、菩提僊那(ぼだいせんな)は「四聖(ししょう)」と呼ばれています。
この「盧舎那大仏造顕(ぞうけん=造立)」という国を挙げての難事業について、聖武天皇は「若し朕が時に造り了るを得ざるあらば来世に於て身を改めて猶作らん」と述べ、自らを「三宝(あるいはみほとけ)の奴(やっこ)と仕えまつる天皇(すめらみこと)」と称しました。華厳経の教理が明らかにされてはじめて聖武天皇の熱意と信仰心が伝わり、これが原動力となって可能になったとも伝わります。
現在の境内は、世界最大級の木造建造物である大仏殿(だいぶつでん)を中心に、南大門(なんだいもん)、鐘楼(しょうろう)、俊乗堂(しゅんじょうどう)、開山堂(かいさんどう)、法華堂(三月堂)、二月堂、戒壇院戒壇堂(かいだんいんかいだんどう)、転害門(てがいもん)などの建造物が建ち並んでいます。また、大仏殿の北方(裏手)には正倉院(しょうそういん)、東方には、宇佐八幡宮より東大寺の鎮守神として勧請された手向山八幡宮(たむけやまはちまんぐう)があります。諸堂内には、盧舎那仏をはじめとして多数の国宝・国重要文化財の彫刻を蔵します。
◆東大寺二月堂の修二会

「東大寺二月堂(とうだいじ にがつどう)」で行なわれる「修二会(しゅにえ)」は、天平勝宝4年(752)東大寺開山の良弁僧正(ろうべんそうじょう)の高弟・実忠(じっちゅう)和尚によって始められたと伝わります。創始以来、令和の現在までいちども途絶えることなく続けられ、引き継がれたものとして「不退の行法(ふたいのぎょうほう)」といわれています。
この法会は3月1日から2週間にわたって行われます。もとは旧暦2月1日から行われていたため「2月に修する法会」の意味で「修二会」と呼ばれています。また、「二月堂」の名もこれに由来しています。
修二会の法要は、正しくは「十一面悔過(じゅういちめんけか)」といい、十一面観世音菩薩を本尊とし、天下泰平・五穀豊穣・万民快楽などを祈願し、人々に代わって懺悔の行を勤めるものです。前行、本行を併せてほぼ1ヶ月、準備期間を含め3ヶ月にも及ぶ大きな法要となります。

毎年、良弁僧正の命日(12月16日)の朝、翌年の修二会を勤める「練行衆(れんぎょうしゅう)」11名の僧侶と配役が発表されます。明けて2月20日より別火(べっか)と呼ばれる前行が始まり精進潔斎して、3月1日からの本行に備えます。そして3月1日から14日までの2週間、27ヶ日夜の間、二月堂において修二会の本行が勤められます。
行中の3月12日深夜(13日の午前1時半頃)には「お水取り」といって、若狭井(わかさい)の井戸から観音さまにお供えする「お香水(おこうずい)」を汲み上げる儀式が行われます。また、この行を勤める練行衆の道明りとして、夜毎大きな松明に火が灯されます。このため修二会は「お水取り」「お松明」とも呼ばれるようになりました。
お水取りのあと、再び悔過法要が日に6回行われ、最終日の15日に満行を結んで、すべての修二会の行事が終了します。

東大寺
◇奈良市雑司町406-1
◇JR・近鉄「奈良駅」から市内循環バス「東大寺大仏殿・春日大社前」下車
◇近鉄「奈良駅」から、ぐるっとバス「大仏殿前駐車場」下車
◇公式サイト:https://www.todaiji.or.jp
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
関西では、12日の「お水取り」が終わらないと春がやって来ないと言い伝えられるほど親しまれ人気のある行事ですが、見物人のなかにはモラルのない行動をとる人がいるようです。
二月堂はいにしえよりご本尊との結縁のため無数の方が連綿と祈りを捧げてこられた場です。行法を取り巻く雰囲気が損なわれれば、現在の形で伝統を次代へ繋いでいくことも難しくなってしまいます。『法句経』に「七仏通戒偈」として、「諸悪莫作(しょあくまくさ)衆善奉行(しゅぜんぶぎょう)自浄其意(じじょうごい)是諸仏教(ぜしょぶっきょう)」の教えがあります。「あらゆる悪を為さず、善を保ち、自分の心を清めること、これが諸仏の教えである」という意味です。
時と場所に応じたルールや守っていただきたいお願いがあります。心を整え自分勝手がでないように臨みましょう。他を慮ることがすべての調和につながります。どのような形であれ、行法の周囲に身を置かれるにあたり、少し心の準備をしてご参詣いただければ幸いです。
東大寺の公式サイトより引用
みなさんは非礼のないように参拝なさって下さい。
時節柄お体ご自愛専一の程
筆者敬白