■6月24日「清正公(せいしょうこう)忌」です。■
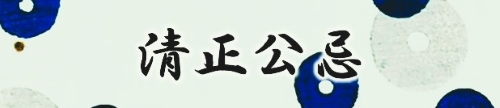
「加藤清正(かとうきよまさ)」は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての武将です。幼名「夜叉丸(やしゃまる)」、元服後は「虎之助清正(とらのすけきよまさ)」と改名。幼少時より「豊臣秀吉(とよとみひでよし)」に仕え、各地を転戦して武功を挙げ、肥後北部を与えられました。秀吉没後は「徳川家」の家臣となり、「関ヶ原の戦い」での働きによって肥後熊本藩の初代藩主となりました。

永禄5年(1562)6月24日、尾張土豪・加藤清忠(かとうきよただ)の子として尾張国愛知(えち)郡中村(現在の名古屋市中村区)に生まれたと伝わります。清正が幼い時に父の清忠が死去。母・伊都が秀吉の生母「大政所(おおまんどころ)」の従妹(あるいは遠戚)であったことから、血縁関係にあった秀吉に仕えました。

因幡国「鳥取城攻め」、備中国「冠山城(かんむりやまじょう)攻め」などで功績をあげ、天正11年(1583)羽柴秀吉と柴田勝家が戦った「賤ヶ岳の戦(しずがたけのたたかい)」では、「賤ヶ岳七本槍(しずがたけのしちほんやり)」のひとりとして名を挙げました。
加藤清正は一般に「智勇兼備の名将」として知られますが、同時に「藤堂高虎(とうどうたかとら)」と並ぶ「築城の名手」としても知られます。熊本城、蔚山倭城(ウルサンワジョウ、現在の韓国蔚山広域市)、江戸城、名古屋城など数々の城の築城に携わりました。

また、領内の「治水」事業にも意欲的に取り組み、新田開発、河川工事に力を尽くしました。熊本県内には現在も清正による遺構が多く存在します。このとき清正は莫大な人手をまかなうため、男女の別なく動員しました。きちんと給金を払い、必要以上の労役を課すことなく、農事に割く時間を確保した上でのことであったため、領民たちもよくこれに協力したといいます。さらに、財政強化策として大船を造って「朱印船(しゅいんせん)」を仕立て、暹羅(シャム:現在のタイ)や交趾(こうち、こうし:現在のベトナム中部から南部)と交易を行ないました。

また、日蓮宗の熱心な信徒でもあり、領内に「本妙寺(ほんみょうじ)」(加藤家代々の菩提寺)をはじめとする日蓮宗の寺を数多く創設しています。
慶長16年(1611)、山城国京都「二条城(にじょうじょう)」において、徳川家康と豊臣秀頼(ひでより)の会見が行なわれ、両者の和解を無事に斡旋した清正は、6月24日、帰国途中の船内で発病し熊本で死去。享年50。清正の死から4年後の慶長20年(1615)家康によって豊臣家は滅ぼされました。
清正の没後、敬意と親しみをこめて「セイショコ(清正公)さん」と呼び、清正を祀って諸願成就を願う信仰が生まれ、熊本から九州一円へと広がりました。はじめは法華宗(日蓮宗)の寺が中心でしたが、明治維新の神仏分離の際、熊本城内に「加藤神社(かとうじんじゃ)」が創建されました。治世の名君「加藤清正公」を祀る、宗教・宗派を超えた庶民信仰を「清正公信仰(せいしょうこうしんこう)」といいます。
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

野菜の「セロリ」を日本に持ち込んだのは、加藤清正とされています。「文禄・慶長の役(ぶんろく・けいちょうのえき)」(豊臣時代の朝鮮半島出兵)の際に持ち帰りました。のち1800年頃にオランダ船により運ばれましたが、独特の強い香りのために普及しなかったのだとか。盛んに栽培されるようになったのは、戦後、食生活が洋風化が進んでからのことです。セロリは「清正ニンジン」の異名で呼ばれることがありますが、当初清正がニンジンの種と騙されて日本に持ち帰ったためという説があります。
筆者敬白













