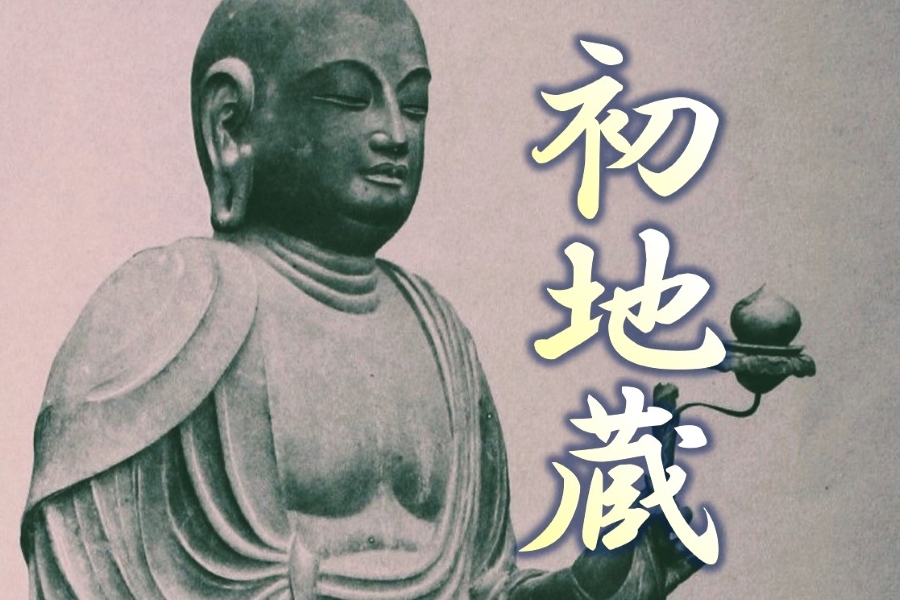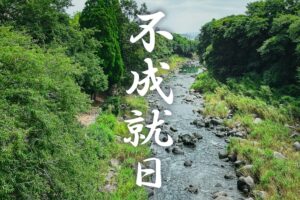■1月24日「初地蔵」です。■
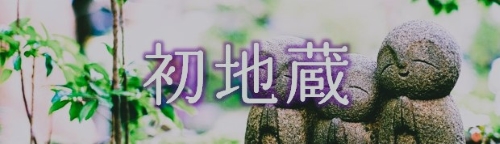
毎月24日は「地蔵の縁日」です。縁日とは、神仏のこの世との有縁(うえん)の日。24日が地蔵の縁日というのは平安時代の中期頃にはすでにいわれていました。年のはじめの1月24日は「初地蔵(はつじぞう)」、年の最後の12月24日は「納めの地蔵」と呼ばれます。「終い地蔵(しまいじぞう)」とも。
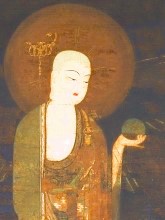
地蔵菩薩(じぞうぼさつ)は、サンスクリット語で「クシティガルバ」。「クシティ」は「大地」を、「ガルバ」は「胎蔵」「子宮」を意味することから「地蔵」とされています。遡ると、インド神話、バラモン教を通して仏教に取り入れられた「地母神(ちぼしん、じぼしん、プリティヴィー)」すなわち「地天(じてん)」です。
この「地天」に対して「梵天(ぼんてん)」があり、こちらは天を司るとされる「虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)」です。本来は、地天の地蔵菩薩と梵天の虚空蔵菩薩は一対として存在しています。それまで日本で一般的に広まっていたのは「民間信仰」の田の神地蔵信仰だったので、そこに地蔵菩薩が深く結びついたと考えられています。

民俗仏典のひとつ『地蔵十王経(じぞうじゅうおうきょう)』によれば、地蔵菩薩は、「閻魔大王(えんまだいおう)」の化身と言われ、釈迦入滅後、56億7千万年後に弥勒菩薩(みろくぼさつ)が現れるまでのあいだ、「六道(ろくどう、りくどう:地獄道・餓鬼道・阿修羅道・畜生道・人間道・天道)」の一切衆生を救う菩薩とされています。もともと地獄信仰と地蔵菩薩とは別個のものでした。
ここで「地蔵菩薩」がもともと「地」を司ることから、農耕民族である日本人にとって民間信仰の対象の「地霊・田の神」とほどなく融合して、地蔵信仰と地蔵菩薩が「お地蔵様」として伝えられています。
右手に錫杖、左手に宝珠をといった姿の地蔵から、僧侶をモチーフにした地蔵、童子の姿の地蔵など多岐にわたります。呼び方も時代と共に「地蔵菩薩」から親しみをこめて「お地蔵さま」へと変化しています。
地蔵に参詣すると、「地蔵の十福(じぞうのじっぷく)」といって、女人泰産・身根具足・衆病疾除・寿命長延・聡明智慧・財宝盈益・衆人愛敬・穀物成熟・神明加護・証大菩提の10の福徳が授けられるといわれます。
真言は「オン カカカ ビサンマエイ ソワカ Aum ha ha ha vismaye svaahaa」。
■1月24日 東京、巣鴨とげぬき地蔵尊「正月大祭」です。■
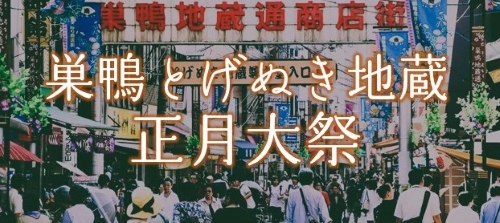
「萬頂山 高岩寺(ばんちょうざん こうがんじ)」は曹洞宗の寺院で「とげぬき地蔵」と呼ばれ有名です。江戸時代の頃、武士の田付又四郎の夢枕に立った「地蔵観音のお告げ」によって地蔵尊の姿を描いた紙を川に流すと、たちまち妻の病が回復したと伝わります。
これが「御影(おすがた、おみかげ)」の始まりとされ、毛利家の女中が針を誤飲し、御影を飲み込んだところ、針を吐き出すことが出来たという逸話から「とげぬき地蔵」と呼ばれるようになりました。「御影(おすがた、おみかげ)」とは、秘仏である延命地蔵尊(えんめいじぞうそん)をもとに書かれた、縦4cm×横1.5cmの「和紙の札」のこと。諸病の治癒改善にも利益があるとされ、現在に至るまでその御利益を求めて参拝者が絶えません。
とげぬき地蔵尊は、ほかに「洗い観音像」が有名です。

縁日は毎月4のつく日に行われ、正月・5月・9月の24日は大祭が行われます。1月24日は「正月大祭(しょうがつたいさい)」です。大祭は「大般若経と地蔵尊に現世利益を願う大祈祷法要」です。午前と午後の2回、本堂で30名ほどの僧侶が、「大般若波羅蜜多経(だいはんにゃはらみったきょう)」600巻を転読(転翻、てんぽん)し、「仏説延命地蔵菩薩経(ぶっせつえんめいじぞうぼさつきょう)」を歩きながら唱え、大間を5周します。
東京・巣鴨は高齢の女性が多く訪れることから「おばあちゃんの原宿」と呼ばれて親しまれ、いつも買い物客や食事を楽しむ人びとであふれています。巣鴨地蔵通り商店街は全長800m弱の通りに約200店舗が軒を連ね、とげぬき地蔵尊の縁日(4のつく日)には多くの人が訪れ賑わいます。
とげぬき地蔵尊(萬頂山高岩寺)
 ◇東京都豊島区巣鴨3-35-2
◇東京都豊島区巣鴨3-35-2
◇JR山手線、地下鉄三田線「巣鴨駅」徒歩5分
◇都電荒川線「庚申塚駅」徒歩10分
◇公式サイト:https://togenuki.jp
◆巣鴨地蔵通り商店街:https://sugamo.or.jp