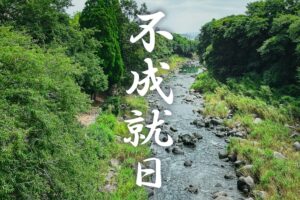■1月20日「二十日正月」です。■
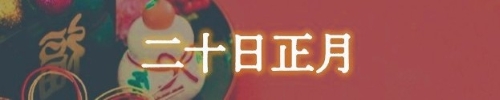
「二十日正月(はつかしょうがつ)」とは、正月の終わりとなる節目の日。この日をもって正月行事は終了とします。正月祝いの納めとして仕事を休む「物忌み」の日。この日、正月の飾り物などは外して、正月行事を締めくくります。

正月にお迎えしていた山の神さま、田畑の神さまがお帰りになる日と考えられていました。神さまがお帰りになるので前夜19日の晩に、尾頭付きのお膳や、小豆御飯をお供えする地方もあります。
京阪神地方では、正月に用いた鰤(ぶり)の骨や頭を20日のあいだ、酒粕の中に入れておき、この日に取り出して、牛蒡(ごぼう)や大根、大豆などと一緒に煮て食べます。このことから「骨正月(ほねしょうがつ)」「頭正月(あたましょうがつ、かしらしょうがつ)」と呼びます。

東日本では「棚探し」、岐阜県では「フセ正月」、石川県では「乞食正月」、岩手県では「二十日ワッパカ」といって、正月のご馳走や餅などを食べ尽くす風習があります。
暦の上では11日に行われることの多い「鏡開き」ですが、江戸時代の初期の頃、この日が鏡開きの日でした。武家では、鎧兜・具足に供えた餅を、刃物を使わず槌(つち)で割り、お雑煮にして食しました。これを「具足開き」と呼んで祝いました。

明治44年(1911)に出版された『東京年中行事』(若月紫蘭著)には、
「廿日正月(はつかしょうがつ)とも骨正月とも云って、お雑煮のお仕舞(おしまい)である。今日を正月のお仕舞として、女子供の遊び戯るることは関西地方にはまだ盛(さかん)なれど、東京では殆ど名のみで有る」
「此日(このひ)また夷講(えびすこう)と云って、商家では鯛を供えて恵比寿と大黒の二神を祭り、どうかどっさり儲かりますようにと祈りながら、親戚知己を迎えて盛んな酒宴を張ると云うことは、昔は一般に行われたもので有るが、今は夷講は大方秋にゆずって、正月にはあまり行われて居らず、従って十九日の晩に大伝馬町の邊り(あたり)に立った夷講の為の市も殆ど姿がない」
とあり、明治の終わり頃にはすでに、各地で行われていた二十日正月の風習は地方によってはすっかり廃れてしまっていたことがうかがえます。
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
正月7日の「七草」、11日、15日と「正月終い」の行事はそれぞれですが、正月終いの行事もこの二十日正月でいよいよお開きです。
すでに今年の目標を立て日々精進している皆様はさておき、いまだ正月気分の抜けていない方は1月20日に今年の目標を立てて邁進してください。三日坊主にならないような目標が大切です。今年こそはと毎年志を立てても、挫折の連続だと嘆いている貴方、それこそ「今年こそは」と志を高く持ちましょう。
筆者敬白