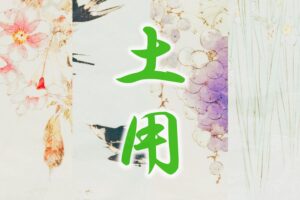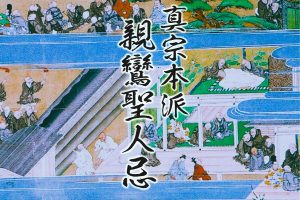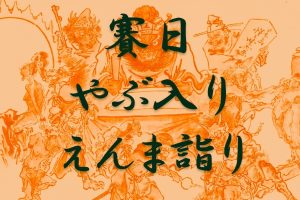■1月9~11日「十日戎(とおかえびす)」です。■

「十日戎(とおかえびす)」は、漁業の神、商売繁盛の神、五穀豊穣の神として有名な七福神の「えびす様」を祀るお祭りです。9日の「宵戎(よいえびす)」、10日の「本戎(ほんえびす)」、11日の「残戎(のこりえびす)、残り福(のこりふく)」の3日間、にぎやかに行なわれます。

「えべっさん」と呼ばれ親しまれている「えびす(恵比寿、戎、夷)さま」。その姿は左脇に鯛を、右手に釣竿を持っています。もともと漁業の守り神で、海からの幸をもたらす神を象徴しています。いつしか福徳を授ける神、商業の繁栄を祈念する神として、厚く信仰されるようになりました。

大阪では古く江戸時代の昔から、毎年1月9日の「宵戎」には雑喉場魚市場(ざこばうおいちば)が、えびす様に縁が深い「大鯛(雌雄一対)」を「今宮戎神社(いまみやえびすじんじゃ)」に奉献し、大漁と商売繁盛を祈願するのが吉例になっていました。明治から昭和前期にかけては、盛大に美しく飾った「献鯛行列」が厳粛に繰り広げられました。
現在では、雑喉場魚市場の流れを継承する大阪木津市場の人びとによって「十日戎献鯛神事」が奉納されています。300年来の由緒ある古式作法にのっとり、縁起の良い鯛の初セリも境内で賑々しく行われます。

また、「宝恵かご(ほえかご)」の行列も見どころです。200年以上前、大阪ミナミの芸妓衆が派手にカゴを繰り出して今宮戎神社に参詣したことが始まりだそうです。明治から昭和の戦前には、100挺ものカゴが華麗を競ったといいます。
京都東山の「京都ゑびす神社」の「宝恵かご社参」は「東映太秦映画村」の女優さんたちが江戸時代の芸姑に扮して参拝します。11日の残り福では、舞妓さんたちが「福笹」授与に奉仕します。

◆縁起物「福笹」
十日戎では「福笹(ふくざさ、ふくささ)」といって、笹にえびす様のお札、鯛や小判などの福々しい飾り「吉兆(きっちょう、きっきょう)」を付けた縁起物が授与されます。えびす様の釣り竿が竹でできていていることにあやかって、笹で縁起物をこしらえたのだとか。関東の「酉の市」の縁起物といえば「熊手」ですが、関西を中心に十日戎が行われる地域では「福笹」が縁起物の筆頭です。

近年、すっかり有名になったのが、「西宮のえべっさん」と地元の人びとに親しまれている兵庫県西宮市の「西宮神社(にしのみやじんじゃ)」で十日戎の日に開催される「開門神事福男選び」です。1月10日午前6時、大太鼓が鳴り響き、「赤門(あかもん)」と呼ばれる表大門(おもてだいもん)が開かれると同時に、1500名の参拝者たちが230m離れた本殿を目指して走り出します。本殿に到着した順に3着までが、その年の「福男(ふくおとこ)」に認定されます。女性も参加できます。
今宮戎神社
◇大阪府大阪市浪速区恵美須西1丁目6番10号
◇公式サイト:https://www.imamiya-ebisu.jp
◆「十日戎」:https://www.imamiya-ebisu.jp/tokaebisu
京都ゑびす神社
◇京都市東山区大和大路四条南
◇公式サイト:http://www.kyoto-ebisu.jp
◆「十日ゑびす大祭(初ゑびす)」:http://www.kyoto-ebisu.jp/tooka.html
西宮神社
◇兵庫県西宮市社家町1-17
◇公式サイト:https://nishinomiya-ebisu.com
◆「正月・十日えびす」特設サイト:https://nishinomiya-ebisu.jp/tookaebisu/
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

関西では一般的な「えべっさん」です。七福神の「えびす様」のご利益拝受の神事です。境内、付近路上で流される「商売繁盛、笹持ってこい」のお囃子は耳に残ります。
活気はあっても「小寒」から「大寒」の最中です。お出掛けになってお風邪などお召しにならないようお体ご自愛専一の程
筆者敬白