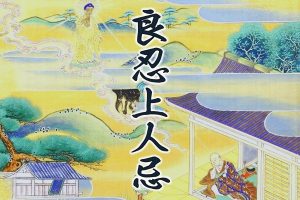■2月25日 京都、北野天満宮「梅花祭(ばいかさい)」です。■

「北野天満宮(きたのてんまんぐう)」は、全国の菅原道真(すがわらみちざね)公を祀る神社の宗祀(総本社)です。国を鎮め守る神として「天神さん」「北野さん」と呼ばれ親しまれています。

平安時代中期、多治比文子(たじひのあやこ)〔※〕らによって北野の右近馬場(うこんのばば)〔※〕に菅原道真公の御霊を祀ったのが始まりとされています。また、近江国・比良宮の禰宜神良種(みわのよしたね)の息子に道真の託宣が下り、北野に祀られたい旨が告げられたため、良種が北野朝日寺の最鎮とはかって社殿を設けたのが北野天満宮のはじまりという言い伝えもあります。いずれにしても、北野の地は、道真を祀る以前から農耕生活に関係ある祈雨の神としての「天神(雷神)」が祀られていて、そこに火雷天神としての道真の霊が結び付き、祀られるようになったと考えられています。
道真公は「和魂漢才(わこんかんさい)」〔※〕の精神を以って学問に勤しみ、幼少の頃より文才を表し、朝廷の官吏として活躍しましたが、天皇を廃立して娘婿の斉世親王を皇位に就けようと謀ったとして、昌泰4年(901)大宰府に左遷され、わずか2年後に薨去。永延元年(987)一条天皇の令により初めて勅祭が執り行なわれ、北野の社に「北野天満天神」の社号が贈られました。
寛弘元年(1004)の一条天皇の行幸を初めてとし代々皇室の御崇敬を受けました。旧社格は官幣中社。特に学問の神として知られ、江戸時代には寺子屋の精神的背景として菅原公がお祀りされました。いまもなお多くの受験生らの信仰を集め、福岡県の「太宰府天満宮(だざいふてんまんぐう)とともに「天神信仰」の中心となっています。
◆梅花祭(ばいかさい)

菅原道真公は、延喜3年(903)2月25日薨去されました。道真公の祥月命日に行われる祭典が「梅花祭(ばいかさい)」です。鳥羽天皇のころ、天仁2年(1109)2月25日に、この祭典の記録が残ることから約900年の歴史を持っているとされています。祭典では貞明皇后(ていめいこうごう)〔※〕参拝の古例により皇后陛下の御代拝が行われます。
古くは御祭神を「宥(なだめる)」と音の通じる「菜種」の花を供えて「菜種御供(なたねごく)」と称していましたが、明治以降新暦になって菜種のかわりに梅の花を用いたことから、次第に「梅花御供(ばいかのごく)」と呼ばれるようになりました。

「大飯(おおばん)・小飯(こばん)」と称すこの御供は、四斗の米を蒸し大小2個の台に盛ったもので、古くより西ノ京(にしのきょう:奈良県奈良市の西部に位置する地域)に住む宮の神人(じにん、じんにん)の末裔らにより、前日に参籠潔斎(さんろうけっさい)し調整されます。男女の厄年に因み、白梅の小枝を挿した「紙立(こうだて)」〔※〕を42組、紅梅を挿した紙立を33組、2台にわけて御神前に供えます。授与所では「紙立」に用いた玄米「厄除玄米(やくよけげんまい)」が授与されます。

道真公の詠んだ「東風吹かば匂い起こせよ梅の花 主なしとて春な忘れそ」(春になって東の風が吹いたならば、その香りを(京から大宰府の私のもとまで)送っておくれ、梅の花よ。主人(菅公)がいないからといって、(咲くべき)春を忘れてはならないぞ)が祭りの由来とされています。この歌は、菅公が無実の罪を着せられて太宰府へ左遷される前に、大事にしていた梅の木を前にして語りかけるように詠んだ歌です。その梅が京から大宰府に飛んで行き、そこで生え匂ったという言い伝えがあり、本殿前にある梅の木と太宰府天満宮にある梅の木は「飛梅(とびうめ)」と呼ばれています。
北野天満宮には、菅公ゆかりの梅50種約1,500本があり、花の時期には約2万坪の境内一円で紅白の梅が咲き競います。早咲きの梅は例年12月中旬頃からつぼみがふくらみ始め、正月明けから開花、3月末頃まで長いあいだ花と香りを楽しむことができます。
※多治比文子(たじひのあやこ):平安時代中期の巫女(みこ)。道真公の乳母(うば)をつとめていたとも伝わる。天慶5年(942)北野の右近馬場に社殿をかまえて菅原道真の霊を祀れとの神託をうける。文子は貧しかったため、はじめは西京(にしのきょう)の自宅近くに小祠をつくったが、天暦元年北野朝日寺の僧最珍らの尽力で神託の地に神殿(現北野天満宮)を造立した。
※右近馬場(うこんのばば):右近衛府(うこんえふ:左近衛府とともに、武器を持って宮中の警護、行幸の供奉などをつかさどった役所)に属した馬場。毎年5月、ここで近衛(このえ)の役人の競馬(くらべうま)の行事があった。
※和魂漢才(わこんかんさい):「和魂」とは、わが国固有の精神のことで、「漢才」とは漢字によって得た知識や才能のこと。日本固有の精神と中国渡来の学問。和魂漢才は、日本固有の精神を失わないで、中国の学問を教養として学び、消化・活用すべきの意。

※※貞明皇后(ていめいこうごう):明治17年(1884)-昭和26年(1951)。第123代天皇・大正天皇の皇后(在位:明治45年/大正元年(1912)-大正15年/昭和元年(1926))。諱(いみな)は節子(さだこ)。お印は藤。旧名は九条節子(くじょうさだこ)。昭和天皇の母。元華族。公爵・九条道孝令嬢。
※紙立(こうだて):仙花紙(せんかし、せんかがみ)を筒状にし、底に小さなかわらけを敷いて、中に玄米を入れ梅の小枝を挿し立てた特殊神饌(しんせん)のこと。「香立」とも書く。仙花紙(泉貨紙)とは、楮(こうぞ)で荒くすいた厚手の和紙のこと。
北野天満宮
◇京都府京都市上京区馬喰町
◇市バス「北野天満宮前」下車すぐ
◇嵐電「北野白梅町」駅、徒歩約7分
◇公式サイト:https://kitanotenmangu.or.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
菅原道真公の精神は「和魂漢才」に集約されるように、自国の歴史と文化にしっかりとした誇りを持ち、他国の文化も受けいれる寛容さが特徴です。また、菅原道真公が生涯一貫された「誠の心」は、今も日本人の心に生きつづけています。
2月は梅にちなんだ祭礼が続きます。北野天満宮の梅花祭は、厄除けの意味が強く、神事と解釈できます。
まだまだ寒い日が続きます。梅まつりにお出かけの際には風邪などお召しにならないようお気をつけください。
筆者敬白