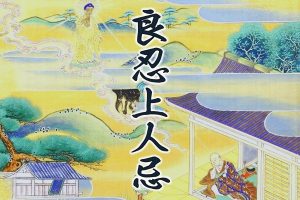■2月6日 京都、伏見稲荷「初午大祭(はつうまたいさい)」です。■
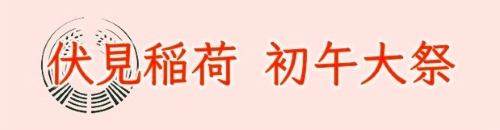
「伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)」は、全国4万社ある稲荷神社の総本宮です。主祭神に「宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)」を祀り、「佐田彦大神」「大宮能売大神」「田中大神」「四大神」を配祀します。式内社(名神大)、二十二社の上七社の一社で旧社格は官幣大社。

御神徳は「衣食住ノ太祖ニシテ萬民豊楽ノ神霊ナリ」(稲荷谷響記)、また「上ハ天子ヨリ下ハ萬民ニイタル幸福豊楽ノ神明ナリ」(十五箇條口授伝之和解)とあります。平安の昔から、「稲荷山」が民衆信仰の「お山」であり、今日では、商売繁昌・産業興隆・家内安全・交通安全・芸能上達の守護神として信仰をあつめます。
御神号は「イナリ」を「伊奈利」と記。イナリとは、イネナリ・イネニナルのつづまったもので、人間生活の根源であった「稲」によって、天地の霊徳を象徴した古語とされています。ちなみに「伏見」は「伏水」だったそうで、伏見の山にはたくさんの滝があります。
◆初午大祭(はつうまたいさい)
「初午祭(はつうまさい、はつうままつり)」とは、「稲荷大神(いなりおおかみ)」が天界より天降りて、稲荷山の三ヶ峰に初めて鎮座した和銅4年(711)の最初の午の日を偲ぶ祭りです。2月の初の午の日、伏見稲荷大社をはじめ全国的に祭礼が行われます。初午詣は「福詣」とも呼ばれ、前日の巳の日から参詣者が訪れます。

毎年初午の日、伏見稲荷大社では「初午大祭」が行われます。京洛初春第一の祭事とされています。授与される「しるしの杉」は商売繁盛・家内安全の御符として、古くから拝受する風習が盛んです。「しるしの杉」は、平安時代中期以降、稲荷社に参詣した人びとが、そのしるしとして杉の小枝をいただいて身につけたという風習に由来しています。

伏見稲荷大社
◇京都市伏見区深草藪之内町68
◇JR「稲荷駅」下車すぐ
◇市バス「稲荷大社前」下車 徒歩約7分
◇京阪電車「伏見稲荷駅」下車 徒歩約5分
◇公式サイト:https://inari.jp
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
今日「初午」といえば、年中で最も寒い時季に当り、時として節分の前にめぐり来ることすらありますが、古くは旧暦を用いていたので、節分前に「初午」が来ることはありませんでした。もう少し春めいた頃にめぐり、四季の移ろいを敏感にとらえ、その中に「もののあわれ」を見出した当時の人々は、「初午」にはこぞって稲荷社に詣でたものでした。
『蜻蛉日記』や『枕草子』には、平安時代の初期、老若男女がうち連れて「初午詣」に出かけた様子が伺えます。
筆者敬白