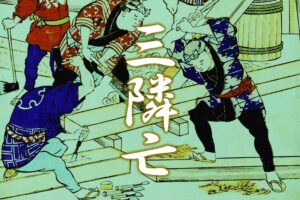■8月24日「京都、地蔵ぼん』です。■
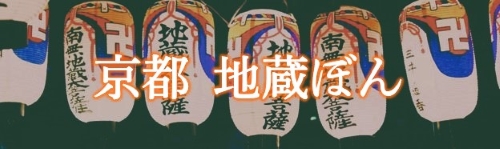
「地蔵盆(じぞうぼん)」は、「地蔵菩薩(じぞうぼさつ)」の縁日のことで、もともと「地蔵会(じぞうえ)」「地蔵祭(じぞうさい)」と呼ばれていました。24日が「裏盆(うらぼん)」〔※〕にあたることから、「盂蘭盆(うらぼん)」に因んで「地蔵盆」と呼ばれるようになりました。

旧暦で盂蘭盆行事をする地方では旧暦24日が地蔵盆になります。最近では、できるだけ参加しやすいように行事の日程を土曜日や日曜日に合わせている場合も多いです。
正確には、地蔵盆は、「道祖神(どうそじん)信仰」と結びついた路傍あるいは街角の辻に立つ「地蔵(お地蔵さま)」が対象です。寺院の中に祀られている地蔵菩薩を対象としてはいませんが、いつしか混交して同一視されるようになりました。
「地蔵菩薩」は中近世以降、子どもの守り神として信仰されました。地蔵菩薩は、親よりも先に亡くなった子どもが「賽の河原(さいのかわら=親不孝の報いで苦を受ける場)」で苦しんでいるのを救うとされています。
◆京都の「地蔵盆」
京都市では、地域と世代をつなぐまちの伝統行事として「地蔵盆」の行事を「京都をつなぐ無形文化遺産」に指定しています。

この日、「お地蔵さま」のある町内ではこの日、町内会や子ども会が主体となって、お地蔵さまを祠(ほこら)から出して洗い清め、新しい前掛けを着せ、新たに彩色して「お化粧」をほどこすなどして飾り付けます。
そして、お地蔵さまの前に集って花や「お札」を飾り、町内の人からのお供え物を備えて祀ります。提灯に見立てた「ほおずき」を飾るところも多いです。「お札」とは、「地蔵幡(じぞうばた)」のことで、この日に古いお札を奉納して、また新しいお札を授かります。

お地蔵さまの周りには、灯籠(とうろう)や行燈(あんどん)、提灯などが飾られます。町によっては青竹や幟(のぼり)を立てます。京都では、子どもが生まれるとその子の名前を書いた提灯を奉納する風習があります。女の子は赤い提灯、男の子は白い提灯で、その子が地蔵盆に参加しているあいだ毎年飾ります。
「地蔵盆の主役は子どもたち」です。行燈に絵を描くなど、子どもたちは準備の段階から参加します。
子どもたちは、「お下がり」として供物の菓子や手料理などを振舞われます。屋台が出る町もあります。「お下がり」は、ほかの地方(特に西日本)では「お接待(おせったい)」とも呼ばれます。

「数珠繰り(じゅずくり)」または「数珠まわし」は、輪の直径3~5mの大きな数珠を囲んで座り、南無阿弥陀仏を唱えながら順に回していく儀式です。回す回数は108回。人間の煩悩と同じ数です。自分のところに大きな房や珠の部分が回ってきたら一礼します。もともとは浄土宗の「百万遍念珠繰り(ひゃくまんべんねんじゅくり)」から来ていますが、地域信仰として広がり、「百万遍さん」と呼ばれ、宗教・宗派に関係なく親しまれている行事です。
※裏盆(うらぼん):「盂蘭盆(うらぼん)」の終わりのことを「裏盆」といいます。お盆とは13日~16日。七月盆、八月盆とありますが、お盆の終わりと言えば16日です。裏盆の時期も16日、20日、24日、27日など地域ごとにまちまちです。
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

地域や習慣は違っても、子どもの成長を願う親心に古今東西変わりはないようです。近年、親が子どもを虐待する報道をしばしば耳にするようになりました。子どもに接するときは慈愛の心をもちたいものです。
筆者敬白