■8月23~24日 愛知、西尾市「三河一色大提灯まつり(みかわいっしきおおぢょうちんまつり)」です。■
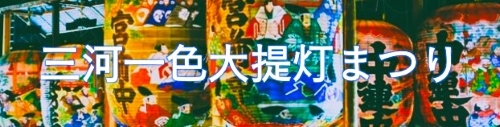
「三河一色大提灯まつり(みかわいっしきおおぢょうちんまつり)」は、愛知県西尾市一色町(にしおしいっしきちょう)にある「諏訪神社(すわじんじゃ)」の例祭で、例年8月第4土曜日・日曜日に行なわれます。

「諏訪神社」の主祭神は「建御名方命(たけみなかたのみこと)」です。建御名方命は国土開発・耕作・雨乞い・狩猟の神といわれます。全国で有名な諏訪神社が海の近くに鎮座していることから、海上航海にも御神徳があるとされています。「三河一色諏訪神社(みかわいっしきすわじんじゃ)」と表記されることもあります。
全国にある「諏訪大社」の分社は15000社。そのうち「三河一色諏訪神社」は、長崎・神戸・四日市・横須賀・藤沢に次いで6番目に登録されています。
第106代正親天皇(おおぎまちてんのう)の世、永録年間当時、鎮守の神を持たなかった一色の地に守り神を招こうと村人たちが考えていたところ、日本六十六ヵ所の霊場に「法華経」を納め歩いていた行者がやってきて、信濃の「諏訪大明神」(諏訪大社)の御分霊を請け、祠を建てて祀ったのが始まりと伝わります。
◆三河一色大提灯まつり(みかわいっしきおおじょうちんまつり)

「三河一色大提灯まつり」の発祥は、はじめは神事として篝火(かがりび)を焚いていました。それが100年ほど続き、寛文年間(1661~1672)に提灯を献灯する祭りに発展したようです。江戸中期には、経済的な余裕も生まれ、提灯の上部に覆いを付けたりと、次第に華美になり、大きさを競うようになって、現在の姿へと変わっていきました。
三河一色の6組(間浜組・上組・中組・大宝組・宮前組・諏訪組)が、それぞれ3本の柱に屋根型の覆いを付け、大提灯を2張りずつ掲げて神前で献灯します。提灯が大きくなる過程で、柱が2本から3本になり、骨の材質が竹から桧に変わりましたが、現在も諏訪組の提灯だけは伝統を守り竹の骨でできています。

大提灯は長いあいだに張替えなど、幾度となく手を入れられて現在に伝わっています。平成6年(1994)から平成13年(2001)にかけて、約130年ぶりに全ての提灯が修復されました。「一色の大提灯六組」は昭和44年(1969)愛知県の有形民俗文化財に指定されています。
古式豊かな絵模様が描かれた、最長約10m、直径約5mの大提灯12張が、昼は青空に映え、夜は境内を照らします。「神楽桟(かぐらさん)」(ウインチ)を使って巨大な提灯を引き揚げる献燈準備も見ものです。
諏訪神社
◇愛知県西尾市一色町一色宮添129
◇名鉄「西尾駅」より名鉄東部交通バス「一色大宝橋」下車
◇名鉄「碧南駅」「吉良吉田駅」より、ふれんどバス「大宝橋」下車
◇公式サイト:https://www.katch.ne.jp/~suwa-jinja/
◆三河一色大提灯まつり(西尾市観光協会):https://nishiokanko.com/list/special/lantern/
◆三河一色大提灯まつり(愛知県の公式観光ガイド Aichi Now):https://www.aichi-now.jp/spots/detail/145/













