■8月9日 宝塚、中山寺「星下り大会式(ほしくだりだいえしき」です。■
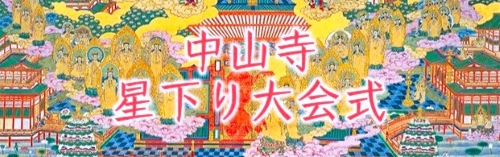
「西国三十三所(さいごくさんじゅうさんしょ)」第24番札所の「中山寺(なかやまでら)」は、兵庫県宝塚市にある真言宗中山寺派の大本山です。本尊は「十一面観世音菩薩(じゅういちめんかんのんぼさつ)」です。その姿はインドの王妃「勝鬘夫人(しょうまんぶにん、シュリーマーラー)」が女性を救済することを願った故事にもとづいて刻まれた三国伝来の尊像と伝えられます。左右の脇侍も十一面観音であり本尊と脇侍をあわせて三十三面となります。

寺伝によると、「中山寺」は「聖徳太子(しょうとくたいし」創建による、わが国最初の「観音霊場」とされます。仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)の先后「大中姫(おおなかひめ)」、その皇子「麛坂皇子(かごさかのおうじ)」と「忍熊皇子(おしくまのおうじ)」の兄弟の追善供養のため、あるいは、「聖徳太子」「蘇我馬子(そがのうまこ)」との政争に敗れた「物部守屋(もののべのもりや)」の霊を鎮めるため、建立されたと伝わります。
地元の人びとには「中山さん」と呼ばれて親しまれ、「安産祈願」の寺として、また、梅の名所としても有名で、一年を通じてたくさんの参拝客が訪れます

観音菩薩を祀る、2府5県に渡る33ヶ所の寺院を「西国三十三所」といいます。令和元年(2019)「1300年つづく日本の終活の旅〜⻄国三十三所観音巡礼〜」として「日本遺産」に登録されています。
養老2年(718)、大和国「長谷寺(はせでら)」の開祖「徳道(とくどう)上人」が、急な病いで仮死状態になり、冥土へ行くと「閻魔大王(えんまだいおう)」に会いました。そこで「生前の悪行によって地獄へ送られるものが多いゆえ、観音の霊場へ参ることにより功徳が得られるよう、人びとに観音菩薩の慈悲の心を説け」と命じられ、「起請文(きしょうもん)」と極楽往生の通行証となる「御宝印(ごほういん)」を授かりました。徳道上人は観音巡礼の流布に努めましたが、世に広まらず、機が熟すまで御宝印を中山寺の白鳥塚古墳(中山寺古墳)内の「石の櫃(からと)」に納めました。270年後、平安時代になって、第65代「花山天皇(かざんてんのう)」が退位し仏門に入って法皇となると、永延2年(988)、石の櫃から御宝印を取り出し、「西国三十三所」を再興しました。
「観音菩薩」は三十三の姿に変身し、いかなる困難に出会っても常に慈悲の心で人びとを見守り、救うといわれます。閻魔大王の約束の証である宝印を33ヶ所すべての寺院で集めると、極楽浄土への通行手形となるとされています。
◆星下り大会式

古来より、「8月9日(ここのかび)」は、西国三十三所の観音さまが中山寺に集まる日とされ、この日に参拝すると西国三十三所観音霊場のすべてに参拝したのと同じ功徳があると伝わります。また、この日は、観音さまの功徳日「四万六千日(しまんろくせんにち)」でもあり、この日一日で一生分の参拝の功徳を得られるとされています。
中山寺では、8月9日は、西国三十三所の観音さまが中山寺に集まるさまが、まるで星降るようであることから「星下り(ほしくだり)」と呼ばれます。「星下り大会式」では、参道沿いの5ヶ院の「塔頭(たっちゅう)」に属する各講の講員たちが「おねり」をなし、「梵天(ぼんてん)」を本堂まで迎えにいきます。そして、授かった「梵天」をおねりの先頭にすえ、観音さまの功徳が参拝者に振り(降り)そそがれるよう、境内を激しく練り歩きます。
紫雲山 中山寺
◇兵庫県宝塚市中山寺2丁目11-1
◇阪急電鉄宝塚線「中山観音駅」徒歩1分
◇JR宝塚線「中山寺駅」徒歩10分
◇公式サイト:https://www.nakayamadera.or.jp
◆「西国三十三所 巡礼の旅」第二十四番 中山寺:https://saikoku33.gr.jp/place/24
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

安産祈願や子授かり信仰で有名な、宝塚・中山寺の「星下り大会式」は、年にいちどの特別な功徳日です。残暑きびしい時節ですが、一日で西国三十三所巡りと同じ功徳を得られるそうですから、近郊のかたはぜひ観音さまを拝みにお出かけください。
読者の皆様、ご自愛専一の程
筆者敬白













