■大宮氷川神社「例大祭」です。■
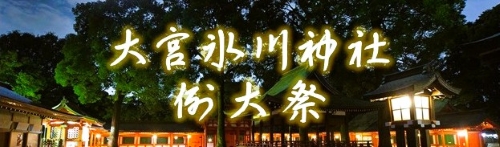
埼玉県さいたま市大宮区に鎮座する「氷川神社(ひかわじんじゃ)」は、武蔵国を中心に全国に200余社ある「氷川神社(ひかわじんじゃ)」の総本社です。「勅祭社(ちょくさいしゃ)」(祭祀の際、天皇により勅使が遣わされる神社)で、旧社格は「官幣大社」。社伝によると、今から2400有余年の昔、第5代孝昭天皇3年4月に創建されたと伝わります。

『延喜式神名帳』では「名神大社」に列し、聖武天皇の時代に「武蔵国一宮」に定められました。「武州六大明神(ぶしゅうろくだいみょうじん)」〔※〕のひとつとされ、他の氷川神社と区別するため「大宮氷川神社(おおみやひかわじんじゃ)」と呼ばれています。
そもそも、地名の「大宮(おおみや)」は、氷川神社の本宮を「大いなる宮居(みやい)」すなわち「大宮」と称えたことに由来します。平成13年(2001)大宮市、浦和市、与野市の3市が合併して「さいたま市」となったため、「大宮市」という名は地図上から消滅しました。

御祭神は「須佐之男命(すさのおのみこと)」で、妻の「稲田姫命(いなだひめのみこと)」、子孫の「大己貴命(おおなむちのみこと)」を合わせて祀ります。
第13代「成務天皇(せいむてんのう)」〔※〕の時代、出雲の「兄多毛比命(えたもひのみこと)」が一族を連れてこの地に移住し、武蔵国造(むざしのくにのみやつこ)となり、氏神として氷川神社を崇敬しました。この一帯は、「出雲族(いずもぞく)」が開拓した地で、武蔵国造は出雲国造(いずものくにのみやつこ)と同族とされます。社名の「氷川」も、出雲の「簸川、肥河(ひかわ)」という川(現在の「斐伊川」)の名に由来するという説があります。
明治以後、「国都(くにのみやつこ)」が武蔵国に設置されたことから、四方拝〔※〕などの「宮中祭祀(きゅうちゅうさいし)」の対象に加えられるなど、皇室からも重んじられました。
◆例大祭、大宮夏まつり「中山道まつり」
毎年8月1日「例大祭」が行なわれます。大祭であるため、神職は神社に篭り潔斎します。8月1~2日、大宮駅東口周辺では大宮夏まつり「中山道まつり」が行なわれます。氷川神社でお祓いを受けた神輿渡御、山車の揃い巡行、民謡輪おどり、阿波おどり、太鼓演奏などさまざまな催しで賑わいます。

※武州六大明神(ぶしゅうろくだいみょうじん):武蔵国総社の大國魂神社(東京都府中市)で祀られており、大國魂神社の例祭「くらやみ祭」に参列する武蔵国の一之宮から六之宮までの6社の神社をいう。「武蔵国六大明神」「武州六社明神」「武州六社」とも。
一之宮、小野神社(東京都多摩市)
二之宮、二宮神社(東京都あきる野)
三之宮、大宮氷川神社(埼玉県さいたま市)
四之宮、秩父神社(埼玉県秩父市)
五之宮、金鑚神社(かなさなじんじゃ、埼玉県児玉郡神川町)
六之宮、杉山神社(神奈川県横浜市緑区)
*「氷川神社」自体は「武蔵一宮」の社標を掲げているが、武蔵国内における位置付けとしては一宮と三宮の2説がある。
※成務天皇(せいむてんのう):垂仁32年-成務60年(84-190)。在位:成務天皇元年1月5日-同60年6月11日。『日本書紀』での名は「稚足彦天皇(わかたらしひこのすめらみこと)」。日本で初めて行政区画を定めたとされている。実在説もあるが、通説では神話時代での天皇のひとりに挙げられる
※四方拝(しほうはい):宮中で行なわれる一年の最初の儀式。天地四方の神祇(じんぎ)を拝して年災をはらい豊作を祈る儀式。戦前は「四方節」〔※〕と呼ばれていた。
◆拝する山陵:伊勢神宮、天神地祇、神武天皇陵・先帝三代(明治天皇の伏見桃山陵、大正天皇の多摩陵、昭和天皇の武蔵野陵)の各山陵、武蔵国一宮(氷川神社)・山城国一宮(賀茂別雷神社と賀茂御祖神社)・石清水八幡宮・熱田神宮・鹿島神宮・香取神宮
※四方節(しほうせつ):「元日(がんじつ)」のこと。年の最初の日、1月1日。年のはじめを祝う日として国民の祝日とされていた大東亜戦争以前の呼び方。もと祝日とされた4つの大きな「節会(せちえ)」の日。四方拝(1月1日)・紀元節(2月11日)・天長節(4月29日)・明治節(11月3日)の総称。「四大節(しだいせつ)」とも。
武蔵一宮 氷川神社(大宮氷川神社)
◇埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-407
◇東武線「北大宮駅」または「大宮公園駅」徒歩10分
◇公式サイト:https://musashiichinomiya-hikawa.or.jp
◆大宮夏まつり「中山道まつり」(さいたま市公式観光サイト):https://visitsaitamacity.jp/events/24
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

よその土地で「関東の人間だ」と名乗ることができる人は、「武州六大明神巡り」をして、最後の府中の「大國魂神社」にご報告した人だけだと伝わります。いつの時代も土地に馴染むには、それなりの掟があるようです。3代前から芝で生まれて神田で育つのが江戸っ子です。江戸時代は下町でも、現代では超高層高級マンションの住宅地です。これを機会に「武州六大明神巡り」にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
お出かけの際には、熱中症対策に飲み物や日傘、帽子をお忘れなく。
筆者敬白













