■4月28日「日蓮宗 立教開宗会」です。■
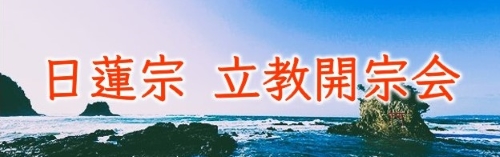
「日蓮宗(にちれんしゅう)」とは、鎌倉時代中期の僧・「日蓮聖人(にちれんしょうにん)」によって興された仏教宗派です。もっぱら『法華経(ほけきょう)』に帰依するため、俗に「法華宗(ほっけしゅう)」とも呼ばれます。
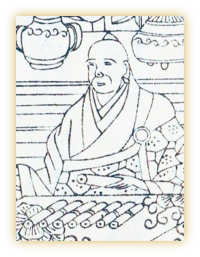
日蓮を宗祖とする諸宗派のうち「宗教法人日蓮宗」を指し、宗務院を池上本門寺(いけがみほんもんじ、東京都大田区池上)、総本山を身延山久遠寺(みのぶさんくおんじ、山梨県身延町)に置く57総、大、本山の連合宗派で、「釈迦本仏論と一致派>」「釈迦本仏論と勝劣派」「宗祖本仏論と勝劣派」など教義の異なる諸門流を包含する日蓮系諸宗派中の最大宗派です。寺院数は5200ヶ寺、直系信徒は330万人。
さらに「日蓮正宗(にちれんしょうしゅう)」のほか、教義を異とする分派を含む場合があります。また、日蓮宗と歴史的に関連が深く「南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)」の題目を唱える新宗教系の信徒団体としては、立正佼成会、霊友会、佛所護念会教団などがあり、直系とは別にこれら信徒団体に在籍の400万世帯の信徒が存在します。
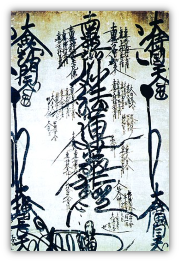
日蓮が生きていた鎌倉時代、飢饉や疫病、旱魃や風水害、大地震などのが立て続けに起き、戦乱も多く、世の中は混沌としていました。そんななか、出家し勉学に励んでいた日蓮は「人を幸せにするはずの仏教宗派がたくさん咲き乱れているのに、なぜ世の中は更に乱れるばかりなのであろうか。そもそもひとりのお釈迦さまの教えであるはずの仏法に、なぜこれほど多くの宗派が存在し、その優劣を争っているのだろうか」と疑問を持ちました。
日蓮は仏法のすべてを知り尽くそうと、比叡山をはじめ、薬師寺・高野山・仁和寺などで十数年をかけて仏教の教えを徹底的に学びました。その結果、「来世(らいせ)」ではなく「現世(げんせ)」での在り方を問う『法華経』こそが人びとを救う「お釈迦さまの真の教え」だと確信を得たのです。
建長5年(1253)4月28日、日蓮は生まれ故郷である千葉県鴨川市の「清澄寺(せいちょうじ)」において、日の出に向かって、『法華経』に帰依するという意味のお題目「南無妙法蓮華経」を唱えました。「いかなる凡夫にも『仏性』が秘められており『南無妙法蓮華経』と題目を唱えれば「仏性」が顕現する」という思想を説き、「南無妙法蓮華経」の題目こそが末法の人びとを救う唯一の教えであると、法華経の弘通(ぐずう:教えがあまねく広まっていくこと)を宣言したといわれています。
この日、日蓮宗では、この日を「立教開宗」の日とし、「立教開宗会」が行なわれます。立教開宗の日は後世定めたもので、各宗派がそれぞれの立教開宗の日の法会を営みます。
◆日蓮宗ポータルサイト https://www.nichiren.or.jp
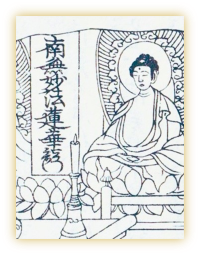
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
法然の浄土宗、親鸞の浄土真宗、一遍の時宗、日蓮の日蓮宗、栄西・道元の禅宗など、鎌倉時代に生まれた仏教は、それまでの護国仏教とは異なり、戦乱や災厄で苦しむ大衆の心を救おうとするものでした。700年も昔の教えが消えずに続いているのは、現代の人びとの心も救う普遍性があるからでしょう。
筆者敬白













