■4月21日 京都、伏見稲荷大社「稲荷祭 神幸祭(おいで)」です。■
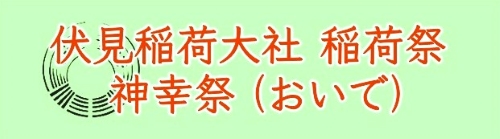
「伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)」は、全国4万社ある稲荷神社(いなりじんじゃ)の総本宮で、1300年以上の歴史があります。式内社(名神大)、二十二社の上七社の一社で旧社格は官幣大社。

稲荷山(いなりやま)の麓に本殿を置き、稲荷山全体を神域としています。崇敬者が祈りと感謝の念を、奥社参道に鳥居の奉納をもって信仰を表す「千本鳥居(せんぼんとりい)」は、国の内外から多くの観光客が訪れる人気スポットです。
主祭神に「宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)」を祀り、「佐田彦大神(さたひこのおおかみ)」「大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)」「田中大神(たなかのおおかみ)」「四大神(しのおおかみ)」を配祀します。

御神徳は「衣食住ノ太祖ニシテ萬民豊楽ノ神霊ナリ」(稲荷谷響記)、また「上ハ天子ヨリ下ハ萬民ニイタル幸福豊楽ノ神明ナリ」(十五箇條口授伝之和解)とあります。平安の昔から、「稲荷山」が民衆信仰の「お山」であり、今日では、商売繁昌・産業興隆・家内安全・交通安全・芸能上達の守護神として信仰をあつめます。
御神号は「イナリ」を「伊奈利」と記。「イナリ」とは、「イネナリ」「イネニナル」のつづまったもので、人間生活の根源であった「稲(イネ)」によって、天地の霊徳を象徴した古語とされています。ちなみに「伏見」は「伏水」だったそうで、伏見の山にはたくさんの滝があります。
◆稲荷祭(神幸祭)
「稲荷祭(いなりまつり)」は、伏見稲荷大社の年中祭事のうち最大の祭礼で、稲荷大神が年にいちど氏子区域を巡幸して、広く御神徳を垂れ給う祭儀です。祭りの起源は古く、藤原資房(ふじわらのすけふさ)の日記『春記(しゅんき)』や藤原宗忠(ふじわらのむねただ)の日記『中右記(ちゅうゆうき)』などにも記述があることから、すでに平安中期には行なわれていたことがわかっています。

4月20日最寄の日曜日に行なわれる「神幸祭(しんこうさい)」で、神璽(しんじ)が御旅所(おたびしょ、油小路九条上ル)に遷されます。それを再び迎えるのが「還幸祭(かんこうさい)」で、5月3日に行なわれます。美しく飾られた30数台の供奉(ぐぶ)列、奉賛(ほうさんれつ)列を従えた5基の御神輿が本殿に向かい、御旅所にとどまっていた神璽が本社に還幸されます。神幸祭を「おいで」、還幸祭を「おかえり」とも呼びます。

古式ゆかしい衣装に身を包んだ供奉者など、数百名の華やかな行列は、美しく飾られた30台程のトラックに乗って約2時間、京都市内の氏子区域を巡幸します。稲荷祭期間中、御旅所は連日氏子の人びとで賑わい、神輿5基が各氏子区内を巡幸します。
伏見稲荷大社
◇京都市伏見区深草藪之内町68
◇JR「稲荷駅」下車すぐ
◇市バス「稲荷大社前」下車 徒歩約7分
◇京阪電車「伏見稲荷駅」下車 徒歩約5分
◇公式サイト:https://inari.jp
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
伏見稲荷の「おいで」「おかえり」は、ちょうどゴールデンウィークに重なります。国内からはもちろん、コロナ後にふたたび戻ってきた外国人観光客も、トラックに載せられて巡幸する神輿や神職の人たちを大変めずらしく見物することでしょう。
日中の日差しはあたたかく、過ごしやすい季節ですが、雷を伴ったにわか雨に遭いやすい時期でもあります。
お風邪などお召しにならないようにお体ご自愛専一の程
筆者敬白













