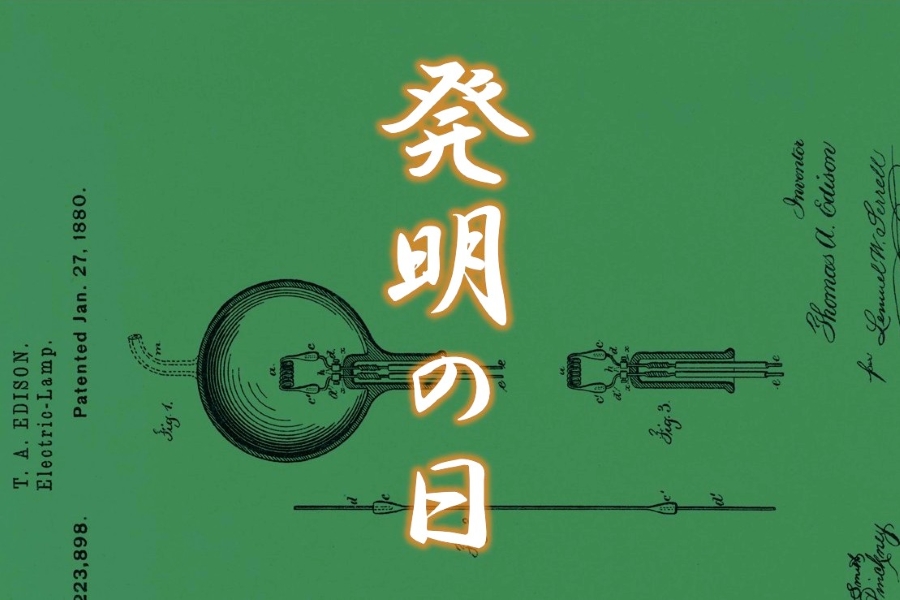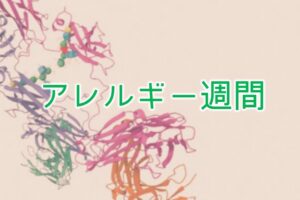■4月18日「発明の日」です。■
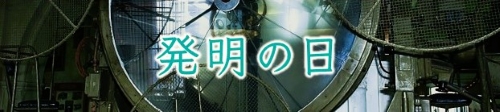
「発明の日(はつめいのひ)」は、明治18年(1885)4月18日、現在の「特許法(とっきょほう)」の前身である「専売特許条例(せんばいとっきょじょうれい)」が、初代特許庁長官を務めた高橋是清(たかはしこれきよ)らによって公布されたことを記念して、昭和29年(1954)に制定された記念日です。「特許制度」をはじめとする産業財産権制度(工業所有権制度)の普及・啓発を図ることを目的としています。

毎年、この日を中心に、特許庁や経済産業省によって様々なイベントが開催されます。また、「発明の日」を含む1週間は「科学技術週間」となっています。
とくに明治時代、「文明開化」のさなか新たに入ってきた西洋の技術に刺激されて、日本でも多くの発明家たちがユニークな発明を次々に生み出しました。しかし当時は、発明品の申請をしても政府から与えられたのは販売の認可だけでした。
明治・大正時代、交通手段として急速に普及した「人力車(じんりきしゃ)」は、明治2年(1869)に和泉要助(いずみようすけ)、高山幸助(たかやまこうすけ)、鈴木徳次郎(すずきとくじろう)らが共同で発明したといわれています。明治3年(1870)、和泉らは東京府より製造・営業の許可を得ましたが、その後も改良を重ねながら再三申請したにもかかわらず、結局「専売特許」を得ることは許されませんでした。

人力車は、日本社会に初めて現れた庶民が利用できる乗り物であり、モータリゼーション以前の移動手段として国の近代化の一助を担ったはずなのですが、肝心の発明者たちが恩恵にあやかることができませんでした。これが新聞報道などで世間に知られ、「特許制度」の必要性を社会全体が認識するようになったのです。和泉らには、明治33年(1900)国から一時金が下賜されました。
現行の「特許法」は、昭和34年(1959)に成立し、公布されました。「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与すること」を目的としています。
人力車とその発明者たちの顛末からもわかるように、特許法が目指す「産業の発達」は発明がもたらす技術革新なくしては達成されず、そのためには発明家の創作意欲を削ぐことがあってはなりません。特許法は、発明者の権利を一定期間保護するかわりに、産業・社会の発展に活かすため発明内容の公開を求めるものです。
特許庁は、昭和60年(1985)4月18日、「専売特許条例」の公布100周年を記念して、日本の歴史的な発明家10名を選定しました。◆「十大発明家」紹介ページ(特許庁)
豊田佐吉(木製人力織機)、御木本幸吉(養殖真珠)、高峰譲吉(アドレナリン)、池田菊苗(グルタミン酸ソーダ)、鈴木梅太郎(ビタミンB1)、杉本京太(邦文タイプライター)、本多光太郎(KS鋼)、八木秀次(八木アンテナ)、丹羽保次郎(写真電送方式)、三島徳七(MK磁石鋼)

アメリカの第16代大統領エイブラハム・リンカーンは、大統領に就任する前年の1859年(日本では安政年間)の演説で、「特許法は、発明者に一定期間、独占権を補償することによって、天才の火に利益という油を注いだ」と述べています。特許制度に支えられた産業を礎として、20世紀のアメリカは大いなる繁栄を遂げました。
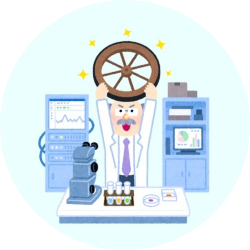
発明家は、それまで世になかった新しいものを考え出し、作り出します。特許制度は、発明者が発明に至るまでに費やした時間や金銭などを回収できるようにし、発明が経済・産業の発展に繋がるようにするための制度ですが、AI時代に入った現在もその理念は変わりません。「発明の日」は、特許制度が社会情勢にあわせて進化し続けながら発明家たちを支えてきたことを知るよい機会です。
◆◆◆◆編修後記◆◆◆◆
これを機に20~30年前の生活様式を思い起こして、今では身近になった数々のイノベーションをあらためて振り返ってみましょう。種々の発明によってこれからの生活様式が、どのように変化するのか興味深く見届けたいものです。
筆者敬白