■4月14日 當麻寺(たいまでら)「練供養(ねりくよう)」です。■
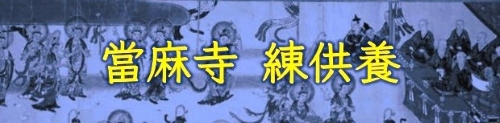
「當麻寺(たいまでら、当麻寺)」は、奈良県葛城市(かつらぎし)にある高野山真言宗・浄土宗の2宗兼帯の寺院です。山号は「二上山(にじょうざん、にじょうさん)」、寺号は「禅林寺(ぜんりんじ)」です。新西国三十三箇所11番、関西花の寺二十五霊場21番(西南院)、仏塔古寺十八尊第8番(西南院)、大和十三仏霊場6番(中之坊)、大和七福八宝めぐり(中之坊)、法然上人二十五霊跡第9番(奥院)。

推古天皇20年(612)、用明天皇の皇子で聖徳太子の弟の「麻呂子親王(まろこしんのう、当麻皇子(たいまのみこ))」が草創した満蔵院禅林寺を、麻呂子親王の孫・当麻国見(たいまのくにみ)が「役小角(えんのおづぬ)」を開山として、天武天皇10年(681)現在の地、二上山の東麓に移転、改称したと伝わります。しかし、もともと奈良時代初期に現在地に創建された寺で、この地に勢力をもつ氏族「当麻氏(たいまうじ)」の氏寺だったという説もあり、有力です。
白鳳時代から天平時代にかけて、金堂、東西両塔、日本最古の梵鐘や石燈籠などが完成されたといわれています。
創建時の本尊は「弥勒仏」、現在の本尊は「當麻曼陀羅(たいままんだら)」です。「中将姫(ちゅうじょうひめ)」ゆかりの古刹として知られ、本尊の當麻曼荼羅は、姫が五色の蓮糸を使って一夜で織り上げたと伝わります。

◆中将姫伝説

中将姫は、奈良時代の右大臣藤原豊成公の娘。5歳のときに実母を亡くしましたが、継母にうとまれ命まで狙われて、14歳で、ひばり山(雲雀山、日張山)に逃れました。父に都へ連れ戻されたあと、『称讃浄土経(しょうさんじょうどきょう:『称讃浄土仏摂受経』の略)』1000巻の写経を成し遂げ、17歳で尼となって當麻寺に入り、「法如(ほうにょ)」という戒名を授かりました。
やがて阿弥陀仏と観世音菩薩が尼に姿を変え姫の前に現れるなどの奇瑞(きずい)を得て、『観経(かんぎょう:『観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)』の略)』に基づいた曼陀羅(諸仏の悟りの境地を描いた絵図)を織ることを決意。百駄の蓮茎を集めて蓮糸を繰り、これを井戸に浸すと糸は五色に染まりました。そしてその蓮糸で、一夜にして一丈五尺(約4m四方)もの蓮糸曼荼羅を織り上げました。
姫が29歳の春、雲間から一丈の光明とともに、阿弥陀如来をはじめとする「二十五菩薩」〔※〕が来迎し、姫は西方極楽浄土へ向かったと伝えられています。
※二十五菩薩(にじゅうごぼさつ):阿弥陀如来とともに来迎する「二十五菩薩」で、観世音、勢至、薬王、薬上、普賢、法自在王、獅子吼、陀羅尼、虚空蔵、徳蔵、宝蔵、金光蔵、金剛蔵、光明王、山海慧、華厳王、衆宝王、月光王、日照王、三昧王、定自在王、大自在王、白象王、大威徳王、無辺身の各菩薩のこと。
◆中将姫ご縁日「練供養会式(ねりくようえしき)」

「練供養会式(ねりくようえしき)」は、當麻曼荼羅と中将姫ゆかりの行事です。葛城郡当麻の生まれと伝わる天台宗の学僧「源信(げんしん:恵心僧都、横川僧都)」は、阿弥陀如来を念じ、生きながら接したいと願い、横川の華台院(けだいいん)で阿弥陀仏迎接会(ごうしょうえ)を始めましたが、これが「二十五菩薩練供養」の始まりと言われています。
毎年4月14日に行なわれる當麻寺の練供養会式(「聖衆来迎練供養会式(しょうじゅらいごうねりくようえしき)」)は、俗に「当麻のお練り」と呼ばれ、中将姫が當麻寺で現身のまま往生したという伝承を演じ再現する行事です。二十五菩薩(聖衆)が、現世に里帰りした中将姫を迎えて、極楽へと導きます。

西の「極楽堂(会式中は本堂を極楽堂と呼ぶ)」と東の「娑婆堂」とのあいだに100m程の橋「来迎橋」が架けられ、真言宗方の僧が極楽堂で、浄土宗方の僧が娑婆堂で、勤行を始めます。
読経の声が聞こえ始めると、面を被って装束に身をかためた「二十五菩薩」が、ふたりの天人に導かれて極楽堂をから娑婆堂へ来迎橋の上を進みます。帰りは、「中将姫」を捧持(ほうじ)した観音菩薩を先頭に、二十五菩薩がつづき、最後に天人が従って、極楽堂に戻ります。
昭和51年(1976)「当麻寺二十五菩薩来迎会」として記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財に選ばれました。現在各地で「練供養」が行なわれていますが、そのほとんどがこの當麻寺の練供養に根源を求めることができます。
當麻寺
◇奈良県葛城市當麻1263中之坊
◇近鉄・南大阪線「当麻寺駅」徒歩約15分
◇公式サイト:https://www.taimadera.org
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

當麻寺といえば「中将姫さま」のお話が有名です。義母を恨むことなくひたすら写経を続けて、仏心に目覚めるという物語です。現代社会にも通じるリアリティーがあります。
ともあれ、読者の皆様、お体ご自愛専一の程
筆者敬白













