■4月10日 平野神社「桜花祭(おうかさい)」です。■
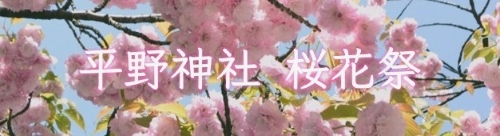
「平野神社」は、延暦13年(794)桓武天皇による平安遷都にともなって、奈良平城京で祀られていた「今木神・久度神・古開神(いまきのかみ・くどのかみ・ふるあきのかみ)」を平野の地に遷座したことに始まります。神社の社格を表した式内社(名神大)で、旧社格は官幣大社。

本殿は4つの社殿が2つに結合された平野造(ひらのづくり)、または、比翼春日造(ひよくかすがづくり)と呼ばれる独特な造りで、重要文化財に指定されています。
祭神4柱は
第一殿に「今木皇大神(いまきすめおおかみ)」(染織・手芸・衣の神)
第二殿に「久度大神(くどのおおかみ)」(竈・台所・食事の神)
第三殿に「古開大神(ふるあきのおおかみ)」(斉火の神)
第四殿に「比賣大神(ひめのおおかみ)」(光仁天皇の皇后である高野新笠のこととされる)
が祀られます。4神は「平野神(ひらののかみ)」と総称されます。「今木」は「今来」のことで、百済(くだら)からの渡来人の祖神という説があります。
◆桜花祭(おうかさい)

平野神社は「北野の梅、平野の桜」と言われる桜の名所で、境内にある約60種4百本の桜は、3月下旬から5月上旬頃まで楽しめます。中でも「平野の夜桜」は有名です。
寛和元年(985)4月10日、時の花山天皇(かざんてんのう)によって臨時の勅祭が遣わされたことが始まりです。「幾世の春を床しく匂えよ」と仰せられ、舞楽「東遊(あずまあそび)」や競べ馬などが催されました。そのとき花山天皇が手ずから植えて以来、桜の名所として名高く、江戸時代には一般庶民に親しまれ、今に至ります。

桜花祭は午前の神事に続き、午後は騎馬や織姫たちの神幸列が繰り出します。町内を練り歩く行列は、さながら時代絵巻のようです。
平野神社
◇京都府京都市北区平野宮本町1番地
◇JR「京都駅」よりバス「衣笠校前」徒歩3分
◇公式サイト:https://www.hiranojinja.com
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
平野神社にはこれから見頃を迎える種類の桜も多く、天気のよい日にはぜひ出かけたいものです。
夜桜見物に興じてお風邪などお召しにならないように、皆様、時節柄お体ご自愛専一の程
筆者敬白













