■4月2日 日光山輪王寺(にっこうさんりんのうじ)「強飯式(ごうはんしき)」です。■
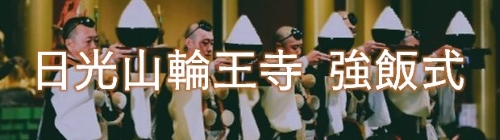
「輪王寺(りんのうじ)」は、栃木県日光市にある天台宗の門跡寺院(もんぜきじいん)〔※〕です。天平神護2年(766)に「勝道上人(しょうどうしょうにん)」〔※〕により開山されたと伝わります。

「輪王寺」という建物自体はなく、本堂(三仏堂)・大猷院(たいゆういん)・慈眼堂(じげんどう)・常行堂(じょうぎょうどう)・大護摩堂(だいごまどう)・護法天堂(ごほうてんどう)・四本龍寺(しほんりゅうじ)、さらに奥日光の中禅寺(ちゅうぜんじ)や温泉寺(おんせんじ)など15の支院の総称です。
明治元年に通達された「神仏分離令」により、日光の参詣所は東照宮、二荒山神社、輪王寺の「二社一寺(にしゃいちじ)」とされましたが、それ以前は、「日光山」全体が山岳信仰の信仰対象であり、修験道の一大霊場でした。

空海(くうかい:弘法大師)や円仁(えんにん:慈覚大師)などの高僧が来山したと伝えられ、鎌倉時代には源頼朝(みなもとのよりとも)をはじめとする源氏の信仰篤く、江戸時代には「家康公」を東照大権現として迎え祀りました。古代の山岳信仰にはじまる日光の歴史が、自然と社殿が一体となった「文化的景観」を形成しているとして、平成11年(1999)、「日光の社寺」が世界遺産に登録されました。そこには日光山内にある二荒山神社、東照宮、輪王寺の103棟の建造物群と、それを取り巻く石垣、階段、参道、そして山や森までが包括されます。
※門跡(もんぜき):皇族・公家が住職を務める特定の寺院、あるいはその住職のこと。寺格のひとつ。一門一派の法跡の意で、元来は、祖師から弟子へと継承されていく宗門の教えの伝統、またその伝統の継承者のことをいった。昌泰2年(899)宇多上皇が出家して法皇となり仁和寺(にんなじ)に入ったことを、後世になって、御門跡(ごもんぜき)と称したことから、皇族・貴族のかかわる特定寺院の格式を表す語となった。
※勝道上人(しょうどうしょうにん):天平7年(735)~弘仁8年(817)。奈良時代末期に日光を開いた僧侶。下野国芳賀郡(現在の栃木県真岡市)に生まれた。少年期から山林修行を行ない、下野薬師寺(しもつけやくしじ)、出流山満願寺(いづるさんまんがんじ、栃木市)で修行を積み、日光を開山。日光二荒山神社(にっこうふたらさんじんじゃ)、立木観音(たちきかんのん:中禅寺)、四本龍寺(しほんりゅうじ)を建立したと伝承される。
◆強飯式

「強飯式(ごうはんしき)」とは、輪王寺の本堂(三仏堂)で行なわれる「強飯頂戴(ごうはんちょうだい)の儀」のことで、全国でも日光山だけに古くから伝わる独特な儀式です。日光山の霊場で修行する山伏(やまぶし)たちが、ご本尊に供えた「お供物」を持ち帰り、里の人びとに分け与えたことが強飯式の始まりと伝わります。
強飯式は
・三天合行供(さんてんごうぎょうく)、採灯大護摩供(さいとうだいごまく)
・強飯頂戴の儀(ごうはんちょうだいのぎ)
・がらまき
の3部からなります。
まず、僧侶・山伏・頂戴人(ちょうだいにん)が約20名の行列をつくり三仏堂に入堂します。「頂戴人」とは、飯を強いられるひとのこと。お堂のすべての扉が閉じられ、壇上に灯された1本の蝋燭で灯りをとります。「三天合行供」の読経とともに、「採灯大護摩供」の炎が上がります。

次いで、裃姿の頂戴人が壇上に並び「強飯頂戴の儀」が始まります。朱塗りの大きな盃になみなみとつがれた酒をいただく「御神酒」、「祈願文の儀」に続いて「強飯」が行われます。
山伏姿の強飯僧が大鉢に山盛りにしたご飯を頂戴人たちの頭上にのせ、「三社権現(さんじゃごんげん)より賜る御供(おとも)!」「七十五杯残さず頂戴しろ!」と責め立てます。大鉢に盛られた飯ひとり分は何と3升! これが「日光責め」と呼ばれる所以です。
先導者より強飯の由来が述べられ、ごちそうとして日光の名物珍味を盛り上げた菜膳がそえられます。そして、毘沙門天(びしゃもんてん)の金甲(きんこう:兜)を頂戴人の頭上に授け、「コリャコリャ」のかけ声とともに、大キセル・ネジレ棒等を手にした山伏が「めでとう七十五杯」と言って、手にした品物を頂戴人の前に出して強飯の儀が終わります。

最後に、強飯頂戴の儀を終えた頂戴人たちが、式でいただいた「福徳を自分だけのものにせず、ほかの人びとにも分け与える」という仏の教えに従い、宝槌(たからづち)や福杓子(ふくしゃもじ)、玩具などの品々を一般の参拝者へ向けて一斉に撒きます。この「がらまき」で強飯式の総仕上げです
強飯式の秘法を受けた者は「七難即滅・七福即生の現世利益疑いなし」といわれ、昔から強飯式に参加すると無病息災・家運長久などのご利益があるとされてきました。
江戸時代には、十万石以上の大名でなければ頂戴人を勤めることは許されませんでした。徳川将軍家の名代や全国の名だたる大名たちが強飯頂戴人に名を連ねました。日光山といえば天皇の皇子を「輪王寺の宮」として迎えた鎮護国家の道場として天下に知られていましたから、大名といえどもおいそれとは儀式に参加できなかったのです。今は申し込みによって頂戴人になることができます。現在でも伝統に従い、十万石以上の大名の格式で頂戴人を迎えます。
日光山輪王寺、本堂(三仏堂)
◇栃木県日光市山内2300
◇JR・東武「日光駅」バス10分
◇公式サイト:https://www.rinnoji.or.jp
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
「飽食」といわれて久しい今日です。スーパーには海外からの輸入食品が並んでいます。強飯式を機に日本の農業、食文化について振り返ってみましょう。食事の前に「いただきます」、食後に「ごちそうさまでした」と感謝の気持ちを込める日本の食文化を世界中に広げたいものです。
季節の変わり目です。時節柄お体ご自愛専一の程
筆者敬白













