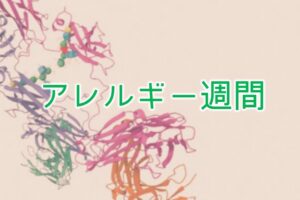■12月1日「鉄の記念日」です。■
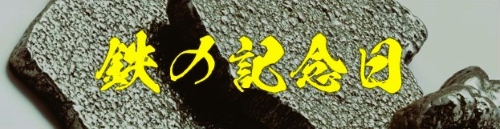
安政4年(1857)、南部藩(現在の岩手県)の「釜石市」に日本で最初の「洋式高炉(ようしきこうろ)」が造られ、12月1日に初めて火が入れられました。「鉄の記念日」はこれを記念して昭和32年(1957)に制定されたものです。
(※薩摩藩のほうが早かったという説もあります)

釜石の高炉を造った鉱山学者「大島高任(おおしまたかとう)」は日本の「近代製鉄の父」と呼ばれています。大島の高炉は明治27年(1894)まで運用されました。
この時の高炉の跡「橋野高炉跡(はしのこうろあと)」(岩手県釜石市橋野町)は後年、発掘調査され、昭和32年(1957)国の史跡に指定、平成27年(2015)には「明治日本の産業革命遺産 製鉄・鉄鋼、造船、石炭産業」の構成資産として「世界遺産」に登録されました。
◆鉄の種類と製造工程
鉄は鉄鉱石や砂鉄などから作ります。特殊な例として「隕鉄(いんてつ)」(主成分が鉄である隕石)から作る場合もあります。これは超高級品です。
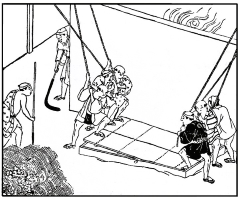
鉄はみなさんもよくご存じのように、非常に錆びやすいものです。錆びるというのはつまり酸化するということ。つまり自然界の鉄はほとんどが「酸化鉄」の状態です。
製鉄の工程では、この酸化鉄を熱して熔かすことにより還元し、金属の状態に戻します。日本の古代の製鉄法での行程はいわゆる「たたら」によって行なっていました。現在でも、刀剣用などの高級品は「たたら」により製造されています。
たたらは良質の「鋼(はがね)」を作ることができるのですが、量産できないという欠点がありました。そこで産業革命以降の大量の鉄を必要とした時代に、大量の鋼を作る方法が考案されました。

この近代製鋼の工程では、最初に「鉄鉱石」を燃料の「コークス」や酸度調整のための「石灰」などといっしょに「高炉」に入れて加熱します。大島高任の高炉ではコークスではなく「木炭」を使っていました。木炭のほうが良質の鋼を生産できるのですが、経費と生産効率の問題がありました。
高炉で還元された鉄は、コークスの炭素を吸収して、炭素濃度の多い鉄になります。これを「銑鉄(せんてつ、crude iron)」といいます。このままではもろくて使えないため、今度はそれを熔けたまま「転炉(てんろ)」に入れて空気を送り込み、炭素を燃やして炭素濃度を下げます。

基本的には一定の炭素濃度のものを「鋼(はがね・こう、steel)」といい、純度の高いものを「練鉄(れんてつ、wrought iron)」といいます。転炉を使う方法では、空気を送り込む時間を調整することで炭素濃度を目的に合わせて正確に調整できます。
そして、転炉でつくられた鋼に焼き入れ・焼き戻し・焼き鈍し〔※〕といったおなじみの処理を加え、引き出し・押し出し〔※〕などの方法で、鋼板(こうはん)・棒材(ぼうざい)・各種形鋼(かたこう)などを製造します。
※焼き入れ:鉄を固くするため、高温に熱してから急冷
※焼き戻し:粘り強くするため、低温で熱してからゆっくり冷やす
※焼き鈍(なま)し:高温で熱してゆっくり冷やすことで、柔らかさを加える
※押し出し、引き出し:細い口から押し出して断面の形に成型
▼ステンレス
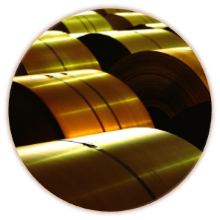
基本的には鉄というのは純鉄の状態では使いにくいので、必ず何かの不純物を混ぜます。つまり私たちの身の回りにある鉄は全て「鉄合金」です。最近特に多いステンレスはクロムとニッケルを混ぜて錆びにくくしています。
▼「鉄」と「鐵」
「鉄」は戦後、当用漢字制度のもとで使われるようになった俗字で、本字は「鐵」です。この字は「金の王なる哉」という意味であるとされます。金属の王様が鐵だというわけです。民営化した「国鉄」が、「国鐵」だったら安泰だったかもしれないが「金を失う」では黒字になる訳がなかった、などといわれることも。今でも「鉄」という字を嫌って「金」に「矢」と書いて社名とする企業があります。