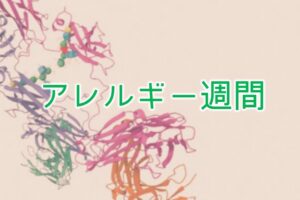■11月9日「太陽暦採用記念日」です。■
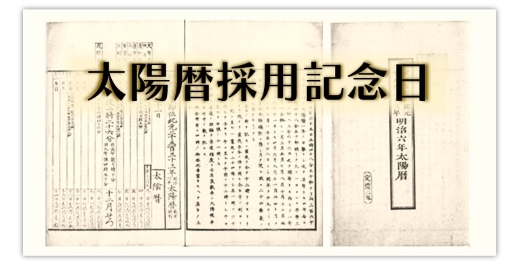
「太陽暦(たいようれき)」とは、地球が太陽の周囲をひと回りする時間(約365.24219日)を「1年」と定めた暦で、「陽暦(ようれき)」あるいは「新暦(しんれき)」ともいいます。太陽の黄道上の運行、季節の交代する周期をもとに作られた「暦法(れきほう)」で、一太陽年(一回帰年)の長さに基づいて「暦年」を設定します。月の運行(満ち欠け)による周期は考慮しません。現在多くの国で使われている「グレゴリオ暦」は太陽暦です。

明治5年(1872)11月9日、それまでの月の運行を基準とする「太陰暦(たいいんれき、旧暦)」を廃止して「太陽暦(新暦)」を採用するという詔書(しょうしょ)が出され、「西暦(せいれき)」を基準とすることになりました。
そのため、明治5年(1872)12月2日でその年が終わりになり、本来なら12月3日になる翌日が突然、明治6年1月1日になったのです。
準備期間がほとんどなかったので国内は混乱しましたが、「福澤諭吉(ふくざわゆきち)」などの学者は合理的な太陽暦を支持し、普及させるための書物を著したりしました。
ちなみに、改暦せずに翌年を迎えた場合、旧暦でいう「閏月(うるうづき)」(太陰太陽暦で、ある月が終わったあとに続いてもういちど繰り返す同じ月のこと)のある年でした。閏月があると1年は13ヶ月になります。当時、財政難だった明治政府は、公務員の年13回の給料支払いを回避したかったのが本音かもしれません。太陽暦に改暦した結果、公務員2ヶ月分の給料を節約できた計算になります。

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
いつの時代も政府は、目先の都合ばかりに目を奪われがちです。年号が変わり令和になっても、喫緊の課題への対応と、長期的な展望を要する課題への取り組みをしっかり区別せず、打ち出す政策がすべて場当たり的な印象を拭えません。
太陰暦から太陽暦に替わっても、春夏秋冬の訪れに変化はありません。いつの世になっても、四季を楽しみながら日々の生活にメリハリを持たせましょう。
季節の変わり目です。お体ご自愛専一の程
筆者敬白