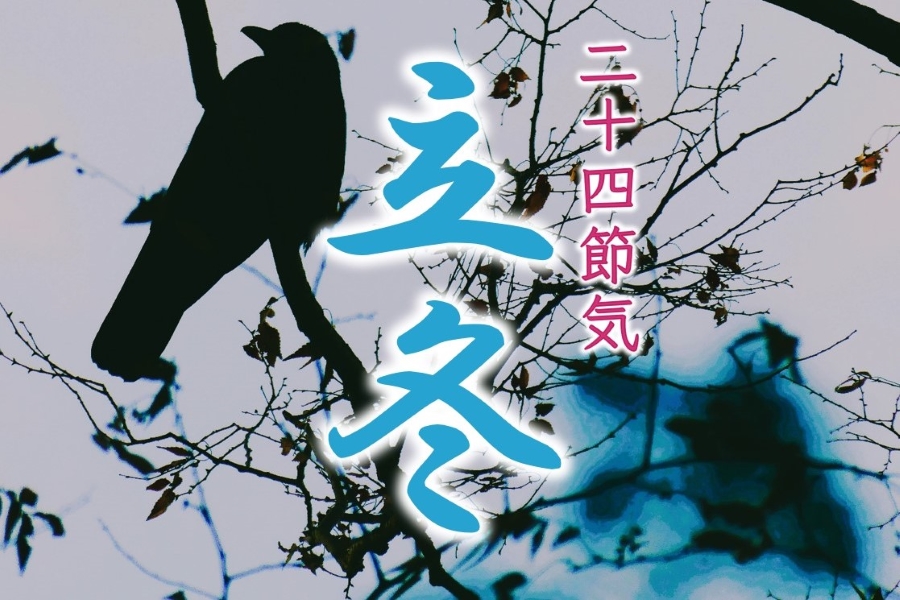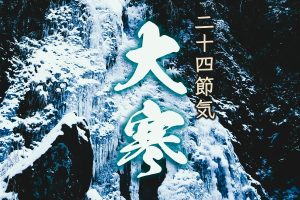◆二十四節気◆令和7年(2025)11月7日「立冬(りっとう)」です。◆

11月7日13時04分「立冬」です。旧暦10月、亥(い)の月の正節で、天文学的には太陽が黄経225度の点を通過するときをいいます。四季の「冬」に入る始まりの二十四節気で、太陽の光もいちだんと柔らかく感じ、日足も目立って短くなり、夕暮れの訪れが早く感じられます。大雪山(たいせつざん)や八甲田山(はっこうださん)からは初冠雪の便りが届き、冬の気配が濃くなります。

晩秋から初冬のこの頃、「木枯らし(こがらし)」が吹きます。木の葉を吹き散らし、木を吹き枯らす、強く冷たい風です。「凩」とも書きます。気象庁は「立冬」前後に吹く、毎年最初の「木枯らし」を「木枯らし一号(こがらしいちごう)」として発表します。「西高東低」の冬の気圧配置になり、北西の季節風がシベリアからの寒気を運んできます。
山では「綿雲(わたぐも、積雲)」が発生し、「時雨(しぐれ)」がしとしと降ります。雲の流れが速く、見事な虹が出てはまた雨が降る「時雨虹(しぐれにじ)」が現れます。「時雨虹」に出会うと、空が表情豊かに語りかけてくるようです。
「暦便覧」では「冬の気立ち始めて、いよいよ冷ゆれば也」と説きます。北国では大地が凍り始め、朝に霜柱が見られることも。「山茶花(さざんか)」が可憐に咲き始めます。「立冬」は「冬立つ」「冬来る」などとともに冬の季語になっています。
あらたのし冬たつ窓の釜の音ーー上島鬼貫
凪ぎわたる地はうす眼して冬に入るーー飯田蛇笏
立冬や手紙を書けば手紙来るーー山口青邨
◆◆「七十二侯」◆◆
◆初候「山茶始開(つばきはじめてひらく)」
◇山茶花(さざんか)の花が咲き始める。「山茶(さんちゃ)」は「つばき」の漢名。
◆次候「地始凍(ち はじめてこおる)」
◇大地が凍り始める。
◆末候「金盞香(きんせんかさく)」
◇水仙の花が咲き、香りが漂い始める。「金盞(きんせん、きんさん)」は、金で作ったの杯のことで、「水仙」の異名。
◆◆「11月の花」◆◆

◆「山茶花(さざんか)」 ツバキ科ツバキ属の常緑小高木 学名 Camellia sasanqua
原産地は日本。江戸時代に長崎からヨーロッパへ持ち出され、西欧で広まりました。学名・英名ともに「サザンカ」です。
開花時期は10月から12月ごろ。晩秋から初冬にかけて咲き出し、よい香りです。椿(つばき)によく似ていますが、椿は花全体が落ちるのに対し、山茶花は花びらが一枚ずつ散っていきます。
耐陰性、耐潮性があり、刈り込みに耐えるので生け垣にします。公害にも強く、庭園や公園、道路の植栽としても広く植えられます。
花言葉は「ひたむき」「困難に打ち勝つ」など。
山茶花を雀のこぼす日和かなーー正岡子規
霜を掃き山茶花を掃く許りかなーー高浜虚子
◆「茶の木(ちゃのき)」 ツバキ科ツバキ属の常緑低木 学名 Camellia sinensis 「茶樹」「茶」とも。

起源はインド、ベトナム、ミャンマー、中国西南部などとされるが詳細は不明。熱帯から温帯のアジアに広く分布しています。「茶畑」での栽培のほか、野生種もあり、日本では伊豆半島や九州で自生しています。
新枝は緑色で細かい毛があり、次び年、枝は褐色になります。葉は互生で、長さ4~10cmの細い楕円形、鋸歯(きょし)あり。秋、2~3cmの小さな白い花を1~3個開きます。萼片(がくへん)、花弁ともに5枚。果実は翌秋熟し、暗褐色の大きな種子を結びます。
花言葉は「追憶」「純愛」。
茶の花のわづかに黄なる夕べかなーー与謝蕪村
茶の花に人里ちかき山路かなーー松尾芭蕉
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

暦の上では「立冬」から本格的な冬に入ります。『四神相応図』では冬の色は黒、守護は玄武、方位は北です。やがて来る春に備えて力を蓄える時期です。
例年この時期から、武漢肺炎、インフルエンザ、風邪が流行します。早めの予防接種、日ごろの手洗い・うがいを心がけましょう。
油断からお風邪などお召しにならないよう、お体ご自愛専一の程
筆者敬白