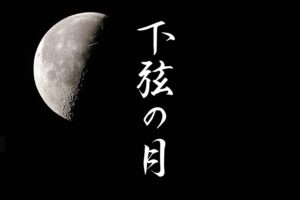■11月2日(旧9月13日)「十三夜(じゅうさんや)」です。■
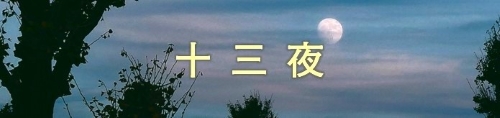
「十三夜(じゅうさんや)」とは、旧暦9月13日の夜のこと。十三夜の月は、旧暦8月15日の「中秋の名月(十五夜)」とならんで美しいとされ、「お月見」を楽しむ習わしがあります。
三十六歌仙のひとりとして名高い「凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)」の家集『躬恒集(みつねしゅう)』によると、延喜19年(919)9月の十三夜に、内裏で月の宴が催されたとあり、それが「十三夜」の始まりだったともいわれ、あるいは、同日に「宇多法皇(うだほうおう)」が「十五夜」の宴に次いで「観月(かんげつ)の宴」を催し、この夜の月を「無双」と称えたことから毎年、十三夜の月を賞するようになったともいわれます。

8月の「十五夜」を「中秋の名月」とするのに対して、9月の「十三夜」を「後の月(のちのつき)」「後の月見(あとのつきみ)」と呼びます。「十五夜」と同じく、団子・芋・栗・柿・枝豆などを供えます。

上方では塩ゆでの枝豆のみを供える地域もあり、「豆名月」とも呼びます。長野の北安曇(きたあずみ)では「小麦の月見」といい、この日が好天でお月見ができれば小麦が豊作だとされます。福岡の糟屋(かすや)では「女名月(おんなめいげつ)」といって女性が幅をきかすのだとか。
十五夜
・中秋の名月
・芋名月
十三夜
・後の月(のちのつき)、後の月見(あとのつきみ)
・栗名月
・豆名月
・女名月(おんなめいげつ)
・小麦の月見
十五夜は中国伝来ですが、十三夜は日本古来からの風習で平安時代に広く伝わりました。時期から秋の収穫祭のひとつではないかと考えられています。十三夜の月を拝むと、「成功」「出世」「財運」「子宝」に恵まれるともいわれます。
十五夜にお月見をしたら、十三夜にもお月見を催すものとされています。どちらかを見逃すと「片見月(かたみづき)」「片月見」と呼び、野暮であるとか不吉であるなどといわれていました。
◆月待ち

旧暦では十三夜、十五夜、十六夜(いざよい)、十七夜、二十三夜(下弦の月)、二十六夜など特定の月齢の晩に、人びとが集い(多くは女性のみ)、お供え物をして月を拝み、会食する「月待ち」の風習がありました。月待ちの「待ち」は「月の出るのを待つ」ではなく「月をマツル(祀る)」の意です。
現在は「太陽暦」(男性:太陽)を採用していますが、「月待ち」の風習から旧暦(太陰暦:女性:月)では、月と女性が尊ばれていたのがわかります。
各地に「二十三夜塔」や、それにちなむ地名が多く残っていることから、特定の月齢のなかでも「二十三夜待ち」がとくに盛んだったようです。二十三夜は「下弦の月」で、満月のあとの半月が特別なものとされていたためです。
江戸時代には、正月と7月の「二十六夜」に、海を臨む高台へ昇り、月が出るのを待って徹夜する行事が記録に残されています。歌川広重『東都名所』にも、高輪(たかなわ)の海岸で「二十六夜」の月の出を待つ人びとで賑わう様子が描かれた一枚があります。正月、5月、9月、11月に神事として「観月」する土地や地域が今でも残っています。

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

江戸時代の臨済宗の禅僧「仙厓(せんがい)」はユーモラスな書画を多く残し、その代表作のひとつが、子どもと戯れる布袋さまがほほえましい「指月布袋画賛(しげつほていがさん)」です。賛文の「を月様幾ツ 十三七ツ」の「十三」は十三夜、「七ツ」は七つ時のこと。月の姿を描くことなく、「月が遠くはるか彼方にあるように悟りの境地には容易に達することはできない」という禅の教えを表現し、わらべうたを歌うような愛らしさで説いています。
照明が十分でなかった時代、真っ暗な闇夜を明るく照らす月は、人びとにとって非常に大切なものであったことは想像に難くありません。月にまつわる風習がたくさん残っているのも、むかしのひとの月の恵みへの感謝の大きさゆえなのでしょう。
筆者敬白