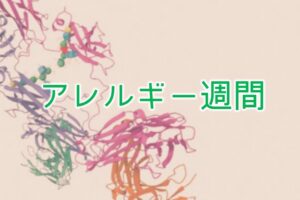11月です。旧暦の11月を「霜月(しもつき)」といいます。文字どおり「霜が降る月」のことで、北から寒冷前線が南下するため気温がぐっと下がり、ときには局所的に悪天候に見舞われることも。「雪待月(ゆきまちづき)」「雪見月(ゆきみづき)」ともいいます。
■11月1日「灯台記念日」です。■

「灯台記念日(とうだいきねんび)」は、日本最初の西洋式灯台「観音崎灯台(かんのんさきとうだい)」の起工日、明治元年(1868)11月1日にちなみ、昭和24年(1949)海上保安庁により制定されました。「初点灯」は明治2年(1869)1月1日です。「観音崎灯台」は、神奈川県横須賀市、三浦半島東端の観音崎にたつ中型灯台です。白亜の八角形の灯台は、大正時代に2度、地震で倒壊しましたが、そのたびに再建され、現在は3代目。東京湾、浦賀水道を照らし、東京湾の入口で海上交通の安全に寄与しています。
「灯台記念日」には、各地の灯台が無料で参観でき、普段公開されていない灯台の内部も特別に公開されます。各地の海上保安部による記念行事が行なわれます。
◆「灯台記念日」(海上保安庁):https://www.kaiho.mlit.go.jp/soshiki/koutsuu/lighthouse-anniversary.html
◆公益社団法人「燈光会」:https://www.tokokai.org
■11月1~7日「教育・文化週間」です。■
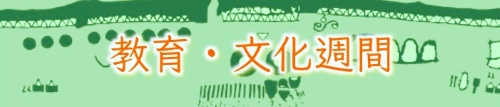
「教育・文化週間」は、わが国の教育・文化に関して広く国民の理解と関心を深めるという趣旨で、昭和34年(1959)に閣議了解され、「文化の日」を中心に毎年開催されています。
期間中、「文化功労者」顕彰式や「文化庁芸術祭」などが開催されるほか、文部科学省や教育委員会が中心となり、美術館や博物館をはじめとする各地の文化施設で特別展や施設の無料公開などが行なわれます。また、さまざまな体験活動や公開講座等の行事が各地で催されます。
◆「教育・文化週間」(文部科学省):https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/kyoiku-bunka/
11月1日が「古典の日」でもあることから、「文化財保護強調週間」(文化庁)も合わせて実施され、各地で文化財の公開や展示会、史跡めぐり等の行事が行なわれます。
■11月1日「新米穀年度(しんべいこくねんど)」です。■

「米穀年度(べいこくねんど)」とは、日本で米などの穀類の取引に関わる年度のことで、11月1日~翌年10月末日の1年の期間の収穫を基準に区分しています。
日本の主食である「米」は、農林水産省が、「食糧管理法」に基づいてその生産や流通までを管理してきました。「食糧管理法」は、平成7年(1995)、WTO(世界貿易機関)設立協定の農業関係の規定が日本国について発効したことにともない廃止され、現在は「食糧法(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律)」において米などの主要な食糧の需給・価格の安定のための措置が定められています。
ちなみに、市場に流通している自主流通米は「○○年度産」という表示がされていても、米の収穫時期に幅があるため、実際に収穫された時期と米穀年度は必ずしも一致しないなど、実情との齟齬が生じています。「新米」「古米」という通俗的な区分は、基準が曖昧なので注意したいところです。米の需要量については、平成15年(2003)以降、当年7月から翌年6月までの1年間をもって算出しています。
■11月1日「計量記念日」です。■

経済産業省では、社会全体の計量制度に対する理解の普及を図るため、昭和27年(1952)から「計量記念日」を定めています。現在は、現行の「計量法」が施行された11月1日を「計量記念日」とし、11月を「計量強調月間」として、計量制度の普及や社会全体の計量意識の向上を目指しています。
「計量記念日」は、経済産業省の4大記念日のひとつです。
経済産業省4大記念日
・電気記念日(3月25日)
・発明記念日(4月18日)
・貿易記念日(6月28日)
・計量記念日(11月1日)
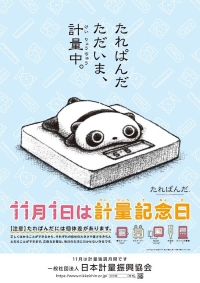
「計量法」は、長さ・質量・角度・面積・体積・速さ・加速度・圧力・熱量などの計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする法律です。
「計量強調月間」中、全国の計量行政機関や計量団体の主催で、計量器の展示、計量ゲーム、シンポジウム等の計量に関するイベントが催されます。日本計量振興協会は、「計量啓発標語」の募集、小学生から募集した「何でもはかってみようコンテスト」の表彰などを行ないます。
◆「計量記念日のご案内」(日本計量振興協会):http://www.nikkeishin.or.jp/kinenbi.html