■10月29日 福岡、香椎宮(かしいぐう)「例祭」です。■
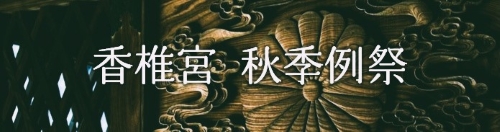
福岡市東部の副都心のひとつ、東区「香椎(かしい)」に鎮座する「香椎宮(かしいぐう)」は、仲哀天皇9年(200)「神功皇后(じんぐうこうごう)」が自ら祠を建て、「仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)」の神霊を祀ったのが起源と伝わります。別表神社。旧官幣大社であり、「勅祭社」です。

御祭神として
主神
・「仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)」:足仲彦天皇(たらしなかつひこのすめらみこと)。第14代天皇。日本武尊(やまとたけるのみこと)の第2子。
・「神功皇后(じんぐうこうごう)」:気長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)。仲哀天皇皇后。第9代開化天皇の曾孫。
配祀神
・「応神天皇(おうじんてんのう)」:誉田別皇(ほむたのすめらみこと)。第15代天皇。仲哀天皇の第4子、母は神功皇后。
・「住吉大神(すみよしおおかみ)」
の4柱を祀ります。
「香椎」は、神功皇后の伝承とも縁が深く、古い歴史を持つ一方で、昭和初期より始まった「香椎潟(かしいがた)」の埋め立てに伴い著しく都心化が進んだ地域です。「香椎潟」「香椎の潟(かしいのかた)」は
いざ子ども香椎の潟に白たへの袖さへ濡れて朝菜摘みてむ――大伴旅人
時つ風吹くべくなりぬ香椎潟潮干の浦に玉藻刈りてな――小野朝臣老
行き帰り常にあが見し香椎潟明日ゆ後には見むよしもなし――宇努首男人
と『万葉集』にも歌われた遠浅の干潟で、埋め立て以前は、西鉄「香椎宮前駅」そばの香椎宮「頓宮」の建つ丘のふもとまで海岸線が迫っていました。「香椎」の名は、敷地内に香ばしい香りの「棺懸(かんかけ)の椎」が立っていたことに由来、あるいは、仲哀天皇が熊襲征伐のため筑紫に行った際、土地の人びとが香ばしい椎の菌(シイタケ)を献じたことからという説もあります。

境内には、仲哀天皇の筑紫の行宮(あんぐう)であった「橿日宮(かしいのみや、訶志比宮)」の跡地があり、そこには御神木「香椎」が立っています。神功皇后自らが植えられたという御神木「綾杉(あやすぎ)」は、『新古今和歌集』で「ちはやふる香椎の宮のあや杉は神のみそきにたてる成けり」と詠まれた老木です。
養老7年(723)神功皇后自身の神託により、朝廷が社殿の造営を始め、翌年の神亀元年(724)に竣工しました。この2つの廟をもって「香椎廟(かしいびょう)」とします。延喜式神名帳の記載はありませんが、『日本書紀』の続編とされる『続日本紀』などには「香椎廟」「香椎宮」「樫日廟」などと書かれています。
◆勅祭社(ちょくさいしゃ)

明治時代に官幣大社となり、終戦までは「勅祭社」に指定され、現在も、10年にいちど「吉日」を選定し、宮内庁より勅使が遣わされます。皇室の崇敬篤く、三重の「伊勢神宮」、京都の「石清水八幡宮」、福井の「氣比神宮」とともに「四所宗廟(ししょそうびょう)」「本朝四所」のひとつに数えられます。
秋の「例祭」は、宮中(天皇陛下)御献納の神饌幣帛料を捧げ、平和と幸福を祈る最も重大な神事で、10月29日に斎行されます。
令和6年(2024)、香椎宮は1300周年を迎えました。前年に国の重要文化財「本殿」の修理を終え、秋の例祭の日に「創建1300年記念祭」が行なわれました。本殿は、享和元年(1801)第10代福岡藩主「黒田斉清(くろだなりきよ)」によって再建されたもの。「香椎造(かしいづくり)」と呼ばれる独特な建築様式の建物です。
香椎宮
◇福岡県福岡市東区香椎4-16-1
◇JR「香椎神宮駅」徒歩4分
◇JR「香椎宮前駅」徒歩12分
◇福岡都市高速「香椎浜ランプ」約10~15分
◇公式サイト:https://kashiigu.com
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

香椎宮には不老不死の「不老水(ふろうすい)」が湧く水源があります。武内宿禰(たけしうちのすくね、たけうちのすくね)が、この湧水を仲哀天皇、神功皇后への料理に使い、自分の食事やお酒を作るのにもこの水を使っていました。そのおかげか武内宿禰は300歳とも360歳ともいわれるほど長寿だったと伝わります。
◆環境省 名水百選(昭和60年選定)「不老水」:https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/meisui/data/index.asp?info=83
◆「不老水」(福岡県観光WEB):https://www.crossroadfukuoka.jp/spot/12594
湧水は香椎宮本殿から住宅街を経て山の手へ徒歩13分ほど行ったところにあり、水源には祠が建てられています。参詣の際には是非お持ち帰り下さい。開門時間は10:00~15:00。1グループ(1家族)2Lペットボトル2本までだそうです。
筆者敬白













