■10月21日 宇都宮二荒山神社(うつのみやふたあらやまじんじゃ)「例祭(秋山祭)」です。■
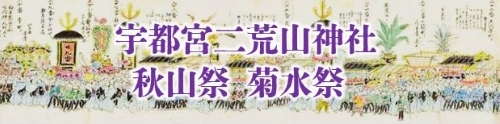
古く「宇都宮大神宮」と呼ばれた「宇都宮二荒山神社(うつのみや ふたあらやまじんじゃ)」は、下野国(しもつけのくに)一宮、宇都宮の中央に位置する神社です。日光の「二荒山神社(ふたらさんじんじゃ)」と区別するため「宇都宮」を冠して呼ばれます。式内社(名神大社)論社、神社本庁の別表神社、旧社格は国幣中社です。

御祭神は「豊城入彦命(とよきいりひこのみこと)」です。「大物主命(おおものぬしのみこと)」「事代主命(ことしろぬしのみこと)」を合わせて祀ります。
「豊城入彦命」は、「崇神天皇(すじんてんのう)」の第一皇子です。「豊城命(とよきのみこと)」とも。「東国(あづまのくに)」の鎮撫・治定にあたったとされ、「毛野(けぬ、けの)」(群馬県と栃木県南部を合わせた地域)を支配した豪族「上毛野氏(かみつけのうじ)」「下毛野氏(しもつけのうじ)」の始祖と伝わります。そして現在、「宇都宮の始祖」としてなおも変わらず郷土の人びとに仰がれています。
「上野国(こうずけのくに:群馬県)」「下野国(しもつけのくに:栃木県)」には、「毛野」の「毛」という字はもうありませんが、「上毛(じょうもう)」や「東毛(とうもう)」「中毛(ちゅうもう)」「西毛(せいもう、さいもう)」「北毛(ほくもう)」「両毛(りょうもう)」といった地域名に残っています。「鬼怒川(きぬがわ)」は、かつては「毛野川(毛野河)」であり、「鬼怒川」は明治以降の宛て字です。

『日本書紀』によると、崇神天皇48年(紀元前50)に、天皇がふたりの皇子「豊城命」と「活目尊(いくめのみこと)」に勅(みことのり)し、皇子たちへの慈愛は等しく、どちらを皇太子とすべきか決められないので、ふたりの見る夢で占おうと言って、夢占いをさせました。そこで兄弟は沐浴をして身をきよめ、祈って、眠りました。
明け方、兄の「豊城命」が、「わたしは三諸山(みもろのやま)に登り、東に向かって8回矛(ほこ)を突きだし、8回刀を振りました」と、夢のお告げを奏上しました。「御諸山」とは、現在の「三輪山」のことです。
弟の「活目尊」は、「わたしは御諸山の嶺に登って、縄を四方に張り、粟(あわ)を食べる雀を追い立てました」とお告げを奏上しました。
崇神天皇は夢合せをし、2皇子に言いました。「兄の豊城命は東の方向だけに向いていた。したがって東国を治めなさい。弟の活目尊は四方すべてに臨んでいた。わたしの位(たかみくら)を継ぎなさい」
「活目尊」は崇神天皇の後を継ぎ、「垂仁天皇(すいにんてんのう)」となりました。「豊城命」は、東国を治め、「上毛野の君・下毛野の君(かみつけめのきみ・しもつけめのきみ」の始祖となりました。

社伝によると、仁徳天皇41年(353)、毛野国が下野国と上野国に分けられた際、下野国の国造(くにのみやつこ)に任じられた「奈良別王(ならわけのきみ)」が曽祖父「豊城入彦命」を地域の氏神として祀ったのが「宇都宮二荒山神社」の始まりとされています。「下野一の宮」と呼ばれていたことが、「宇都宮」という名の由来ではないかという説もあります。
「豊城入彦命」は、郷土の祖神、総氏神さまとして篤く信仰されています。武徳にも優れ、武家の信仰も篤く、藤原秀郷(ふじわらのひでさと)、源頼義・義家(みなもとのよりよし・よしいえ)親子、源頼朝(みなもとのよりとも)、徳川家康(とくがわいえやす)などの武将たちが戦勝祈願し、神領や宝物の寄進、社殿改築を行ないました。
宇都宮は湧き水が多く、江戸時代の人びとは主な湧き水を7つ選び、「七水(しちすい)」と呼んで名所としました。「宇都宮二荒山神社」の境内には、七水のひとつ「明神の井(みょうじんのい)」が湧き出ています。この水は明治天皇の献茶の湯にも使われた名水です。また、書道などの技芸の水に使うと上達すると伝わります。
◆例祭「秋山祭」

毎年10月21日、例祭「秋山祭(あきやまさい)」が行なわれます。年に一度の例大祭で神社の重儀です。前日より準備、社殿の飾り付けを行ない、神職は参籠して奉仕します。当日は役員総代のほか、関係者が多数参列します。
◆菊水祭
「菊水祭(きくすいさい)」は、例祭「秋山祭」の付祭(つけまつり)として発展しました。10月の最終土曜日・日曜日に行なわれます。寛文13年(1673)、火難を免れたことを宇都宮大明神に感謝する「神賑(かみにぎわい、しんしん)行事」が始まりといわれています。江戸時代、付祭は隆盛をきわめ、「江戸の天下祭」(山王祭、神田祭)に匹敵する規模になりました。重陽の節句に行なうようになったことから「菊水祭」という名称になりました。
明治期に入ると、「菊水祭」は神輿渡御を中心にした祭礼行事となり、参加する山車や屋台が増え、明治17年()の栃木県庁新設祝賀行事では40町が自慢の山車・屋台を繰り出しました。

現在、「豊城入彦命」が神輿に乗って宇都宮のまちを渡御する「鳳輦渡御(ほうれんとぎょ)」や「流鏑馬(やぶさめ)」などが行なわれ、数年おきに山車や屋台が鳳輦渡御のお供をします。
宇都宮二荒山神社
◇栃木県宇都宮市馬場通り1-1-1
◇JR「宇都宮駅」よりバス5分
◇東武宇都宮線「東武宇都宮駅」徒歩約10分
◇東北自動車道「鹿沼IC」から約20分
◇東北自動車道・日光宇都宮道路「宇都宮IC」から約25分
◇公式サイト:http://futaarayamajinja.jp
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

宇都宮二荒山神社の「明神の井」は、宇都宮七水のなかでも随一といわれるきれいな水で、口に含むと甘みが感じられます。東京からの祐気採り・お水採りは、北、もしくは北東です。
「餃子の街」宇都宮にちなんで、フライパンから箸でつまみあげる、ユニークな「餃子おみくじ」もあるそうです。
筆者敬白













